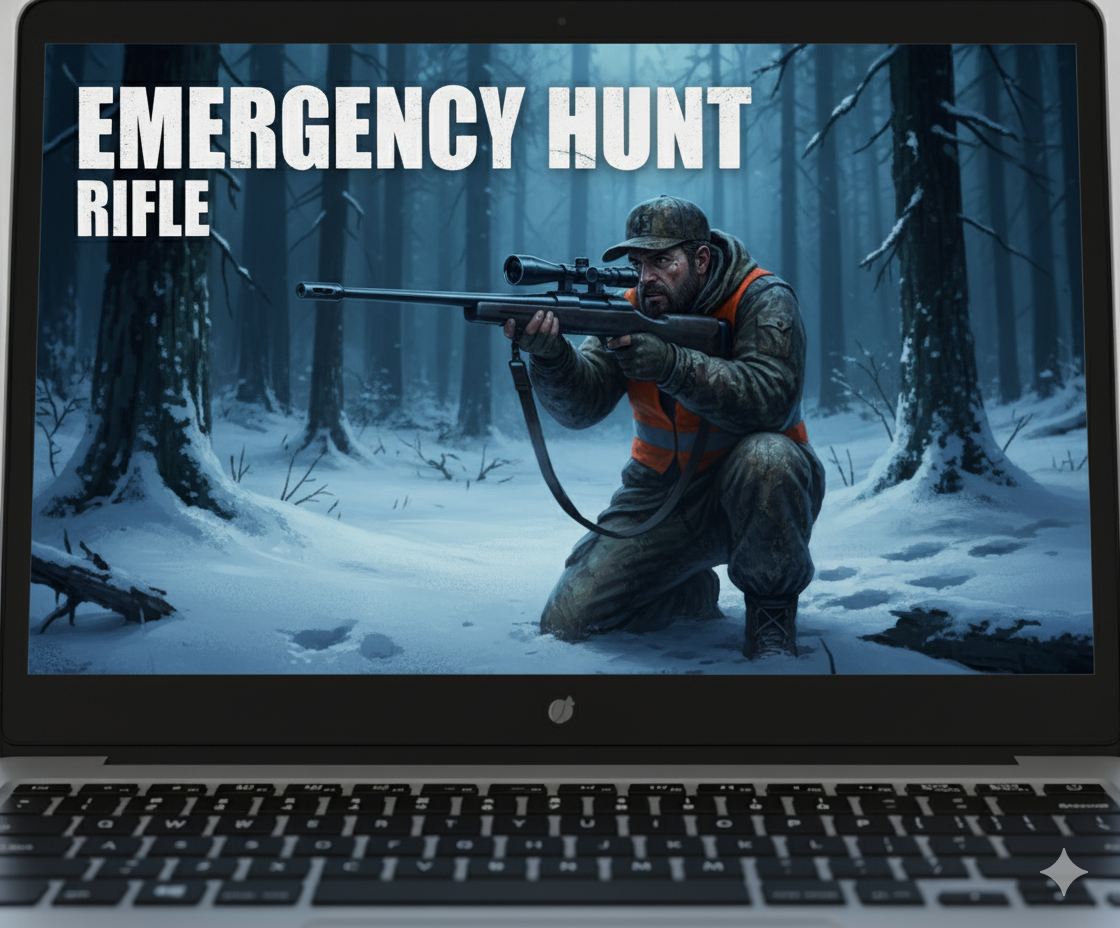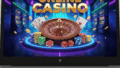緊急時の猟銃使用とは? 熊の市街地出没とハンターの役割、法的な背景を徹底解説
「緊急猟銃」の概要
「緊急猟銃」という言葉は、一般的な法律用語や正式な名称ではありません。
しかし、恐らくこれは、近年日本各地で深刻化している熊(クマ)などの危険な野生動物が市街地や人里に出没した際、人の生命や身体を守るために緊急的に猟銃が使用される状況を指していると考えられます。
日本において猟銃の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により極めて厳しく制限されています。
その厳格な管理下にある猟銃が、どのような法的根拠と手順に基づき、「緊急時」に使用されるのか、その概要と背景を解説します。
これは、私たちの安全を守るための最後の手段であり、多くの課題も抱えています。
「緊急猟銃」の詳細
なぜ今「緊急時の猟銃使用」が注目されるのか?
近年、ツキノワグマやヒグマが、従来は考えられなかった市街地や住宅街にまで出没する「アーバンベア(都市型クマ)」問題が全国的に急増しています。
これに伴い、人が襲われる人身被害も過去最悪のペースで発生している地域もあります。
野生動物の保護も重要ですが、市民の生命という最優先の法益が差し迫った危険にさらされた場合、その危険を排除するための「緊急的な措置」が必要となります。
この最終手段が、猟銃による駆除(射殺)です。
誰が「緊急時」に猟銃を撃つ権限を持つのか?
市街地で猟銃を使用できるのは、主に以下の二者です。
1. 警察官:
警察官は、警察官職務執行法(警職法)第7条に基づき、人の生命・身体の防護、または公務執行への抵抗を抑止するために「武器の使用」が認められています。
これには拳銃だけでなく、都道府県警察が配備しているライフル銃(猟銃の一種)も含まれます。
熊などの動物が人に危害を及ぼすか、その明白な恐れがある場合、市民や警察官自身を守るために、やむを得ない限度で猟銃を使用することができます。
ただし、全ての警察官が常に猟銃を携帯しているわけではなく、専門の訓練を受けた部隊や担当者が対応にあたります。
2. 猟友会のハンター(鳥獣被害対策実施隊など):
実際に出没現場で対応するケースとして多いのが、地元の猟友会に所属するハンター(狩猟者)です。
多くの場合、ハンターは市町村の「鳥獣被害対策実施隊」の隊員を兼ねています。
彼らは、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づき、市町村長からの「緊急捕獲(緊急駆除)」の要請を受けて出動します。
これは、通常の狩猟期間や狩猟区域とは全く異なる、行政による「有害鳥獣駆除」の一環です。
緊急駆除の法的な枠組みと流れ
緊急時に猟銃が使用されるまでの一般的な流れは以下の通りです。
1. 住民からの通報: 「熊が出た」「人を襲っている」といった110番通報や市町村への連絡が入ります。
2. 警察と行政の連携: 警察官が現場に急行し、住民の避難誘導や安全確保を行います。同時に、市町村役場も状況を把握します。
3. 出動要請: 市町村長が、人命への危険が切迫していると判断した場合、地元の猟友会や鳥獣被害対策実施隊に「緊急駆除」の出動を要請します。
4. 現場での判断: 現場に到着したハンターと警察官が状況を評価します。熊が山に逃げたか、建物に立てこもっているか、人を襲っているかなどを確認します。
5. 発砲の実行: 警察官が周辺住民の安全を確保し、立ち入り規制を行った上で、ハンターが最も安全かつ確実に駆除できるタイミングと場所を判断し、発砲します。市街地での発砲は、跳弾(弾が硬いものに当たって跳ね返る)や流れ弾の危険が常につきまとうため、極めて高度な技術と冷静な判断が求められます。
市街地で発砲する危険性と社会的な課題
緊急時の猟銃使用には、多くの困難が伴います。
- 安全確保の難しさ: 住宅が密集する市街地では、万が一の跳弾や流れ弾のリスクをゼロにすることはできません。ハンターは、背後に安全な「矢止め(弾を受け止める土手や壁)」がない状況で、発砲をためらうケースもあります。
- ハンターの不足と高齢化: そもそも猟銃の所持許可のハードルが非常に高く、若手の担い手が減少しています。有害鳥獣駆除の担い手である猟友会のメンバーは高齢化が進んでおり、危険が伴う緊急時の出動に対応できる人が限られているのが現状です。
- 駆除に対する社会的ジレンマ: 熊を「かわいそう」と感じる市民感情と、「危険だから駆除すべき」という安全確保の要請は、時に社会的な対立を生みます。しかし、一度人を襲った熊や、市街地から追い払っても再び戻ってくる熊は、人命を優先するために駆除せざるを得ないのが現実です。
「緊急猟銃」の参考動画
「緊急猟銃」のまとめ
「緊急猟銃」とは、法律や制度に裏付けられた正式な用語ではありませんが、熊などの危険動物による差し迫った脅威から人の命を守るため、警察官や猟友会のハンターがやむを得ず猟銃を使用する最後の手段を指す言葉と言えます。
その使用は、銃刀法、警職法、鳥獣保護管理法といった厳格な法律の枠組みの中で、行政の要請に基づき、極めて慎重に行われています。
ハンターの高齢化や、野生動物との距離感の変化(アーバンベア問題)など、私たちが直面している課題は複雑です。
なぜ彼らが市街地で危険を冒して猟銃を構えなければならないのか、その背景にある社会的な問題を理解することが重要です。
野生動物との共存を模索しつつも、私たちの安全をどう確保していくか、社会全体で考えていく必要があります。
関連トピック
鳥獣保護管理法: 正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。日本の野生鳥獣の保護と管理、狩猟について定めた法律で、有害鳥獣の駆除許可(緊急捕獲を含む)の根拠もここにあります。
猟友会(大日本猟友会): 全国の狩猟者を会員とする一般社団法人です。単なる趣味の団体ではなく、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣駆除の重要な担い手として、行政と連携しています。
有害鳥獣駆除: 農作物への被害や、人の生命・身体への危害を防ぐために、鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事や市町村長の許可を得て野生鳥獣を捕獲・駆除することです。
アーバンベア(都市型クマ): 従来の生息地である山林から下りてきて、市街地やその周辺を生活圏の一部とし、人間の出すゴミを餌にするなど、都市環境に適応した熊を指す言葉です。
警察官職務執行法(警職法): 警察官が職務を遂行する上で必要な権限(質問、保護、武器の使用など)を定めた法律です。緊急時の武器使用の根拠となります。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法): 武器の所持を原則禁止し、猟銃や空気銃など一部の銃についてのみ、厳格な審査を経た許可制を定めている法律です。
関連資料
環境省「鳥獣保護管理法の概要」: 法律の目的や、捕獲許可の制度について解説されています。
大日本猟友会ウェブサイト: 猟友会の活動内容や、有害鳥獣駆除の現状について情報が掲載されています。
警察庁「銃砲刀剣類所持等取締法」関連資料: 猟銃の所持許可制度の厳格さについて解説されています。
各地方自治体の「クマ出没対応マニュアル」: 住民への注意喚起とともに、緊急時の行政(警察・猟友会)の連携体制について記載されています。