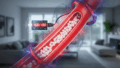認知症とは?種類別の初期症状、予防法、家族の正しい対応まで専門の知見を含めて徹底解説
「認知症」の概要
認知症は、何らかの病気によって脳の細胞が傷ついたり、働きが悪くなったりすることで起こる脳の病気です。
単なる「加齢による物忘れ」とは異なり、記憶障害や判断力の低下、理解力の低下などが起こり、日常生活や社会生活に支障が出る状態を指します。
日本の高齢化に伴い、認知症は非常に身近な病気となっており、誰もが関わる可能性があります。
しかし、認知症は正しく理解し、早期に対応することで、進行を遅らせたり、穏やかな生活を長く続けたりすることが可能です。
この記事では、認知症の基本的な知識から、種類別の症状、今日からできる予防法、そしてご家族や周囲の方の適切な対応方法まで、幅広く解説します。
「認知症」を深く理解する(詳細)
認知症の症状は、大きく「中核症状」と「BPSD(行動・心理症状)」の2つに分けられます。
中核症状とBPSD(行動・心理症状)
中核症状とは、脳の細胞が壊れることによって直接引き起こされる症状です。
これには、新しいことを覚えられない「記憶障害」、時間や場所、人がわからなくなる「見当識障害」、物事を理解し、判断し、実行する能力が低下する「理解・判断力の低下」「実行機能障害」などがあります。
一方、BPSD(行動・心理症状)は、これらの中核症状を背景に、本人の性格、元々の生活環境、人間関係、心理的な要因が複雑に絡み合って現れる症状です。
具体的には、不安、抑うつ、徘徊、物盗られ妄想、暴力・暴言、介護への抵抗などが挙げられます。
BPSDは、周囲の対応や環境の調整によって、症状を軽減させることが可能な場合があります。
認知症の主な種類と特徴
認知症にはいくつかの種類があり、原因となる病気によって症状の現れ方や進行の仕方が異なります。
アルツハイマー型認知症
認知症の中で最も多く、全体の半数以上を占めると言われています。
脳にアミロイドβやタウといった異常なたんぱく質がたまることで、脳の神経細胞が徐々に死んでいき、脳が萎縮します。
初期症状としては、「今さっきの出来事」を忘れてしまう記憶障害が特徴で、同じことを何度も言ったり、尋ねたりすることが増えます。
進行は比較的ゆるやかです。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって、脳の神経細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、その部分の機能が失われることで発症します。
障害を受けた脳の場所によって症状が異なり、症状に波がある「まだら認知症」と呼ばれる状態になることが特徴です。
例えば、記憶力は保たれているのに判断力が低下する、といった状態です。
感情の起伏が激しくなる「感情失禁」(急に泣いたり笑ったりする)が見られることもあります。
レビー小体型認知症
脳の神経細胞内に「レビー小体」という異常なたんぱく質が現れることで発症します。
初期症状として、非常にリアルな「幻視」(実在しない人や動物、虫などが見える)が特徴的です。
また、手足の震え、筋肉のこわばり、小刻み歩行といった「パーキンソン症状」も現れやすいです。
症状が良い時と悪い時の波(日内変動)が大きいのも特徴の一つです。
前頭側頭型認知症
脳の前頭葉(社会性や計画性)と側頭葉(言語や記憶)が萎縮することで発症します。
他の認知症と異なり、初期は記憶障害よりも「人格の変化」や「社会性の欠如」が目立ちます。
例えば、ルールを守れなくなる(万引きや信号無視)、他人に配慮しなくなる、同じ行動を繰り返す(常同行動)といった症状です。
比較的若い世代(40代~60代)で発症することもあります。
認知症の予防と早期発見(MCI)
認知症は、発症する何年も前から脳の中では変化が始まっていると言われています。
認知症の一歩手前の状態は「軽度認知障害(MCI)」と呼ばれます。
MCIは、物忘れはあっても日常生活には支障がない状態ですが、この段階で適切な対策を講じることで、認知症への進行を防いだり、遅らせたりできる可能性があります。
予防には、生活習慣の見直しが非常に重要です。
-
適度な運動: ウォーキングや軽いジョギング、スクワットなどの有酸素運動や筋力トレーニングが推奨されます。1日30分程度、週に3回以上を目安に、楽しみながら続けることが大切です。
-
バランスの取れた食事: 野菜、果物、魚(特に青魚)、大豆製品などをバランス良く摂ることが推奨されます。「まごわやさしい」(豆、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、いも)を意識するのも良いでしょう。
-
知的活動と社会参加: 脳トレも良いですが、それ以上に「楽しく」行うことが脳の活性化に繋がります。新しい趣味を始める、旅行の計画を立てる、友人や家族との会話を楽しむなど、社会的な交流を保つことが予防に効果的です。
-
質の良い睡眠とストレス管理: 睡眠不足やストレスは認知症のリスクを高めます。リラックスできる時間を持ち、十分な睡眠をとることが大切です。
-
生活習慣病の管理: 高血圧、糖尿病、脂質異常症などは血管性認知症のリスクを高めるだけでなく、アルツハイマー型認知症のリスクにもなります。持病の管理をしっかり行いましょう。
-
禁煙: 喫煙は認知症の大きなリスク要因の一つです。
認知症の人への家族・周囲の接し方
認知症の人と接する上で最も大切なのは、本人の尊厳を守り、不安を取り除くことです。
家族や周囲の対応次第で、BPSD(行動・心理症状)は大きく改善する可能性があります。
接し方の基本「3つの“ない”」
1. 驚かせない(Not Surprising): 後ろから急に声をかけるなど、相手を驚かせる行動は避けましょう。
2. 急がせない(Not Rushing): 認知症の人は、物事を理解したり行動したりするのに時間がかかります。本人のペースに合わせ、ゆっくり待ちましょう。
3. 自尊心を傷つけない(Not Demeaning): 失敗を責めたり、子ども扱いしたりする言葉遣いは避けましょう。「忘れた」こと自体を指摘するのではなく、気持ちに寄り添うことが大切です。
具体的な対応のポイント
-
目線を合わせて、前から話しかける: 相手の視野に入り、穏やかな表情で、優しい口調で話しかけます。
-
否定せず、まずは共感する: 「物盗られ妄想」などで「盗られた」と言われても、頭ごなしに否定せず、「それは大変ですね」「一緒に探しましょう」と、まずは本人の不安な気持ちを受け止めましょう。
-
分かりやすく、簡潔に伝える: 一度に多くの情報を伝えると混乱してしまいます。「お風呂に入りましょう」「次に服を着替えましょう」と、一つずつ具体的に伝えます。
-
本人ができることは続けてもらう: 全てを先回りしてやってしまうのではなく、時間がかかっても本人ができることは見守り、役割を持ってもらうことが自信や意欲につながります。
家族だけで抱え込まない
認知症の介護は長期にわたることが多く、家族だけで抱え込むと介護者が疲弊してしまいます。
「最近様子がおかしい」と感じたら、まずはかかりつけ医や、地域の「地域包括支援センター」に相談してください。
介護保険サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護など)を利用することで、本人にとっても社会とのつながりができ、家族の負担も軽減できます。
参考動画(専門医による認知症解説)
まとめ
認知症は、決して特別な病気ではなく、誰もがなりうる、または関わる可能性がある病気です。
最も重要なのは、早期発見と早期対応です。
「年のせい」と見過ごさず、MCI(軽度認知障害)の段階から予防的な生活習慣を心がけることが、発症を遅らせる鍵となります。
もし家族やご自身が認知症と診断されても、絶望する必要はありません。
正しい知識を持ち、本人の尊厳を守る接し方を心がけ、介護保険サービスや専門機関のサポートを上手に利用することで、認知症と共に穏やかに生活を続けることは十分に可能です。
不安や悩みを一人で抱え込まず、まずは身近な相談窓口である「地域包括支援センター」や専門の医療機関に相談することから始めてみてください。
関連トピック
軽度認知障害(MCI): 認知症の前段階とされる状態です。記憶障害などの症状はありますが、日常生活には支障がないレベルです。この段階での気づきと対策が、認知症予防において非常に重要です。
地域包括支援センター: 高齢者の健康、福祉、介護などに関する総合相談窓口です。認知症に関する最初の相談先として、全国の市町村に設置されています。
介護保険制度: 認知症のケアを社会全体で支えるための公的な制度です。デイサービス、ショートステイ、訪問介護、福祉用具のレンタルなど、様々なサービスを利用できます。
BPSD(行動・心理症状): 認知症の中核症状(記憶障害など)に付随して現れる、徘徊、妄想、暴力、不安などの症状です。これらの症状は、環境調整や適切な対応によって改善する可能性があります。
成年後見制度: 認知症などにより判断能力が低下した方の財産管理や、医療・介護の契約などを法的に支援するための制度です。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。