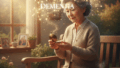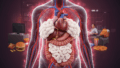高血圧とは?その原因、症状、放置するリスクと今日からできる対策(食事・運動)を徹底解説
「高血圧」の概要
高血圧は、血圧が正常範囲を超えて高い状態が続くことを指します。
日本高血圧学会のガイドラインでは、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上(家庭血圧では135/85mmHg以上)の場合に高血圧と診断されます。
高血圧は自覚症状がほとんどないことが多いため、「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれています。
しかし、放置すると動脈硬化が進行し、脳卒中(脳梗塞や脳出血)、心筋梗塞、狭心症、腎不全といった命に関わる重大な病気を引き起こすリスクが高まります。
日本国内でも非常に患者数が多く、生活習慣病の代表格とされています。
「高血圧」の詳細
高血圧は、その原因によって大きく二つに分類されます。
本態性高血圧(一次性高血圧)
高血圧患者の約90%以上がこのタイプに該当します。
特定の病気が原因ではなく、遺伝的な要因(体質)に加えて、塩分の過剰摂取、肥満、運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒といった複数の生活習慣要因が組み合わさって発症すると考えられています。
これらの要因が血管を収縮させたり、血液量を増やしたりすることで血圧が上昇します。
特に日本人は、食塩感受性が高い(塩分摂取で血圧が上がりやすい)人が多いとされています。
二次性高血圧
腎臓病(腎実質性高血圧、腎血管性高血圧)、内分泌異常(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫など)、睡眠時無呼吸症候群、薬剤の副作用など、特定の原因疾患によって引き起こされる高血圧です。
この場合、原因となっている病気の治療を行うことで、血圧の改善が期待できます。
高血圧の診断と治療
高血圧の診断は、一度の測定で高い数値が出ただけでは行われません。
異なる日時に繰り返し血圧を測定し、常に高い状態が続くことを確認して診断されます。
診察室での血圧測定だけでなく、家庭での血圧測定(家庭血圧)が非常に重要視されています。
これは、病院では緊張して血圧が上がってしまう「白衣高血圧」や、病院では正常でも家庭では高い「仮面高血圧」を見つけるためです。
高血圧の治療は、まず生活習慣の修正から始まります。
これには、減塩(1日6g未満目標)、野菜や果物の積極的な摂取(カリウムによるナトリウム排出促進)、適正体重の維持(肥満の解消)、適度な有酸素運動(ウォーキングなど)、アルコールの節制、禁煙、ストレス管理が含まれます。
食事療法や運動療法だけで血圧が十分に下がらない場合や、すでに合併症のリスクが高い場合には、薬物療法(降圧薬)が併用されます。
降圧薬には、カルシウム拮抗薬、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)、ACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬など、さまざまな種類があります。
患者さんの状態や合併症の有無に合わせて、これらの薬が単独または組み合わせて処方されます。
薬を飲み始めても、生活習慣の改善は継続することが極めて重要です。
「高血圧」のまとめ
高血圧は、現代社会において非常に一般的な疾患でありながら、その危険性はしばしば軽視されがちです。
自覚症状がないままに進行し、ある日突然、深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、「サイレントキラー」の異名を持っています。
しかし、高血圧は早期に発見し、適切に管理すれば、合併症のリスクを大幅に減らすことが可能な病気でもあります。
重要なのは、まず自身の血圧を知ることです。
定期的な健康診断や、家庭での血圧測定を習慣づけることが第一歩となります。
もし高血圧と診断された場合は、医師の指導のもと、生活習慣の改善(特に減塩、運動、体重管理)に真剣に取り組むことが求められます。
降圧薬の服用が必要になった場合も、自己判断で中断せず、継続して治療を受けることが大切です。
自身の健康を守るため、高血圧に対する正しい知識を持ち、日々の生活を見直してみましょう。
「高血圧」の関連トピック
動脈硬化: 高血圧が続くと血管の壁に圧力がかかり続け、血管が硬く、もろくなる状態です。高血圧は動脈硬化の最大の危険因子の一つです。
脳卒中: 脳の血管が詰まる「脳梗塞」や、破れる「脳出血」「くも膜下出血」の総称です。高血圧は脳卒中の最大のリスクとなります。
心筋梗塞: 心臓の筋肉(心筋)に血液を送る冠動脈が動脈硬化などで詰まり、心筋が壊死してしまう病気です。高血圧は心臓に負担をかけ、心筋梗塞のリスクを高めます。
腎不全: 高血圧が長く続くと、血液をろ過する腎臓の細い血管がダメージを受け、腎臓の機能が低下します。進行すると人工透析が必要になる場合もあります。
メタボリックシンドローム: 内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上を合併した状態です。動脈硬化を急速に進行させます。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。