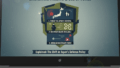SEOは終わるのか? AI時代の新戦略「生成エンジン最適化(GEO)」と従来型SEOの徹底比較
「SEO」と「GEO」の概要
検索エンジン最適化(SEO)は、長らくWebマーケティングの中心的な施策でした。
しかし、ChatGPTやGoogleのSGE(Search Generative Experience)といった生成AIの台頭により、その常識が変わりつつあります。
ここで新たに登場した概念が「GEO(Generative Engine Optimization)」、すなわち「生成エンジン最適化」です。
SEOがGoogleやBingなどの「検索エンジン」を対象に、検索結果の「リンクリスト」で上位表示を目指す施策であるのに対し、GEOはAIチャットボットやAI検索結果の「生成される回答」そのものを対象にします。
GEOの目的は、自社のコンテンツをAIに「信頼できる情報源」として認識させ、AIが生成する回答の中で引用・参照・推薦してもらうことにあります。
SEOが「クリックされる」ことを目指すなら、GEOは「AIに選ばれる・語られる」ことを目指す、新しい時代の最適化戦略と言えます。
「SEO」と「GEO」の詳細な解説
従来のSEO(検索エンジン最適化)の役割
従来のSEOは、検索エンジンのクローラーがWebサイトを正しく理解し、高く評価できるように最適化する技術です。
主な施策は、ユーザーの検索意図に沿ったキーワードを選定し、質の高いコンテンツを作成すること(コンテンツSEO)でした。
また、サイトの表示速度を改善したり、モバイル対応したりする「技術的SEO」や、他の信頼できるサイトからリンクを獲得する「外部施策(被リンク)」も重要視されてきました。
これらの目的は一貫して、検索結果ページ(SERPs)に表示される「10本の青いリンク」の中で、いかにして1位に近づけるか、というものでした。
ユーザーは提示されたリンクをクリックし、サイトを訪れて初めて情報を得ることができます。
新しいGEO(生成エンジン最適化)の概念
一方、GEOは全く異なるアプローチを取ります。
GoogleのSGE(AI Overview)やPerplexityなどのAI検索では、ユーザーが質問をすると、AIが複数のWebサイトの情報を要約・再構成した「直接的な回答」を提示します。
ユーザーは、もはや個別のリンクをクリックしなくても、その場で答えを得られるようになります。
この環境下で重要になるのがGEOです。
GEOは、自社のWebサイトやコンテンツが、AIにとって「最も信頼でき、引用するに値する情報源」であると示すための施策です。
AIが回答を生成する際に、「(あなたのサイト)によると…」と引用されたり、回答の根拠としてリンクが提示されたりすることがGEOの成功となります。
GEOで重要となる具体的な施策
GEOはまだ新しい分野ですが、専門家の間ではいくつかの重要な施策が議論されています。
1. E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の徹底強化
これはSEOでも重要でしたが、GEOではさらに決定的な要素となります。
AIは「ハルシネーション(嘘)」を避けるため、信頼できる情報源を優先します。
「誰が」書いた情報なのかを明確にするため、著者情報、運営者情報、企業の専門性や実績をサイト上で明示することが不可欠です。
2. 構造化データのマークアップ
AIがコンテンツの「意味」を正確に理解できるように、Schema.orgなどの構造化データを用いて情報を整理することが求められます。
例えば、「この記事の著者はこの人物である」「この情報はQ&A形式である」とAIが理解しやすいようにタグ付けすることです。
3. 独自性の高い一次情報の提供
AIは既存の情報を要約するのが得意です。
しかし、AI自身が持っていない独自の調査データ、専門家による深い洞察、具体的な事例や体験談(「経験」)は、AIにとって非常に価値の高い情報源となります。
他サイトの情報をまとめただけの内容は、AIの回答の「素材」にはなっても、「引用元」として選ばれにくくなります。
4. 明確で簡潔なコンテンツ構造
AIは、ユーザーの「問い」に対して「答え」を返すように設計されています。
そのため、FAQ(よくある質問)ページのように、一つの見出し(問い)に対して直接的な回答(答え)を簡潔に記述する形式が、AIに引用されやすいとされています。
SEOとGEOの未来:補完し合う関係へ
では、GEOの登場によってSEOは不要になるのでしょうか。
答えは「いいえ」です。
専門家の多くは、GEOはSEOを「置き換える」ものではなく、「拡張・補完する」ものだと考えています。
GoogleのSGE(AI Overview)を見ても、AIが生成した回答の直下には、従来通りのWebサイトリンク(SEOの結果)が表示されます。
また、AIが回答を生成する際の「情報源」として選ぶサイトは、多くの場合、現在SEOで高く評価されている(=信頼性が高い)サイトです。
つまり、E-E-A-Tの強化や技術的SEOといった「優れたSEOの基盤」があってこそ、初めて「効果的なGEO」が可能になります。
今後は、従来の検索結果での上位表示を目指すSEOと、AIの回答内での引用を目指すGEOの両輪で戦略を立てることが、デジタルマーケティングの新たな標準となるでしょう。
参考動画
まとめ
「生成エンジン最適化(GEO)」は、AIが検索体験の中心になりつつある現代において、避けては通れない新しいマーケティング戦略です。
従来のSEOが「検索順位」という席取りゲームだったとすれば、GEOは「AIの教科書に載る」ための権威性や信頼性を高める活動と言えます。
幸いなことに、GEOで求められることの多くは、E-E-A-Tの強化や独自コンテンツの作成など、これまでGoogleがSEOで推奨してきた「ユーザー第一主義」の延長線上にあります。
SEOがなくなるわけではありません。
むしろ、検索エンジンと生成AIの両方から「信頼できる情報源」として選ばれるために、コンテンツの「質」と「信頼性」がこれまで以上に問われる時代が来たと捉えるべきです。
読者の皆様も、まずはご自身のWebサイトが「誰によって」「どのような専門性を持って」運営されているかを明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。
関連トピック
SGE (Search Generative Experience): Googleが導入を進める、検索結果の上部にAIによる要約回答を表示する新しい検索体験です。AI Overview(AIによる概要)とも呼ばれ、GEOの主要な対象領域とされています。
E-E-A-T: 「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の略です。Googleがコンテンツの品質を評価する上で最も重視する基準であり、AIが情報源を選ぶ際の基準としても最重要視されています。
構造化データ (Schema.org): Webページの内容(例:これはレシピです、これは人物評です、これはFAQです)を検索エンジンやAIが理解できる共通の形式(語彙)で記述するためのマークアップ方法です。GEOにおいてAIの理解を助けるために不可欠とされます。
関連資料
Google検索セントラル: Googleが公式に発表するSEOやE-E-A-T、SGEに関する最新情報やガイドラインが掲載されています。GEO対策の基礎となる情報源です。
Schema.org: 構造化データのリファレンスサイトです。どのような情報をどのようにマークアップすればよいか、全ての仕様が公開されています。
Generative engine optimization (Wikipedia): 2023年11月に学術論文で初めて提唱された「GEO」という用語の定義や背景について解説されています。この概念の原点を知ることができます。
GEO対策の7つのコツを学ぶ この動画は、Generative Engine Optimization(GEO)で成果を出すための具体的な7つのコツを対談形式で解説しており、SGE対策や構造化データなど、本文書で触れた実践的な内容を深掘りするのに役立ちます。