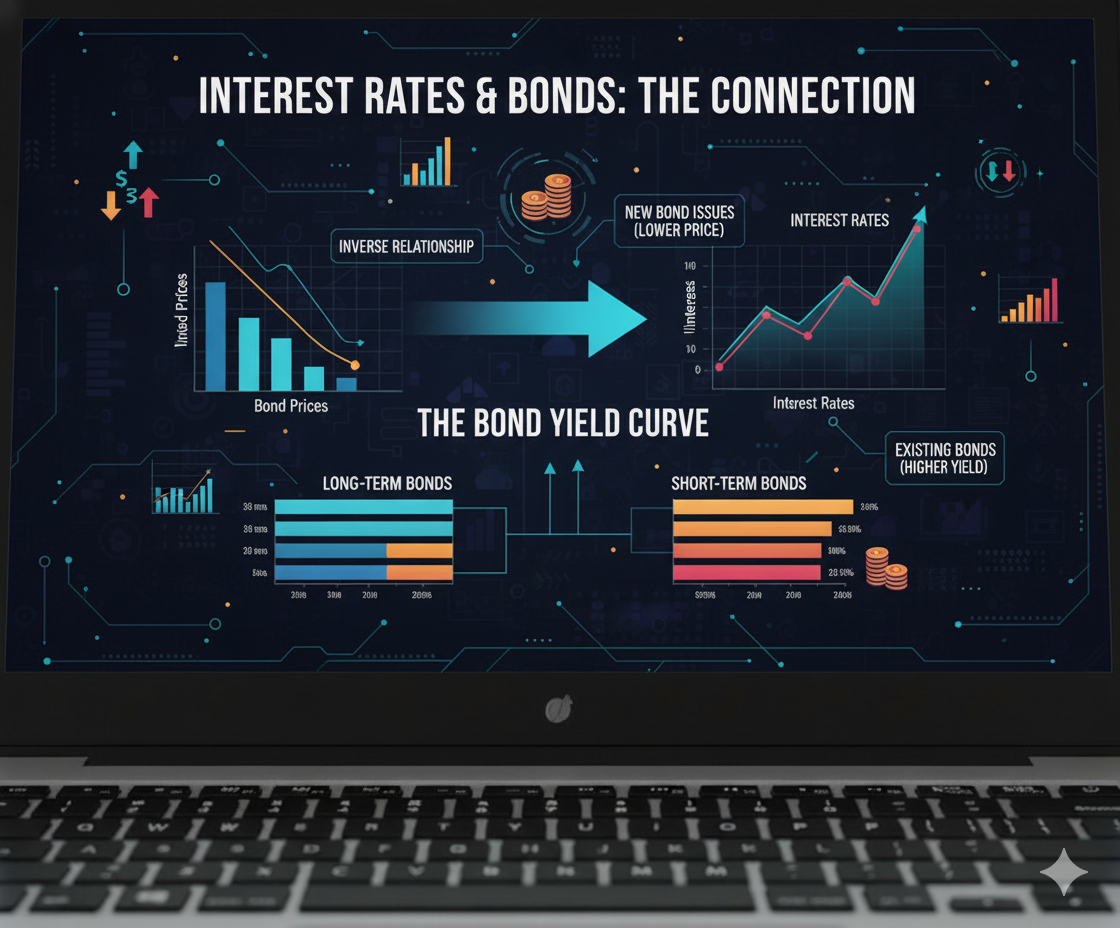年賀状のすべて:2026年(令和8年)版の書き方からマナー、歴史まで徹底解説
概要:新年の心を伝える日本の伝統
新しい年の幕開けに、大切な人へ送る「年賀状」。
年賀状は、旧年中にお世話になったことへの感謝と、新しい年も変わらぬお付き合いをお願いする気持ち、そして相手の健康や幸福を祈る心を伝える、日本独自の美しい文化です。
近年ではSNSやメールでの挨拶も増えていますが、手元に届く一枚のはがきには、デジタルにはない特別な温かみがあります。
この記事では、年賀状の概要や歴史、2026年(令和8年・午年)版の年賀状作成に役立つ基本的な書き方、知っておきたいマナー、そして最近の「年賀状じまい」の動向まで、年賀状に関する情報を網羅して解説します。
詳細:年賀状の知識とマナー
年賀状の概要と歴史
年賀状のルーツは、平安時代にまで遡ると言われています。
当時は、貴族たちが新年に集まって祝宴を開き、遠方で参加できない人々が年始の挨拶を文書で送ったのが始まりとされています。
藤原明衡がまとめた手紙の文例集『雲州消息』には、すでに年始の挨拶の文例が残されています。
江戸時代に入ると、飛脚制度が発達したことにより、庶民の間でも新年の挨拶状を交換する習慣が広まりました。
現在の「はがき」の形で年賀状が普及したのは、明治時代に郵便制度が確立されてからです。
1873年(明治6年)に官製はがきが発行され、年末に郵便局に預けると元日に配達される「年賀郵便特別取扱」が1899年(明治32年)に始まりました。
そして、年賀状の最大の楽しみの一つである「お年玉付郵便はがき」は、1949年(昭和24年)に初めて発行され、国民的な習慣として爆発的に普及しました。
年賀状の基本的な書き方
年賀状は、主に「表面(宛名)」と「裏面(賀詞・本文)」で構成されています。
表面(宛名)の書き方
宛名は、相手に失礼がないよう、正しく丁寧に書くことが最も重要です。
住所は都道府県から正確に記載し、ビル名やマンション名、部屋番号も省略せずに書きましょう。
宛名は、住所よりも少し大きめの文字で、中央に配置します。
敬称は「様」が基本ですが、会社や部署宛ての場合は「御中」を使います。
家族全員に宛てる場合は、それぞれの氏名に「様」をつけるのが丁寧ですが、世帯主の氏名に「様」をつけ、左側に「御家族様」と添える方法もあります。
裏面(本文)の書き方
裏面は、主に「賀詞(がし)」「本文(感謝と祈り)」「日付」「一言」で構成されます。
1. 賀詞(がし)
新年のお祝いの言葉です。
「あけましておめでとうございます」や「謹賀新年」など、様々な種類がありますが、送る相手によって使い分けるマナーがあります(詳細は後述)。
2. 本文
賀詞に続けて、旧年中の感謝や近況報告、新年のお付き合いをお願いする言葉、相手の健康や幸福を祈る言葉を書きます。
3. 日付
「令和八年 元旦」または「二〇二六年 元旦」と書くのが一般的です。
「元旦」とは1月1日の朝を意味するため、もし1月1日に届かない可能性がある場合(松の内に出す場合)は、「令和八年 一月」などとします。
4. 一言(添え書き)
印刷された年賀状でも、最後に手書きで一言添えるだけで、温かみが格段に増します。
「お体を大切にお過ごしください」「ご家族皆様でのご来訪をお待ちしております」など、相手を思いやった個別のメッセージが喜ばれます。
知っておきたい年賀状のマナー
年賀状には、相手に失礼のないよう、古くから伝わるいくつかのマナー(決まりごと)があります。
いつまでに出すか
元日に確実に届けるためには、郵便局が推奨する期間、例年「12月15日から12月25日まで」に投函するのがベストです。
もし年賀状の準備が遅れて年が明けてしまった場合、「松の内」と呼ばれる期間内であれば年賀状として送っても失礼にはあたりません。
「松の内」は地域によって異なりますが、一般的に関東では1月7日まで、関西では1月15日までとされています。
賀詞の使い分け
賀詞は、送る相手との関係性によって正しく使い分ける必要があります。
目上の方(上司、恩師、先輩)に使う賀詞:
「謹賀新年」「恭賀新年」といった4文字の賀詞や、「謹んで新春のお慶びを申し上げます」といった文章体のものが丁寧です。
「謹」や「恭」には、「つつしんで」という敬意が込められています。
友人、同僚、目下の方に使う賀詞:
「賀正(正月を祝う)」「迎春(新年を迎える)」といった2文字の賀詞や、「寿」「福」といった1文字の賀詞が使えます。
これらは敬意表現が簡略化されているため、目上の方に使うのは失礼にあたるとされています。
「あけましておめでとうございます」は、相手を問わず使える万能な賀詞です。
句読点は使わない
年賀状の本文では、「、」(読点)や「。」(句点)を使わないのが伝統的なマナーです。
これには二つの理由があるとされています。
一つは、句読点が文章の「区切り」や「終わり」を意味するため、「おめでたい関係が区切れないように、終わらないように」という縁起を担ぐ意味です。
もう一つは、古来、毛筆で文章を書く文化では句読点が存在せず、句読点は「相手が文章を読みやすくするための補助」という認識があったため、相手への敬意として使わない、という説です。
喪中の場合は
自分、または相手方が喪中(一般的に近親者が亡くなってから一年間)の場合、年賀状のやり取りは控えます。
自分が喪中の場合は、年賀状の受付が始まる前(12月上旬頃)までに「喪中はがき(年賀欠礼状)」を送り、新年の挨拶を失礼する旨を伝えます。
もし喪中の方から年賀状が届いた場合や、喪中と知らずに年賀状を出してしまった場合は、松の内が明けた後(1月8日以降)に「寒中見舞い」として返信するのがマナーです。
最近の年賀状事情:「年賀状じまい」
近年、SNSの普及や高齢化、人間関係の変化に伴い、「年賀状じまい」を選択する人が増えています。
「年賀状じまい」とは、今年送る年賀状を最後に、翌年以降の年賀状による挨拶をご遠慮する旨を伝えることです。
突然送るのをやめてしまうと、相手に「何かあったのでは」と心配をかけてしまう可能性があるため、最後の年賀状でその旨を丁寧に伝えます。
「誠に勝手ながら、本年をもちまして年賀状でのご挨拶を最後とさせていただきたく存じます」といった一文に、これまでの感謝の言葉と、今後も変わらぬお付き合いをお願いする言葉を添えるのが一般的です。
参考動画:年賀状の書き方(手書きの温かさ)
まとめ:年に一度、心を結ぶ便り
年賀状は、一年に一度、日本の多くの人々が「手紙」という文化に触れる貴重な機会です。
一枚一枚に込められた思いや、ポストを開ける瞬間のときめきは、デジタル通信が主流となった現代だからこそ、より一層価値のあるものになっています。
確かに、年賀状の準備は手間がかかる作業かもしれません。
しかし、その手間こそが、相手への「心遣い」の表れでもあります。
2026年の新年に、あなたは誰に、どのような思いを伝えますか。
年賀状を出す人も、年賀状じまいを考える人も、この文化が持つ「人と人との絆を大切にする心」を見つめ直す良い機会かもしれません。
関連トピック
寒中見舞い
松の内(1月7日または15日)が明けてから、立春(2月4日頃)までに出す季節の挨拶状です。
年賀状の返礼が遅れた場合や、喪中の方への挨拶、喪中に年賀状を受け取った際の返礼として使われます。
お年玉付郵便はがき
1949年(昭和24年)に登場した、くじ付きの年賀はがきです。
新年の運試しとして、当選番号の発表は多くの人にとっての楽しみの一つとなっています。
年賀状じまい
高齢や終活、ライフスタイルの変化などを理由に、年賀状のやり取りをやめることを宣言する挨拶状です。
失礼にならないよう、感謝の言葉と共に最後の年賀状で伝えるのが一般的です。
暑中見舞い・残暑見舞い
夏の暑い時期に、相手の健康を気遣って送る挨拶状です。
年賀状と並ぶ、日本の伝統的な季節の便りです。
関連資料
年賀状作成ソフト(『筆まめ』『筆王』など)
住所録の管理から、裏面のデザイン作成、印刷までを一貫して行えるソフトウェアです。
パソコンで年賀状を作成する際の定番ツールです。
年賀状素材集(書籍・Webサイト)
2026年の干支である「午(うま)」のイラストや、デザインテンプレート、賀詞のフォントなどが多数収録されています。
オリジナルの年賀状を作る際に便利です。
家庭用インクジェットプリンター
自宅で手軽に年賀状を印刷できる機器です。
近年は高画質な写真印刷にも対応しており、家族写真入りの年賀状作成などに活躍します。