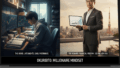スマホ新法(スマホソフトウェア競争促進法)とは? 2025年12月施行でiPhoneやAndroidはどう変わる?メリット・デメリットを徹底解説
「スマホ新法」の概要
スマホ新法とは、通称「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」のことです。
2024年6月に成立し、2025年12月18日に全面施行が予定されている日本の新しい法律です。
この法律の主な目的は、AppleやGoogleといった特定の巨大IT企業(プラットフォーマー)が独占しているスマートフォンのOSやアプリストア市場に競争を促すことです。
これまで私たちは、iPhoneならApp Store、AndroidならGoogle Playストアからしかアプリをダウンロードできませんでした。
また、アプリ内での課金も、AppleやGoogleが提供する決済システムを利用する必要があり、高額な手数料が問題視されていました。
スマホ新法は、こうした状況を改善し、アプリストアや決済方法、さらにはブラウザや検索エンジンなどを、利用者がもっと自由に選べるようにすることを目指しています。
これにより、アプリの価格が下がるなどのメリットが期待される一方で、セキュリティリスクが高まるのではないかという懸念も指摘されています。
「スマホ新法」の詳細
スマホ新法が制定された背景
なぜ今、このような法律が必要とされたのでしょうか。
その背景には、AppleとGoogleの2社による「寡占(かせん)状態」があります。
スマートフォンのOS(オペレーティングシステム)は、Appleの「iOS」とGoogleの「Android」が市場のほとんどを占めています。
これにより、アプリを配布する「アプリストア」や、アプリ内でサービスを購入する「決済システム」も、両社が提供するものにほぼ限定されていました。
アプリ開発者は、売上の最大30%とも言われる高額な手数料(通称:Apple税、Google税)をプラットフォーマーに支払わなければならず、そのコストが最終的に利用者の支払う価格に転嫁されていると指摘されてきました。
また、新規参入企業が独自のアプリストアや決済サービスを提供しようとしても、事実上ブロックされてしまうため、公正な競争が妨げられていると考えられたのです。
このような市場の独占的な状況を是正し、イノベーションを促進するために、スマホ新法が制定されました。
スマホ新法で変わること:主な規制内容
スマホ新法では、規制対象となる巨大IT企業を「指定事業者」として指定します。
指定事業者は、以下の4つの分野(特定ソフトウェア)において、特定の行為が禁止されます。
1. アプリストアの開放(サードパーティストアの許可)
指定事業者は、自社以外の第三者が運営するアプリストア(サードパーティストア)の提供や利用を妨害してはなりません。
これにより、例えばiPhoneユーザーもApp Store以外のアプリストアからアプリをダウンロードできるようになる可能性があります。
2. 決済システムの自由化(外部決済の許可)
アプリ内課金において、指定事業者は自社が提供する決済システム以外の、第三者の決済システム(外部決済)の利用を不当に制限してはなりません。
開発者は、より手数料の安い決済手段をユーザーに提供できるようになります。
3. ブラウザや検索エンジンの選択の自由
スマートフォン利用者が、デフォルトで使用するブラウザ(SafariやChromeなど)や検索エンジン(Google検索やYahoo!検索など)を、簡単に、かつ自由に選択できるような画面を表示することが義務付けられます。
4. 不当な優遇の禁止
指定事業者が、自社のサービスやアプリを、競合他社のものよりも不当に優遇すること(例:検索結果で自社サービスを上位に表示する)を禁止します。
利用者(ユーザー)にとってのメリット
この法律が施行されると、私たち利用者にはどのような良いことがあるのでしょうか。
-
アプリやコンテンツの価格が下がる可能性
開発者が支払う手数料が安くなれば、その分アプリの購入価格やサブスクリプション料金、ゲーム内アイテムの価格などが引き下げられる可能性があります。
-
サービスの選択肢が増える
多様なアプリストアが登場することで、これまで公式ストアでは配信されていなかったような、個性的で新しいアプリに出会えるかもしれません。
また、決済方法も多様化し、自分が使いやすいサービスを選べるようになります。
-
イノベーションの促進
新規参入が容易になることで、企業間の競争が活発になり、より高品質で革新的なサービスが生まれる土壌が育まれます。
利用者(ユーザー)が注意すべきデメリットとリスク
一方で、自由には責任が伴います。
スマホ新法の施行には、大きな懸念点も存在します。
-
セキュリティリスクの増大
最大の懸念は、セキュリティの低下です。
AppleやGoogleの公式ストアは、配信されるアプリがマルウェア(ウイルス)や詐欺アプリでないか、厳格な審査を行っています。
しかし、新しく登場するサードパーティストアが、同様のレベルで安全性を審査するとは限りません。
審査の甘いストアから、個人情報を盗み出したり、スマートフォンを乗っ取ったりする悪意のあるアプリ(野良アプリ)をダウンロードしてしまう危険性が高まります。
-
プライバシー保護の懸念
公式ストアでは、アプリが不必要にユーザーの個人情報(位置情報、連絡先、マイクへのアクセスなど)を収集しないよう厳しくチェックされています。
サードパーティストアのアプリでは、この監視が緩くなり、意図せずプライバシーが侵害されるリスクがあります。
-
青少年保護の問題
公式ストアでは、年齢制限やフィルタリング機能により、子どもたちが不適切なコンテンツ(暴力的な表現やポルノなど)に触れないよう保護されています。
規制の緩いストアが登場することで、こうした保護機能がうまく働かなくなる可能性が指摘されています。
-
ユーザーの自己責任が重くなる
これまでは「公式ストアだから安全」という前提がありましたが、今後は「どのストアからダウンロードするか」「どの決済方法を選ぶか」を、ユーザー自身がその安全性や信頼性を判断して決める必要が出てきます。
参考動画
まとめ
スマホ新法は、スマートフォンの利用体験を大きく変える可能性を秘めた重要な法律です。
巨大IT企業による市場の寡占を解消し、公正な競争を促すことで、私たちはより安価で多様なサービスを享受できるという大きなメリットを期待できます。
しかし、その一方で、これまでプラットフォーマーが「壁」となって守ってきたセキュリティやプライバシーの安全性が、一部崩れるリスクも抱えています。
施行後は、アプリの価格や種類といった「利便性」だけに着目するのではなく、そのアプリやアプリストアの「信頼性」を自分自身で見極める姿勢が不可欠になります。
例えば、提供元が不明な怪しいアプリストアは利用しない、アプリに不必要な権限(パーミッション)を許可しない、OSやアプリを常に最新の状態に保つといった、基本的なセキュリティ対策の重要性がこれまで以上に高まります。
この法律は、私たち利用者に「選ぶ自由」を与えると同時に、「自らを守る責任」を問いかけるものと言えるでしょう。
関連トピック
デジタル市場法 (DMA): EU(欧州連合)で先行して施行された、巨大IT企業(ゲートキーパー)を規制する法律です。スマホ新法も、このDMAの考え方に強く影響を受けています。
独占禁止法: 公正で自由な競争を促進するための基本的な法律です。スマホ新法は、デジタル市場の急速な変化に対応するため、独占禁止法を補完する特別な法律として位置づけられています。
サイドローディング: 公式アプリストアを経由せずに、Webサイトなどから直接アプリをダウンロードしてインストールする行為を指します。スマホ新法はサードパーティ「ストア」を認めるもので、厳密にはサイドローディングとは異なりますが、公式以外からアプリを導入するという点で関連性の高い概念です。
App Store手数料 (Apple税・Google税): プラットフォーマーがアプリ開発者に課す高額な手数料の通称です。この手数料問題が、スマホ新法制定の大きなきっかけの一つとなりました。
関連資料
公正取引委員会(JFTC)の公式資料: 法律の条文や、具体的な運用方針を示すガイドラインなどを公開している一次情報源です。YouTubeチャンネルでは解説動画も公開されています。
政府広報オンライン: スマホ新法の目的や内容について、国民向けに分かりやすく解説した記事や資料が掲載されています。
国民生活センターの発表資料: 消費者としてどのような点に注意すべきか、具体的なアドバイスや注意喚起を行っています。
各セキュリティ企業のレポート: スマホ新法の施行に伴う新たなセキュリティ脅威や、具体的な対策方法について分析したレポートやブログ記事も参考になります。