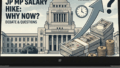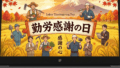【2025年版】二十四節気「小雪(しょうせつ)」とは?意味や旬の食べ物、冬支度のポイントを徹底解説
「小雪」の概要
2025年11月22日は、二十四節気の一つ「小雪(しょうせつ)」にあたります。
暦の上では冬の入り口である「立冬」を過ぎ、いよいよ本格的な寒さが訪れる少し手前の時期を指します。
「小雪」という文字が表す通り、北国や山間部では雪がちらつき始めるものの、積もるほどではないという季節感を表しています。
本記事では、小雪の意味や由来、この時期に見られる自然の変化(七十二候)、そして美味しく健康に過ごすための旬の食材や生活の知恵について詳しく解説します。
詳細:小雪の意味と過ごし方
小雪(しょうせつ)の意味と2025年の日程
小雪は、二十四節気(にじゅうしせっき)の第20番目の節気です。毎年11月22日頃から、次の節気である「大雪(たいせつ)」までの約15日間を指します。
2025年の小雪は、11月22日(土)です。
「小雪」とは、わずかな雪が降る頃という意味ですが、多くの地域ではまだ紅葉が散り始め、木枯らしが吹き、冬の到来を肌で感じ始める時期です。
日中は「小春日和(こはるびより)」と呼ばれる穏やかな暖かさを感じることもありますが、陽が落ちると急激に冷え込むため、体調管理が重要になります。
小雪の時期の自然変化(七十二候)
二十四節気をさらに細かく5日ごとに分けた「七十二候(しちじゅうにこう)」を見ると、この時期の移ろいがよく分かります。
- 初候:虹蔵不見(にじかくれてみえず)
11月22日頃。日差しが弱まり、空気が乾燥してくるため、雨上がりに虹がかかることが少なくなります。「虹が隠れて見えなくなる」という表現に、冬の訪れを感じさせます。
- 次候:朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)
11月27日頃。「朔風(さくふう)」とは北風のことです。冷たい北風が木々の葉を吹き飛ばし、地面が落ち葉で埋め尽くされる頃です。
- 末候:橘始黄(たちばなはじめてきばむ)
12月2日頃。日本古来の柑橘である「橘(たちばな)」の実が黄色く色づき始める頃です。常緑樹である橘は「永遠」の象徴ともされ、お正月の飾りなどにも使われます。
小雪に味わいたい「旬の食べ物」
寒さが増すと野菜や魚介類は身を守るために糖分や脂肪を蓄え、味が濃厚になります。
- 白菜・ほうれん草・春菊
冬野菜の代表格。霜にあたると甘みが増し、繊維が柔らかくなります。特にほうれん草はビタミンCが豊富で、風邪予防に最適です。
- みかん
こたつでみかん、はこの時期の風物詩です。ビタミンCが豊富で、白い筋には血流を良くする成分も含まれています。
- 牡蠣(カキ)
「海のミルク」と呼ばれる牡蠣は、冬に向けて身が太り、栄養価が高まります。鍋料理やフライで楽しみたい食材です。
- ズワイガニ
北陸地方などでは漁が解禁され、食卓が華やぎます。
この時期の過ごし方と風習
●お歳暮の準備
小雪に入ると、年末の挨拶である「お歳暮」の準備を始めるのに適した時期とされます。お世話になった方への感謝を込めて品物を選び始めましょう。
●勤労感謝の日(11月23日)
小雪の期間中には国民の祝日「勤労感謝の日」があります。元々は「新嘗祭(にいなめさい)」という、その年の収穫を神様に感謝する宮中儀式が由来です。旬の食材をいただきながら、自然の恵みと労働に感謝する日にしましょう。
●乾燥対策と冷え対策
空気が乾燥し、ウイルスが飛散しやすくなる時期です。加湿器の準備や、生姜やネギなど体を温める食材を積極的に摂り、「温活」を始めるのがおすすめです。
参考動画
まとめ
「小雪」は、秋の彩りが終わりを告げ、冬の静けさがやってくる準備期間です。
本格的な厳寒期「大雪」を迎える前に、暖房器具の点検や冬用の衣類への完全な衣替え、そしてお歳暮の手配など、冬支度を整える大切なタイミングでもあります。
急な寒暖差で体調を崩しやすい時期ですが、脂の乗った旬の魚や甘味の増した冬野菜をたっぷり食べて免疫力を高め、来るべき冬本番に備えましょう。
関連トピック
立冬(りっとう):小雪の一つ前の節気。暦の上での冬の始まり。
大雪(たいせつ):小雪の次の節気。本格的に雪が降り積もり始める頃。
冬至(とうじ):一年で最も昼が短くなる日。カボチャを食べ柚子湯に入る風習がある。
新嘗祭(にいなめさい):現在の勤労感謝の日。五穀豊穣を祝う重要な宮中祭祀。
関連資料
『日本の365日を愛おしむ―季節を感じる暮らしの暦』:二十四節気や七十二候を日々の暮らしに取り入れるためのガイドブック。
『旬の野菜カレンダー』:その時期に一番おいしい野菜の選び方やレシピが掲載された実用書。