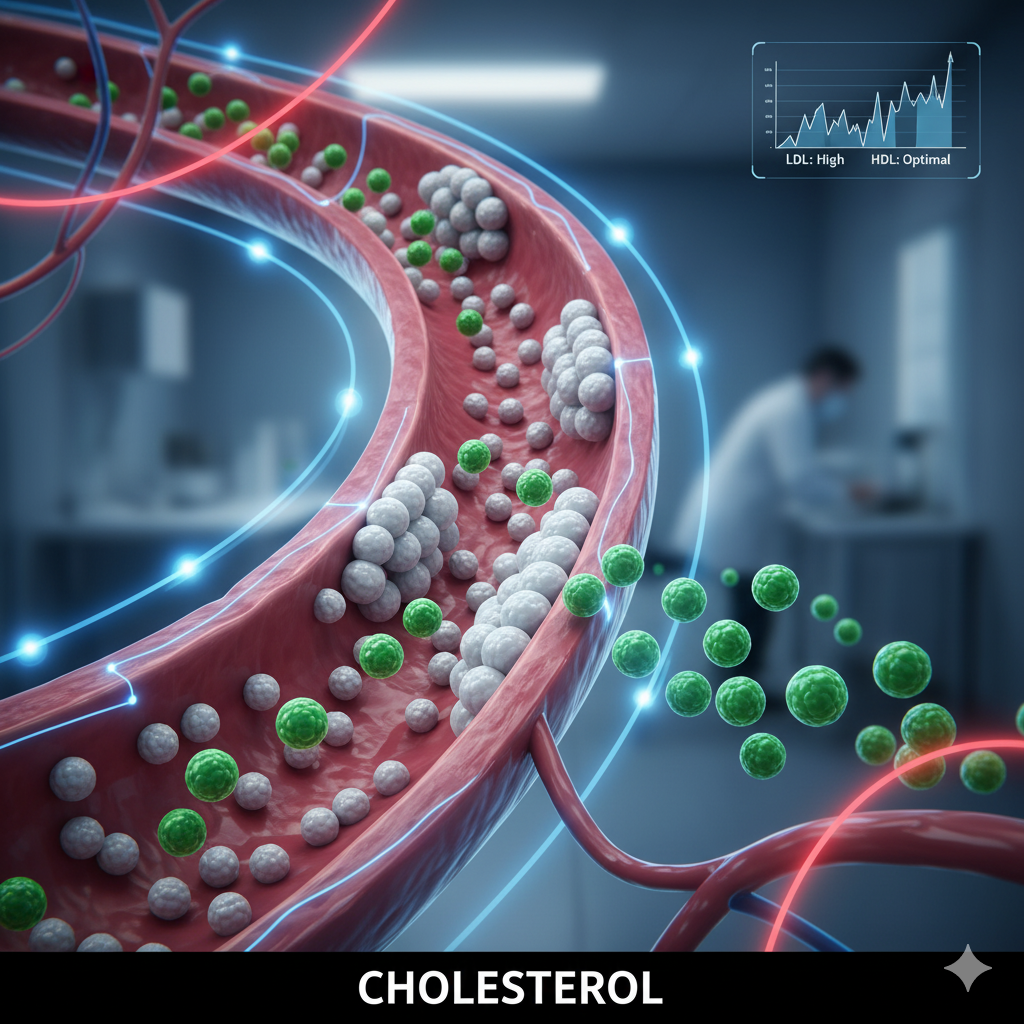コレステロールとは?善玉(HDL)と悪玉(LDL)の違い、基準値、効果的な下げ方を徹底解説
コレステロールの概要
コレステロールは、私たちの体に存在する脂質の一種です。
一般的に「コレステロール=不健康」というイメージを持たれがちですが、実際には私たちの生命維持に不可欠な物質です。
コレステロールは、全身の細胞膜の材料となるほか、性ホルモンや副腎皮質ホルモン、さらには消化吸収を助ける胆汁酸の原料としても使用されます。
体内で必要とされるコレステロールの約7割から8割は肝臓などで作られており、残りの2割から3割が食事から摂取されています。
問題となるのは、このコレステロールが血液中で過剰になったり、バランスが崩れたりすることです。
特に健康診断などで指摘される「コレステロール値」は、私たちの健康状態を知る重要なバロメーターとなります。
この記事では、コレステロールの基本的な役割から、健康に影響を与える「善玉」と「悪玉」の違い、基準値、そして気になる数値を改善するための具体的な方法について詳しく解説していきます。
コレステロールの詳細:善玉・悪玉の違いと改善法
コレステロールについて深く理解するためには、まず「善玉」と「悪玉」と呼ばれる2つの種類について知る必要があります。
コレステロールは脂質であり水に溶けないため、血液中を移動するために「リポタンパク質」というカプセルのような粒子に乗って運ばれます。
このリポタンパク質の種類によって、コレステロールの呼び名が変わります。
LDL(悪玉)コレステロールとは
LDLコレステロールは、低密度リポタンパク質(Low Density Lipoprotein)の略です。
その主な役割は、肝臓で作られたコレステロールを、細胞膜やホルモンの材料として全身の組織や細胞に運ぶことです。
いわば「コレステロールを配達するトラック」のような存在です。
しかし、LDLコレステロールが血液中で増えすぎると、運ばれるコレステロールも過剰になります。
行き場を失ったコレステロールは、血管の壁の内部に入り込んで蓄積していきます。
これが「プラーク(粥腫)」と呼ばれるコブのようなものを作り出し、血管を硬く、狭くする「動脈硬化」の原因となります。
動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる重大な病気を引き起こすリスクが高まるため、LDLコレステロールは「悪玉」と呼ばれています。
HDL(善玉)コレステロールとは
HDLコレステロールは、高密度リポタンパク質(High Density Lipoprotein)の略です。
LDLとは逆に、全身の組織で余ったり、血管の壁に溜まったりした余分なコレステロールを回収し、肝臓に戻す役割を担っています。
こちらは「コレステロールを回収するトラック」に例えられます。
HDLコレステロールは、動脈硬化を抑制し、血管を健康に保つ働きがあるため「善玉」と呼ばれています。
したがって、HDLコレステロールは基準値よりも低い「低HDLコレステロール血症」が問題とされます。
脂質異常症の診断基準
健康診断では、血液中の脂質の値をチェックします。
以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、現在はコレステロールのバランスの異常を重視し「脂質異常症」と呼ばれています。
日本動脈硬化学会が定める主な診断基準(空腹時採血)は以下の通りです。
-
高LDLコレステロール血症: LDLコレステロール値が 140mg/dL 以上
-
境界域高LDLコレステロール血症: LDLコレステロール値が 120〜139mg/dL
-
低HDLコレステロール血症: HDLコレステロール値が 40mg/dL 未満
-
高トリグリセライド(中性脂肪)血症: 中性脂肪(TG)値が 150mg/dL 以上
これらのいずれかに当てはまると、脂質異常症と診断されます。
特にLDLコレステロール値が高い状態が続くと、自覚症状がないまま動脈硬化が進行してしまうため、注意が必要です。
コレステロール値を改善する生活習慣
コレステロール値の異常は、多くの場合、生活習慣の乱れが原因となっています。
特に「食事」と「運動」の2つを見直すことが非常に重要です。
1. 食事療法のポイント
食事で目指すのは、LDL(悪玉)コレステロールを増やさず、HDL(善玉)コレステロールを増やすことです。
-
控えるべき脂質(飽和脂肪酸・トランス脂肪酸)
LDLコレステロールを増やす最大の要因の一つが「飽和脂肪酸」の摂りすぎです。これは、肉の脂身(バラ肉、ひき肉など)、バター、ラード、生クリームなどの動物性脂肪に多く含まれます。
また、マーガリンやショートニング、それらを使用した揚げ物、ファストフード、スナック菓子などに含まれる「トランス脂肪酸」もLDLを増やし、HDLを減らすため避けるべきです。
-
コレステロールを多く含む食品
卵(特に卵黄)、レバー、魚卵(たらこ、いくらなど)はコレステロール自体を多く含みます。以前は厳しく制限されていましたが、食事からの影響は体内で作られる量より少ないことが分かってきました。
とはいえ、摂りすぎは良くないため、バランスを考えることが大切です。
-
積極的に摂りたい栄養素
不飽和脂肪酸: LDLコレステロールを下げる働きが期待できます。特に、サバ、イワシ、サンマなどの青魚に豊富な「オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)」や、オリーブオイル、ナッツ類に多い「オメガ9脂肪酸(オレイン酸)」を意識して摂りましょう。
食物繊維: 野菜、海藻、きのこ類、大豆製品、オートミールなどに豊富に含まれる水溶性食物繊維は、腸内でコレステロールの吸収を妨げ、体外への排出を促す働きがあります。
大豆製品: 豆腐、納豆、豆乳などに含まれる植物性タンパク質(大豆イソフラボン)には、コレステロールの合成を抑える効果が期待されています。
2. 運動療法のポイント
運動は、脂質代謝を改善し、特にHDL(善玉)コレステロールを増やし、中性脂肪を減らす効果があります。
推奨されるのは、体内に酸素を取り込みながら行う「有酸素運動」です。
-
運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳、踏み台昇降などが効果的です。
-
運動の強度と時間: 「ややきつい」と感じる程度(中強度)の運動が理想です。
時間は、1回30分以上を目標に、まとめて時間が取れなければ1回10分を3回など、合計で調整しても構いません。
-
運動の頻度: できるだけ毎日、少なくとも週に3回以上は継続することが重要です。
運動習慣がない人は、まずは「今より10分多く歩く」ことから始めるだけでも効果があります。
生活習慣の改善は、コレステロール値だけでなく、高血圧や糖尿病などの予防・改善にもつながります。
無理のない範囲で、できることから継続していくことが成功の鍵となります。
参考動画
まとめ
コレステロールは、私たちの体にとって必要不可欠な成分ですが、そのバランスが崩れると深刻な健康問題を引き起こす「諸刃の剣」でもあります。
特にLDL(悪玉)コレステロールの増加は、自覚症状がないまま静かに動脈硬化を進行させ、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞といった形で私たちの生活を脅かします。
現代社会では、食生活の欧米化や運動不足により、多くの人がコレステロールの問題を抱えやすい環境にあります。
健康診断でコレステロール値の異常を指摘された場合はもちろん、今は問題がないという方も、他人事とは思わずにご自身の生活習慣を見直すきっかけにしてください。
まずは日々の食事で、肉の脂身を減らして青魚や大豆製品を増やすこと、エレベーターを階段に変えることなど、小さな一歩から始めてみませんか。
自分の体を守るためには、コレステロールに関する正しい知識を持ち、日々の生活の中で賢くコントロールしていくことが何よりも大切です。
関連トピック
脂質異常症
血液中の脂質、すなわちLDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)の値が、基準値から外れた状態を指す病気です。
自覚症状がほとんどないため、健康診断での血液検査が早期発見の鍵となります。
動脈硬化
LDLコレステロールなどが血管の壁に蓄積することで、血管が弾力性を失い、硬く、狭くなる状態です。
高血圧や糖尿病、喫煙なども動脈硬化を促進する要因となります。
進行すると血流が悪くなり、心臓や脳に重大なダメージを与える可能性があります。
中性脂肪(トリグリセライド)
コレステロールと同じく血液中の脂質の一つで、主に体を動かすエネルギー源として貯蔵されます。
しかし、中性脂肪が増えすぎると、HDL(善玉)コレステロールを減らし、LDLコレステロールをより小さく(超悪玉化)させて動脈硬化を促進させることが分かっています。
アルコールの飲み過ぎや糖質の摂りすぎで増加しやすい特徴があります。
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸
食事から摂取する脂質(脂肪酸)の種類です。
飽和脂肪酸は主に動物性脂肪(肉の脂身、バターなど)に多く、摂りすぎるとLDLコレステロールを増加させます。
不飽和脂肪酸は主に植物油(オリーブオイルなど)や魚の油に多く、LDLコレステロールを下げるなど、健康維持に役立つとされています。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。