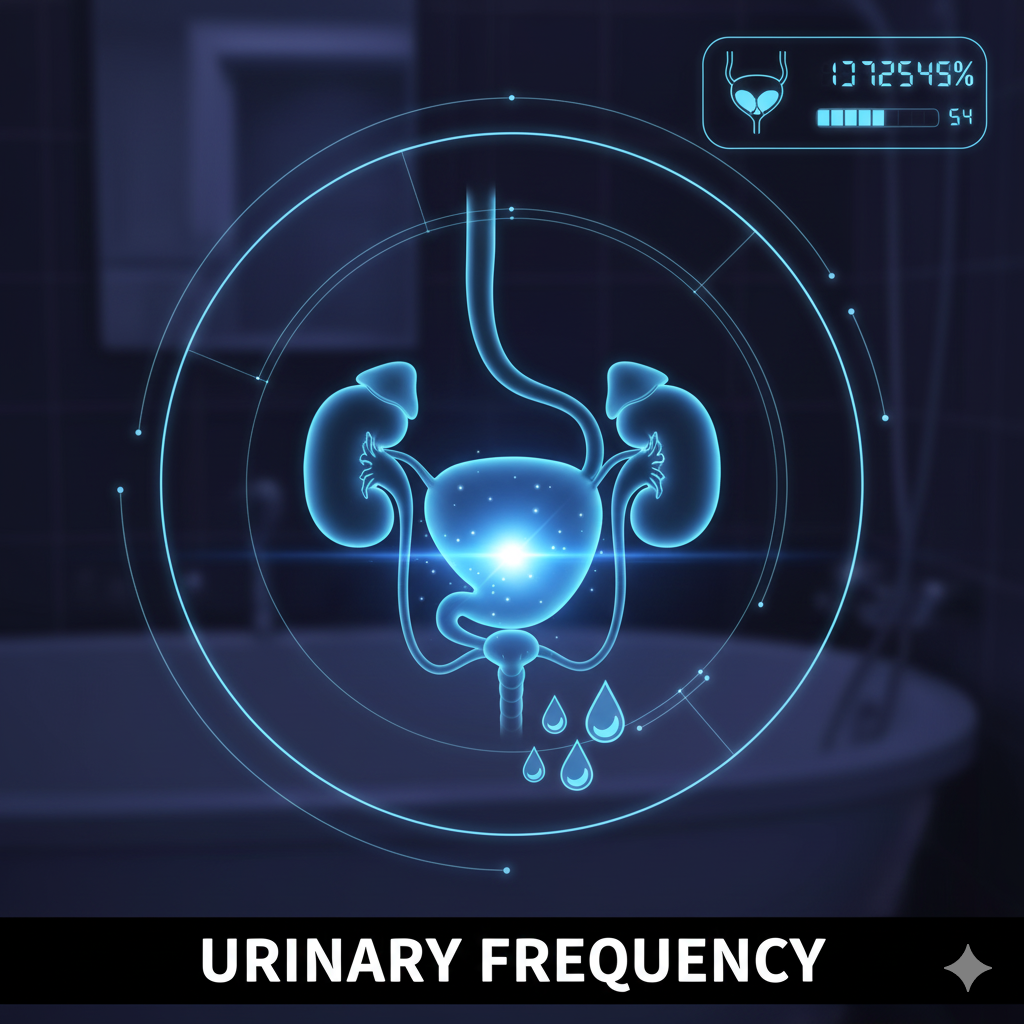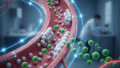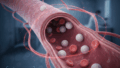トイレが近い「頻尿」の原因とは?男女別の理由からセルフケア、病院での治療法まで徹底解説
頻尿の概要
頻尿とは、排尿回数が通常よりも多い状態を指します。
医学的には、日中(朝起きてから寝るまで)の排尿回数が8回以上、または夜間(寝てから朝起きるまで)に排尿のために1回以上起きる状態を「夜間頻尿」と呼び、これらを頻尿の目安としています。
ただし、これはあくまで目安であり、排尿回数には個人差があります。
回数が8回以下でも、ご自身が「トイレが近い」「回数が多くて困る」と感じていれば、それは頻尿と言えます。
頻尿は単に水分を摂りすぎているだけでなく、加齢やストレス、さらには何らかの病気が原因となっている可能性もあります。
日常生活の質(QOL)に大きく関わる悩みであるため、その原因を正しく理解し、適切に対処することが重要です。
この記事では、頻尿が起こるさまざまな原因を男女別に掘り下げ、自分でできる対策から専門的な治療法まで詳しく解説します。
頻尿の詳細:原因と対策
頻尿の症状は、排尿回数が多いこと以外にも、「急に強い尿意を感じ、我慢するのが難しい(尿意切迫感)」や、「トイレに間に合わずに漏れてしまう(切迫性尿失禁)」などを伴う場合があります。
頻尿の原因は一つではなく、複数の要因が関わっていることも少なくありません。
頻尿を引き起こす主な原因
1. 水分の過剰摂取
当然ながら、水やお茶、アルコールなどを大量に飲むと尿量が増え、排尿回数も増えます。
特にカフェインを含むコーヒーや緑茶、アルコール類には利尿作用があるため、頻尿になりやすくなります。
2. 加齢による変化
年齢を重ねると、夜間の抗利尿ホルモン(尿を濃縮して量を減らすホルモン)の分泌が減少し、夜間に作られる尿量が増えることがあります。
また、膀胱の弾力性が低下し、溜められる尿の量(膀胱容量)が少なくなることも原因となります。
3. 過活動膀胱(OAB)
膀胱に尿が十分に溜まっていなくても、膀胱が過敏になって自分の意思とは関係なく収縮してしまう病気です。
急な強い尿意(尿意切迫感)が特徴で、頻尿や夜間頻尿、時には切迫性尿失禁を伴います。
加齢のほか、原因が特定できない場合も多くあります。
4. 心因性頻尿
緊張や不安、ストレスなど、精神的な要因によってトイレが近くなる状態です。
膀胱や尿道に異常はありませんが、トイレのことが気になって何度も行ってしまいます。
就寝中は症状が出ないのが特徴です。
男女別の主な原因
頻尿の原因には、性別によって特有のものがあります。
-
男性特有の原因:「前立腺肥大症」
中高年の男性に非常に多い病気です。男性にしかない前立腺という臓器が加齢とともに肥大し、尿道を圧迫します。
これにより、尿が出にくくなる(排尿困難)だけでなく、膀胱が過敏になったり、排尿後も尿が膀胱に残る「残尿」が生じたりするため、頻尿や夜間頻尿の症状が現れます。
-
女性特有の原因:「膀胱炎」「骨盤底筋の緩み」
女性は男性に比べて尿道が短いため、細菌が膀胱に入りやすく「膀胱炎」を起こしやすい特徴があります。膀胱炎になると膀胱の知覚神経が刺激され、頻尿、排尿時痛、残尿感などの症状が出ます。
また、出産や加齢によって、膀胱や子宮などを支える「骨盤底筋」という筋肉が緩むことがあります。
これにより尿道をうまく締められなくなり、咳やくしゃみで尿が漏れる「腹圧性尿失禁」や、頻尿の原因となることがあります。
隠れている可能性のある病気
頻尿は、以下のような全身性の病気の一症状として現れることもあります。
-
糖尿病: 血糖値が高いと、尿中に糖が排出される際に水分も一緒に排出されるため尿量が増えます(多尿)。
また、喉が渇きやすくなるため水分摂取量も増えます。
-
尿路感染症: 膀胱炎や前立腺炎、腎盂腎炎など、尿の通り道での感染症は膀胱を刺激し頻尿を引き起こします。
-
子宮筋腫・卵巣腫瘍: 女性の場合、筋腫や腫瘍が大きくなると膀胱を物理的に圧迫し、溜められる尿量が減って頻尿になることがあります。
自分でできる対策とセルフケア
頻尿の症状を和らげるために、日常生活で見直せるポイントがあります。
1. 水分摂取の調整
1日の水分摂取量(食事以外)は1.5リットル程度を目安にし、一度にがぶ飲みせず、こまめに摂るようにします。
特に就寝前の水分摂取は控えめにしましょう。
2. 利尿作用のあるものを控える
夕方以降は、カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶)やアルコールの摂取を控えることが有効です。
3. 体を冷やさない
体が冷えると尿意を感じやすくなるため、服装や入浴などで体を温め、血行を良く保ちましょう。
4. 骨盤底筋体操(ケーゲル体操)
特に女性や、前立腺の手術後の男性に有効です。
尿道を締める筋肉(骨盤底筋)を意識的に鍛えることで、尿意のコントロールや尿漏れの改善が期待できます。
5. 膀胱訓練
尿意を感じてもすぐにトイレに行かず、少し我慢する時間を設け、徐々に排尿間隔を延ばしていく訓練です。
ただし、自己流で行わず医師の指導のもとで行うのが安全です。
病院での診断と治療
頻尿が続く場合や、生活に支障が出ている場合は、我慢せずに「泌尿器科」を受診しましょう。
泌尿器科では、問診のほか、排尿日誌(いつ、どれくらいの量の尿が出たかを記録するもの)の確認、尿検査、超音波(エコー)検査(残尿量の確認、前立腺の大きさなど)を行い、原因を特定します。
治療は原因に応じて行われます。
膀胱炎などの感染症であれば抗生物質が処方されます。
過活動膀胱や前立腺肥大症の場合は、膀胱の異常な収縮を抑える薬や、前立腺の緊張を緩める薬など、薬物療法が中心となります。
その他、行動療法や、場合によっては手術が選択されることもあります。
参考動画
まとめ
頻尿は、単に「トイレが近い」という症状だけでなく、外出や乗り物での移動が不安になったり、夜間に何度も起きることで睡眠不足になったりと、生活の質(QOL)を大きく低下させる深刻な悩みです。
「年だから仕方ない」「恥ずかしい」と一人で抱え込まず、まずはセルフケアを試してみましょう。
それでも改善しない場合や、排尿時の痛み、血尿など他の症状を伴う場合は、重大な病気が隠れている可能性もあります。
頻尿は専門医のもとで適切な診断と治療を受ければ、多くの場合で改善が期待できる症状です。
気になる症状があれば、ぜひお近くの泌尿器科専門医にご相談ください。
関連トピック
過活動膀胱(OAB)
膀胱が過敏になり、急に我慢できないほどの強い尿意(尿意切迫感)を伴う病気です。
頻尿や夜間頻尿の主な原因の一つであり、特に中高年の女性に多く見られます。
前立腺肥大症
男性特有の病気で、加齢とともに前立腺が大きくなり尿道を圧迫します。
尿が出にくい、残尿感がある、トイレが近い(頻尿・夜間頻尿)といった症状を引き起こします。
夜間頻尿
夜間、排尿のために1回以上起きてしまう状態を指します。
加齢による抗利尿ホルモンの減少、水分の摂りすぎ、過活動膀胱、前立腺肥大症など、さまざまな原因で起こり、睡眠の質を大きく低下させます。
骨盤底筋体操
尿道を締める役割を持つ「骨盤底筋」を鍛えるトレーニングです。
特に女性の腹圧性尿失禁や、出産・加齢による頻尿の改善に効果が期待できます。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。
頻尿の原因と対処法 – YouTube