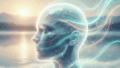腕が上がらない、夜痛む…「五十肩」とは?原因、症状の3つの時期、正しい対処法とストレッチまで徹底解説
五十肩の概要
五十肩(ごじゅうかた)は、特定の病名ではなく、40代から50代に多く見られる肩の痛みと可動域制限(動きにくさ)を伴う症状の総称です。
正式な医学用語では「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」と呼ばれます。
40代で発症した場合は「四十肩(しじゅうかた)」と呼ばれることもありますが、五十肩と四十肩は基本的には同じ病態を指し、症状や治療法に違いはありません。
主な原因は、加齢に伴い、肩関節を構成する骨、軟骨、靱帯、腱、あるいは関節を包む袋(関節包)といった組織が炎症を起こすことと考えられています。
多くの場合は自然に治癒に向かうとされていますが、放置すると肩が固まったまま(拘縮)になるリスクもあるため、症状の時期に合わせた適切な対処が非常に重要です。
五十肩の詳細:原因、3つの時期、治療法
五十肩は、ある日突然、腕を上げようとした時や服を着替えようとした時に「ズキッ」という痛みで発症することが多いです。
この厄介な症状について、その原因、特徴的な症状の経過、そして治療法を詳しく解説します。
五十肩の原因
五十肩のはっきりとした原因は、実はまだ完全には解明されていません。
しかし、一般的には加齢によって肩関節の周辺組織がもろくなり、そこに何らかの負担がかかることで炎症が生じると考えられています。
肩関節は非常に可動域が広い分、構造が複雑で不安定な側面も持っています。
加齢による組織の変化や、日々の小さな負荷の蓄積、運動不足、時にはストレスなどが引き金となり、肩関節の周囲にある「関節包」や「腱板」といった組織に炎症が起こり、痛みや可動域の制限を引き起こすのです。
五十肩の症状と経過:「3つの時期」
五十肩の症状は、一般的に「急性期(炎症期)」「慢性期(拘縮期)」「回復期」という3つの時期を経て、約半年から1年半、長い場合は数年かけて回復していくのが特徴です。
それぞれの時期で適切な対処法が異なります。
1. 急性期(炎症期):痛みが最も強い時期
-
症状: 症状の出始めの時期で、炎症が最も強い時期です。
「ズキズキ」「ジンジン」とした激しい痛みが特徴で、腕を動かした時だけでなく、安静にしている時にも痛み(安静時痛)が出ることがあります。
特に夜間に痛みが強くなる「夜間痛」が顕著で、痛みで寝返りが打てなかったり、目が覚めてしまったりすることが多く、非常につらい時期です。
-
対処法: この時期の最優先事項は「安静」です。
炎症を抑えることが重要であり、無理に動かしたり、ストレッチやマッサージをしたりすると、かえって炎症を悪化させてしまう可能性があります。
痛む肩を無理に使わず、安静を保つことが大切です。
痛みが強い場合は、整形外科を受診し、消炎鎮痛剤の内服薬や湿布、場合によってはステロイド注射などで炎症と痛みを抑える治療が行われます。
寝る時は、痛む方の肩の下にタオルやクッションを敷いて、肩が後方に落ちないように工夫すると夜間痛が和らぐことがあります。
2. 慢性期(拘縮期):痛みが和らぎ、「固まる」時期
-
症状: 急性期の激しい痛みは徐々に和らいでいきますが、今度は肩の「拘縮(こうしゅく)」、つまり肩関節が固まって動きにくくなる症状が顕著になります。
炎症によって関節包が癒着したり、厚く硬くなったりすることが原因です。
腕を上げる動作(洗濯物を干すなど)や、腕を背中に回す動作(エプロンの紐を結ぶ:結帯動作、髪を結ぶ:結髪動作)が困難になります。
無理に動かそうとすると、強い痛みが出ます。
-
対処法: この時期からは、痛みのない範囲で徐々に肩を動かす「リハビリテーション(運動療法やストレッチ)」を開始することが非常に重要です。
固まった関節包や筋肉をほぐし、可動域を広げていくことが目的です。
お風呂上がりなど、体が温まって血行が良くなっている時に行うのが効果的です。
ただし、強い痛みを感じるまで行うのは禁物です。
医師や理学療法士の指導のもと、正しいストレッチを行うことが推奨されます。
3. 回復期:徐々に可動域が戻る時期
-
症状: 痛みも拘縮も徐々に改善し、肩の可動域が少しずつ広がってくる時期です。
-
対処法: 引き続き、慢性期に始めたストレッチや運動療法を根気強く続けます。
ここで油断せず、日常生活でも意識的に肩を動かすようにしていくことで、回復が早まり、可動域制限などの後遺症を防ぐことができます。
五十肩の治療
五十肩が疑われる場合、まずは整形外科を受診することが重要です。
肩の痛みを引き起こす病気には、五十肩と症状が似ていても治療法が全く異なる「腱板断裂」や「石灰沈着性腱板炎」などがあるため、自己判断は危険です。
病院では、レントゲンや超音波(エコー)、MRIなどの検査で正確な診断が行われます。
治療は、前述の「3つの時期」に合わせて、以下のような保存療法(手術をしない治療)が中心となります。
-
薬物療法: 消炎鎮痛剤の飲み薬、湿布、塗り薬などで炎症と痛みを抑えます。
-
注射: 痛みが非常に強い急性期には、関節内にステロイドやヒアルロン酸、局所麻酔薬などを注射することで、強力に炎症と痛みを抑えることができます。
-
リハビリテーション(理学療法): 慢性期から回復期にかけて、理学療法士の指導のもとでストレッチや運動療法を行い、可動域の回復を目指します。
これらの保存療法で改善しない場合や、拘縮が長期間続く場合には、まれに関節鏡を使った手術が検討されることもあります。
参考動画:五十肩におすすめ 肩ストレッチ
まとめ:時期に合わせた対処が回復の鍵
五十肩は、40代や50代の多くの人が経験する可能性のある身近な症状です。
激しい痛みや長引く不便さから、生活の質(QOL)が大きく低下することもあります。
「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、痛みが引いた後も肩が上がらないといった後遺症が残ってしまう可能性もあります。
五十肩の治療で最も大切なのは、急性期・慢性期・回復期という自分の「時期」を正しく把握し、その時期に合った適切な対処を行うことです。
痛みが強い急性期は安静にし、痛みが和らいできた慢性期からは根気強くリハビリを続ける。
このメリハリが、早期回復と後遺症予防の鍵となります。
肩に異常を感じたら、まずは専門医である整形外科を受診し、正しい診断とアドバイスを受けるようにしてください。
「五十肩」に関連するトピック
肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)
五十肩の正式な医学的診断名です。肩関節の周囲にある組織(関節包、腱、靱帯など)に炎症が起きている状態を指します。
四十肩(しじゅうかた)
五十肩と同じ「肩関節周囲炎」を指しますが、主に40代で発症した場合に使われる俗称です。症状や原因に違いはありません。
腱板断裂(けんばんだんれつ)
五十肩と間違われやすい病気の一つです。肩を動かす重要な筋肉(腱板)が、加齢や怪我によって断裂してしまう状態です。五十肩と異なり、腕を上げようとしても力が入らない、特定の角度で引っかかるような痛みが特徴で、治療法(手術が必要な場合がある)も異なります。
石灰沈着性腱板炎(せっかいちんちゃくせいけんばんえん)
これも五十肩と混同されやすい病気で、肩の腱板に石灰(カルシウムの結晶)が沈着し、急激な炎症を引き起こします。五十肩の急性期よりもさらに激しい、突発的な激痛(夜間に救急車を呼ぶほどの痛み)が特徴です。レントゲン検査で石灰が写ることで診断されます。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。