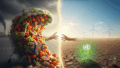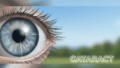🦻 難聴(きこえの障害)を徹底解説!種類、原因、最新の治療と認知症予防への重要性
難聴(きこえの障害)の概要
難聴とは、音を聞き取る能力が低下している状態の総称で、専門的には「きこえの障害」を意味します。
難聴は、軽度なものから高度なものまで様々な程度があり、音が小さく聞こえるだけでなく、言葉の聞き分けが難しくなることが、日常生活やコミュニケーションにおける大きな問題となります。
加齢や騒音への曝露などによって徐々に進行するケースが多い一方で、突発性難聴のように突然発症し、早期の治療が必要となる病気もあります。
難聴の放置は、生活の質(QOL)を大きく低下させるだけでなく、認知症のリスクを高めることが指摘されており、適切な診断と対策が非常に重要です。
難聴(きこえの障害)の詳細
難聴の主要な3つの種類と発生部位
1. 伝音難聴(音を伝える部分の障害)
伝音難聴は、音を内耳に伝えるまでの経路、すなわち外耳や中耳に問題があることで起こります。
原因としては、耳垢塞栓(耳垢の詰まり)、急性・慢性中耳炎、滲出性中耳炎、鼓膜穿孔(鼓膜に穴が開く)、耳小骨の異常などが挙げられます。
この種類の難聴では、音が小さく聞こえますが、音量を上げれば比較的はっきりと聞こえることが特徴です。
原因となる病気の治療(薬物治療や手術など)によって聴力が改善するケースが多いです。
2. 感音難聴(音を感じる・認識する部分の障害)
感音難聴は、音の振動を電気信号に変換する内耳(蝸牛)にある有毛細胞や、その信号を脳に送る聴神経に障害があることで起こります。
この難聴は、音が小さく聞こえるだけでなく、音の歪みや言葉の聞き分けの難しさ(明瞭度の低下)を伴うのが特徴です。
一般的な原因として、加齢性難聴(老人性難聴)、騒音性難聴、突発性難聴、メニエール病、遺伝的要因、薬剤の副作用などがあります。
残念ながら、有毛細胞の損傷は現在の医学では回復が難しいことが多く、治療は補聴器や人工内耳による聴覚の補助が中心となります。
3. 混合性難聴
混合性難聴は、上記2つのタイプ、すなわち伝音難聴と感音難聴の両方の要素を併せ持つ難聴です。
外耳・中耳と内耳・聴神経の両方に問題がある場合に発生し、原因疾患に応じて薬物治療、手術、補聴器、人工内耳などが組み合わせて検討されます。
難聴の治療法と最新の補聴機器
難聴の治療は、原因と種類、難聴の程度によって異なります。
薬物治療・手術
伝音難聴や、感音難聴の中でも突発性難聴やメニエール病などの急性期の病態に対しては、ステロイド剤の投与や血管拡張剤の使用などの薬物治療が中心となります。
慢性中耳炎や耳硬化症などの中耳の構造的な問題がある場合は、手術によって聴力が改善することが期待できます。
補聴器(Hearing Aid)
治癒が難しい感音難聴、特に軽度から高度の難聴に対しては、補聴器が最も一般的な対処法です。
補聴器は、外部の音を大きくして内耳に届ける役割を果たしますが、感音難聴ではただ音を大きくするだけでなく、言葉の聞き分けを助けるための調整(適合)が重要になります。
人工内耳(Cochlear Implant)
補聴器の効果が不十分な高度から重度の感音難聴者に対しては、人工内耳が唯一の聴覚獲得手段となる場合があります。
人工内耳は、蝸牛の損傷した部分を迂回し、電極を内耳に埋め込んで聴神経に直接電気信号を送ることで、音として認識させる医療機器です。
手術が必要ですが、特に成人においては、リハビリテーションを通じて言葉の聞き取りが大幅に改善する可能性があります。
難聴と認知症予防の関連性
近年、難聴と認知症の関連性が注目されています。
難聴を放置すると、会話や周囲の音の情報を脳が十分に受け取れなくなり、脳の聴覚野への刺激が減少します。
これにより、情報処理能力や認知機能の低下を招き、認知症の発症リスクが高まることが複数の研究で示唆されています。
難聴対策は、単に「聞こえ」の問題を解決するだけでなく、脳の健康を保ち、認知症を予防する上で重要な役割を果たすと考えられています。
聴力の低下を感じたら、できるだけ早く専門の耳鼻咽喉科を受診し、適切な補聴器などの対策を講じることが、健康寿命の延伸につながります。
難聴(きこえの障害)のまとめ
難聴は、私たち一人ひとりの行動が直接的に影響する、非常に身近な社会問題であり、SDGs達成のための最重要課題の一つです。
難聴は、加齢や騒音など様々な原因で起こる身近な問題であり、伝音難聴、感音難聴、混合性難聴に分類されます。
伝音難聴は治療で改善する可能性がありますが、感音難聴は補聴器や人工内耳といった人工聴覚器による補助が中心となります。
難聴を放置することは、コミュニケーションの困難さ、生活の質の低下に加え、認知症のリスク増加にもつながるため、早期の診断と介入が求められています。
聞こえに不安を感じたら、まずは耳鼻咽喉科を受診し、自身の難聴タイプと程度を正確に把握することが、より豊かな生活を送るための第一歩となります。
難聴は治らないと諦めず、補聴器や人工内耳など、進化する技術を積極的に活用することが大切です。
難聴(きこえの障害)の関連トピック
加齢性難聴(老人性難聴):加齢に伴い、内耳の有毛細胞が徐々に減少し、聴力が低下する最も一般的な感音難聴です。
突発性難聴:突然、片耳または両耳の聴力が低下する感音難聴で、早期(発症から1週間以内)の治療開始が予後を大きく左右します。
補聴器:外部の音を増幅して聞こえを補助する医療機器です。難聴の程度や種類に応じて、様々なタイプがあります。
人工内耳:補聴器で効果が得られない高度・重度感音難聴者に対し、蝸牛に埋め込んだ電極で聴神経を刺激し聴覚を再建する医療機器です。
耳鳴り:難聴にしばしば伴う症状で、外部には音源がないにもかかわらず、耳の中で「キーン」「ジー」といった音が聞こえる状態です。
難聴(きこえの障害)の関連資料
よくわかる難聴(金原出版など):聴覚障害者やその支援者を対象に、難聴のメカニズム、原因、評価方法などを専門的かつ分かりやすく解説した書籍です。
「よく聞こえない」ときの耳の本(朝日新聞出版など):難聴と補聴器だけでなく、耳鳴りの治療や人工内耳まで、幅広い聴覚ケアに焦点を当てた一般向けのムック(雑誌)です。
聴覚障害(クリア言語聴覚療法10)(建帛社):言語聴覚士などの専門家向けに、聴覚系の構造・機能、難聴の病理、リハビリテーション支援などを体系的に解説した専門書です。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。