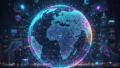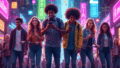ジェンダーギャップ指数2024、日本は118位。G7最下位の現状と課題、解消のメリットを徹底解説
ジェンダーギャップの概要
ジェンダーギャップとは、教育、経済、政治、健康といった社会の様々な分野における、性別による格差や不平等のことを指します。
この格差を数値化し、世界各国の状況を毎年発表しているのが、世界経済フォーラム(WEF)による「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」です。
2024年6月に発表された最新の報告書では、日本の総合順位は146カ国中118位でした。
これは、過去最低だった2023年の125位からは上昇したものの、G7(先進7カ国)の中では依然として最下位という深刻な状況を示しています。
特に「政治」と「経済」の分野での遅れが、日本のジェンダーギャップ指数の足を大きく引っ張っています。
この記事では、「ジェンダーギャップ 概要」から日本の具体的な課題、そしてなぜ格差解消が必要なのかを詳しく解説します。
ジェンダーギャップの詳細
ジェンダーギャップ指数とは?
ジェンダーギャップ指数(Gender Gap Index: GGI)は、世界経済フォーラム(WEF)が2006年から毎年公表している指標です。
各国の男女平等達成度を測ることを目的としています。
この指数は、以下の4つの基本的な分野における格差に基づいています。
-
経済: 労働参加率、男女間の賃金格差、管理職や専門職における女性比率など。
-
政治: 国会議員の女性比率、閣僚の女性比率、過去50年間の女性国家元首(首相や大統領)の在任期間など。
-
教育: 識字率、初等・中等・高等教育への就学率における男女差など。
-
健康: 出生時性比、男女の健康寿命の差など。
スコアは0が完全な不平等、1が完全な平等を示します。
2024年、日本の現在地
2024年の報告書で、日本の総合スコアは0.663(118位)でした。
2023年の125位からは順位を上げたものの、達成度は100%のうち約66.3%に留まっています。
G7の中では最下位が定位置となっており、他の先進諸国から大きく遅れをとっているのが実情です。
分野別に見ると、日本の課題はより鮮明になります。
-
健康: 58位(スコア0.973)
-
教育: 72位(スコア0.993)
-
経済: 120位(スコア0.568)
-
政治: 113位(スコア0.118)
健康や教育分野では高い水準を維持していますが、「経済」と「政治」の分野でのスコアが極端に低く、これが総合順位を押し下げる最大の要因となっています。
日本が抱える深刻な課題:なぜ順位が低いのか?
日本のジェンダーギャップ、特に「経済」と「政治」における格差はなぜ解消されないのでしょうか。
経済分野(120位)の課題
日本の経済分野におけるスコアの低さは、主に「男女間の賃金格差」と「指導的地位(管理職)の女性比率の低さ」に起因します。
日本の女性の平均賃金は、男性の約75%程度に留まっているというデータもあります。
この背景には、日本社会に根強く残る「性別役割分担意識」(男性は仕事、女性は家庭)があります。
この無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)により、女性が出産・育児を機にキャリアを中断せざるを得ない「M字カーブ」の問題が依然として存在します。
育児休業後に復職しても非正規雇用になるケースが多く、昇進や昇給の機会から遠ざけられがちです。
また、家事・育児の負担が女性に大きく偏っている現実(日本人女性の家事関連時間は男性の数倍にのぼる)も、女性の経済的自立とキャリア形成を阻んでいます。
政治分野(113位)の課題
政治分野のスコアは、2023年の138位から見れば改善しました。
これは2023年の内閣改造で一時的に女性閣僚が5人(全閣僚の4分の1)になったことが影響しています。
しかし、世界的に見れば依然として極めて低い水準です。
国会議員(特に衆議院)に占める女性の割合は低迷しており、政策決定の場に女性の声が届きにくい構造があります。
さらに、過去50年以上にわたり、日本で女性の首相が誕生していないことも、政治分野のスコアを下げる要因となっています。
なぜジェンダーギャップの解消が必要なのか?
ジェンダーギャップの解消は、単に「女性のため」の問題ではありません。
これは社会全体、特に経済の持続的成長にとって不可欠な課題です。
ジェンダーギャップが大きい社会は、人口の半分である女性の能力や才能を十分に活用できていないことを意味します。
これは、深刻な労働力不足に直面する日本にとって、大きな経済的損失です。
多様な視点(ダイバーシティ)が欠如することで、企業のイノベーションや競争力も阻害されます。
逆に、ジェンダーギャップを解消し、女性が経済活動や政治活動に平等に参加できるようになれば、新たな視点がもたらされ、経済全体の生産性が向上すると期待されています。
男女ともにワーク・ライフ・バランスを実現し、性別に関わらず誰もがその能力を最大限に発揮できる社会を築くことは、社会全体の利益に繋がるのです。
参考動画
まとめ
2024年のジェンダーギャップ指数で日本は118位と、G7最下位の状況が続いています。
特に「政治」と「経済」における深刻な格差が、その主な原因です。
この背景には、「男性は仕事、女性は家庭」といった根強い性別役割分担意識や、それに伴う家事・育児負担の偏りがあります。
ジェンダーギャップの解消は、女性だけの問題ではなく、労働力不足の解消、経済成長、社会の多様性確保といった、日本社会全体が直面する課題の解決に直結します。
私たち一人ひとりが、まずは自分の中にある「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」に気づき、家庭や職場で性別に基づく役割の押し付けをなくしていくことが、格差解消への重要な第一歩となるでしょう。
関連トピック
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見):
「女性だからお茶汲み」「男性だから力仕事」といった、性別に基づく無意識の思い込みや偏見のこと。
これがジェンダーギャップを生む温床の一つとされています。
M字カーブ:
日本の女性の労働力率を年齢階級別に見ると、結婚・出産期にあたる30代で一度低下し、育児が落ち着く40代で再び上昇するという、アルファベットの「M」の字に似たグラフを描く現象を指します。
男女間賃金格差:
正規・非正規雇用間の格差や、同じ職務内容でも性別によって賃金に差が生じる問題。
日本の経済分野における大きな課題の一つです。
クオータ制:
政治分野(議席)や企業(役員)において、女性の割合を一定数割り当てる制度のこと。
ジェンダーギャップ解消を加速させるための一手法として、世界各国で導入が議論されています。
関連資料
世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書(Global Gender Gap Report)」:
この記事で紹介した指数の大元となる公式報告書です。
世界経済フォーラムの公式サイトで閲覧可能で、各国の詳細なデータが確認できます。
『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ著):
韓国の小説ですが、結婚・出産を機にキャリアを絶たれ、家事や育児の中で徐々に自分を失っていく女性の姿を描写。
日本を含むアジア社会に共通する性別役割分担意識の問題を浮き彫りにし、大きな反響を呼びました。
内閣府男女共同参画局:
日本政府の男女共同参画に関する公式な取り組みや最新データ(「男女共同参画白書」など)が公開されています。
日本の現状をデータで深く知りたい場合の参考になります。