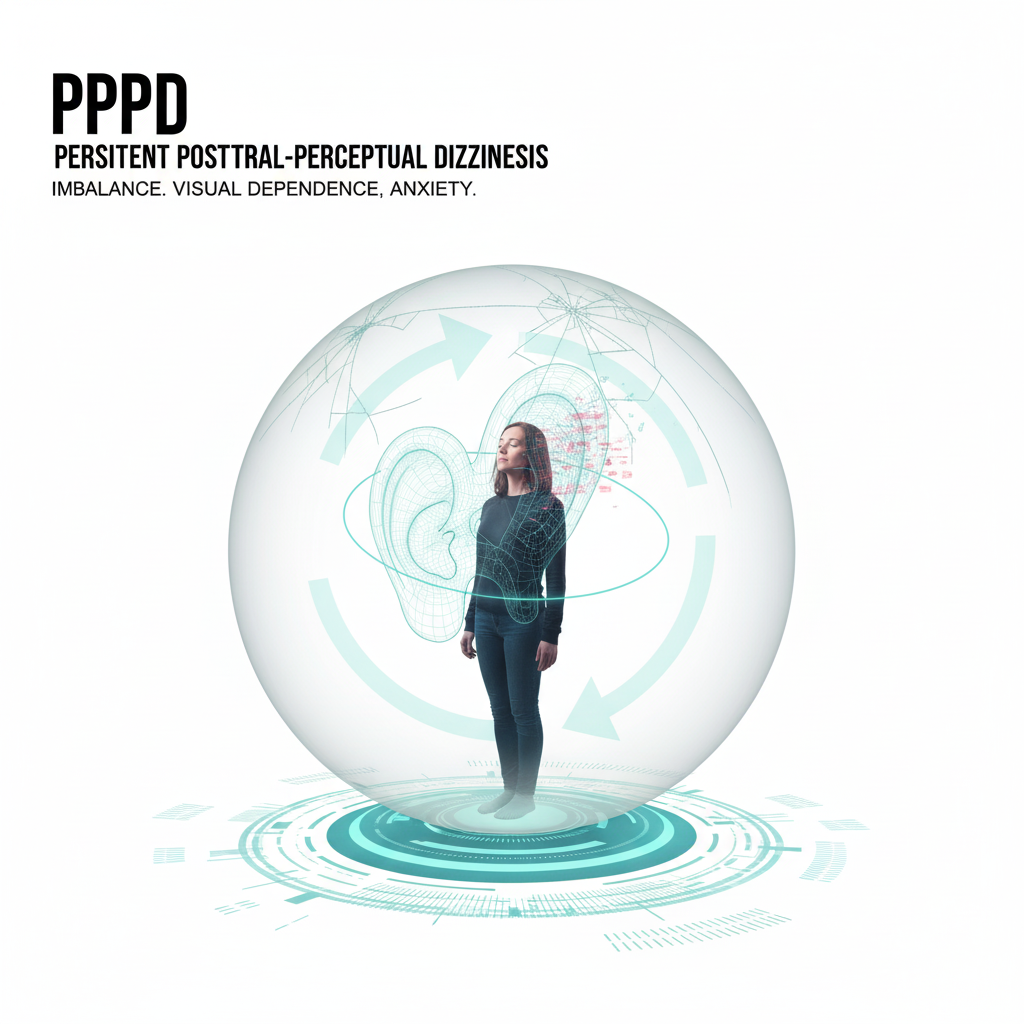繰り返す「めまい」はメニエール病?症状の特徴、原因、治療法まで徹底解説
「メニエール病」の概要
メニエール病とは、ある日突然、激しい回転性のめまい(自分や周囲がぐるぐる回る感じ)が起こり、それと同時に難聴、耳鳴り、耳が詰まった感じ(耳閉感)といった聴覚の症状が現れる病気です。
この一連の発作は、数十分から数時間続くことが多いですが、治まっても繰り返し再発するのが最大の特徴です。
原因は内耳(耳の奥)にあるリンパ液が増えすぎ、水ぶくれ(内リンパ水腫)になることだと考えられています。
30代後半から40代前半の女性に比較的多く見られ、ストレスや疲労、睡眠不足が発症の引き金になるとも言われています。
「メニエール病」の詳細
メニエール病は、放置すると難聴が進行したり、めまい発作が頻繁に起こることで日常生活に大きな支障をきたしたりする可能性があるため、正しい理解と早期の対応が重要です。
メニエール病の主な症状
メニエール病の症状は、主に「めまい」と「聴覚症状」の二つに分けられ、これらが同時に、かつ繰り返し起こることが診断の鍵となります。
1. 回転性のめまい発作
前触れなく、突然、自分自身や周囲がぐるぐる回るような激しいめまいが起こります。
多くの場合、強い吐き気や嘔吐を伴います。
このめまい発作は、通常10分程度から数時間続きますが、1日中続くことは稀です。
2. 聴覚症状(主に片耳)
めまいと連動して、以下のような聴覚症状が現れます。
-
難聴: 特に低い音(低音域)が聞こえにくくなるのが特徴です。
-
耳鳴り: 「ジー」「キーン」「ゴー」といった耳鳴りがします。
-
耳閉感(じへいかん): 耳が詰まったような、圧迫されるような感覚です。
これらの聴覚症状は、めまい発作が治まると軽快または消失することが多いですが、発作を繰り返すうちに徐々に悪化し、難聴が進行してしまうケースもあります。
多くは片方の耳から発症しますが、経過とともに両耳に症状が出る場合もあります。
メニエール病の原因
メニエール病の直接的な原因は、音や平衡感覚を司る「内耳」が、「内リンパ水腫(ないリンパすいしゅ)」という水ぶくれ(むくみ)の状態になることだと考えられています。
内耳は内リンパ液という液体で満たされており、この液体が増えすぎると内耳の機能が圧迫され、めまいや難聴を引き起こすのです。
しかし、なぜ内リンパ液が増えすぎるのか、その根本的なメカニズムはまだ完全には解明されていません。
ただし、発症の誘因として、ストレス、睡眠不足、過労、几帳面な性格、気圧の変化などが強く関わっていると指摘されています。
診断と検査
めまい発作が1回起きただけでは、メニエール病とは診断されません。
「難聴、耳鳴り、耳閉感などの聴覚症状を伴うめまい発作を反復する(繰り返す)」ことが、診断の最も重要な基準となります。
診断のためには、まず聴力検査を行い、特に低音域の聴力が低下していないかを確認します。
また、めまいが起きている時に眼球の揺れ(眼振)を調べる検査(平衡機能検査)も行われます。
さらに、脳梗塞や脳腫瘍(特に聴神経腫瘍)など、他の重大な病気が隠れていないかを除外するために、MRIやCTなどの画像検査が行われることもあります。
治療法について
メニエール病の治療は、発作が起きている「発作期」と、症状が落ち着いている「間歇期(かんけつき)」で異なります。
発作期の治療
激しいめまいや吐き気があるため、まずは安静にし、症状を鎮めることが最優先です。
めまいを抑える薬(抗めまい薬)や吐き気止めのほか、内リンパ水腫を改善させるために利尿薬(水分を排出する薬)が点滴または内服で用いられます。
不安感が強い場合は、精神安定剤が処方されることもあります。
間歇期(予防的治療)
発作を繰り返さないようにすることが治療の目標となります。
根本的な原因とされるストレス、疲労、睡眠不足を日常生活からできるだけ取り除くことが最も重要です。 具体的には、十分な睡眠時間の確保、リラックスする時間の確保、適度な有酸素運動(ウォーキングやランニングなど)が推奨されます。
また、内耳の血流を改善する薬や、利尿薬、自律神経調整薬などが継続的に処方されることもあります。
水分を多めに摂る「飲水療法」が有効な場合もあります。
薬物療法や生活習慣の改善で効果が見られない場合や、難聴の進行が止まらない場合には、内耳に薬を注入する治療や、外科的な手術(内リンパ嚢開放術など)が検討されることもあります。
参考動画:メニエール病について
まとめ:生活習慣の見直しと早期受診
メニエール病は、激しいめまいと聴覚症状を繰り返す、日常生活に大きな影響を与える病気です。
しかし、その背景にはストレスや疲労といった生活習慣が深く関わっている「ストレス病」としての一面も持っています。
めまいはメニエール病だけでなく、脳の病気や他の耳の病気(良性発作性頭位めまい症など)が原因である可能性もあります。
「ぐるぐる回るめまい」や「耳鳴り・難聴」を自覚したら、決して自己判断せず、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診してください。
適切な治療を受けることと同時に、ご自身の生活習慣を見直し、ストレスと上手に付き合っていくことが、メニエール病の克服と再発防止の鍵となります。
関連トピック
良性発作性頭位めまい症(BPPV): めまいの原因として最も多い病気です。寝返りを打ったり、起き上がったりするときなど、頭を特定の位置に動かしたときに数十秒間の回転性めまいが起こりますが、難聴や耳鳴りは伴いません。
突発性難聴(とっぱつせいなんちょう): ある日突然、片方の耳が聞こえなくなる病気です。めまいを伴うこともありますが、発作を「繰り返す」ことはありません。早期の治療(ステロイド治療など)が非常に重要です。
内リンパ水腫(ないリンパすいしゅ): メニエール病の本体とされる、内耳がリンパ液でむくんだ状態を指します。
自律神経: ストレスや疲労は自律神経のバランスを乱し、内耳の血流にも影響を与えるため、メニエール病の発作の誘因となると考えられています。
関連資料
『めまい・メニエール病を自分で治す正しい知識と最新療法(書籍)』:メニエール病のメカニズムや、日常生活でできるセルフケア(運動療法、食事療法、ストレス対策)について解説した一般向けの書籍です。
『めまいメニエール病 自分で治す本(書籍)』: めまいを改善するための体操や、再発予防のための生活習慣の見直し方などを紹介したムック本です。
ストレス管理アプリ: 日々のストレスレベルを記録したり、瞑想(マインドフルネス)やリラクゼーション法をガイドしたりするスマートフォンアプリです。メニエール病の誘因となるストレス対策に役立ちます。
家庭用血圧計: メニエール病の治療や管理において、日々の体調管理は重要です。自律神経のバランスとも関連する血圧を日常的にチェックすることも一つの目安となります。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。