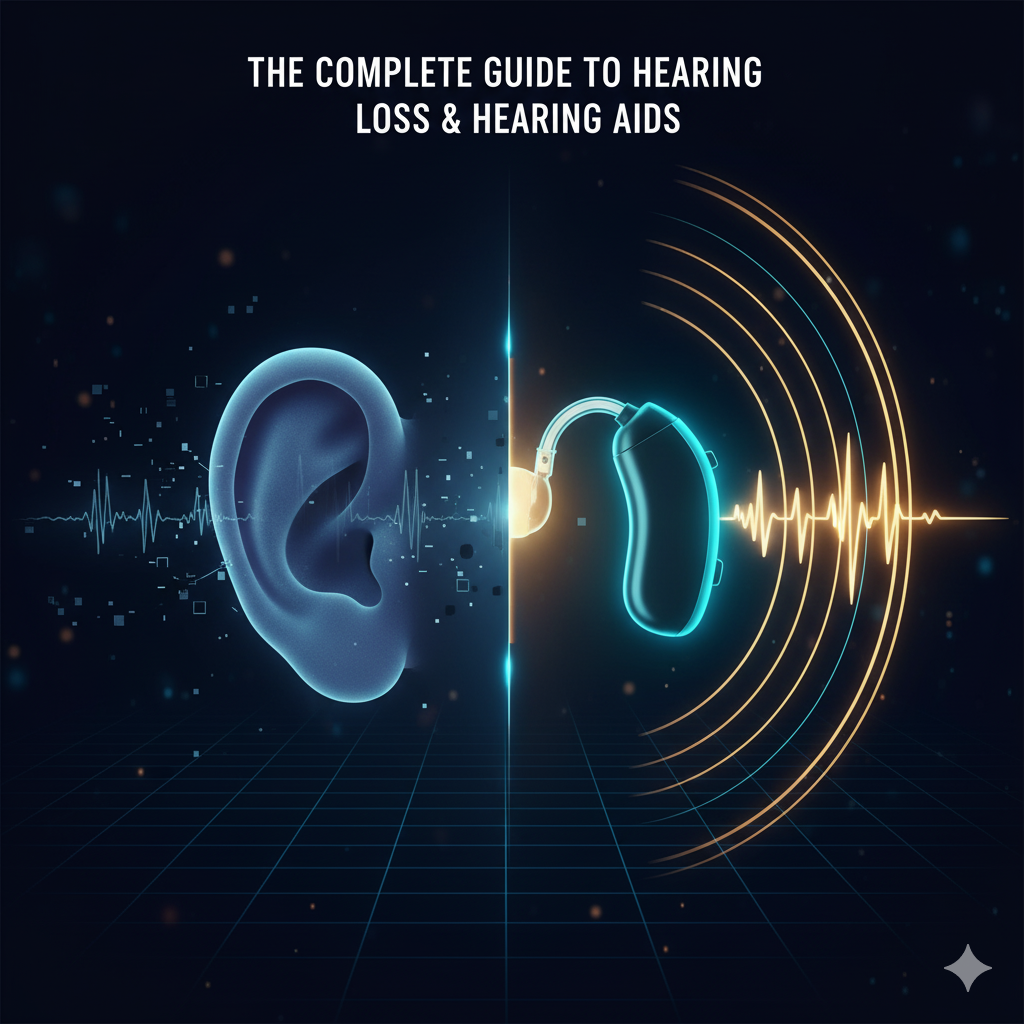聴覚障害と補聴器の完全ガイド:聞こえの悩みに寄り添う基礎知識と選び方、公的支援まで
聴覚障害と補聴器の概要
「最近、テレビの音が大きいと家族に言われる」。
「会議や雑談の中で、話が聞き取りにくくなった」。
このような「聞こえ」に関する悩みは、多くの方が経験する可能性のある身近な問題です。
聴覚障害(難聴)は、単に音が小さく聞こえるだけでなく、言葉の区別がつきにくくなるなど、コミュニケーションや生活の質(QOL)に大きく影響します。
その聞こえをサポートする最も代表的な手段が「補聴器」です。
この記事では、「聴覚障害 概要」としての基本的な知識から、「補聴器 選び方」のポイント、そして「補聴器 公的支援」に至るまで、聞こえの悩みを持つ方とそのご家族に知っていただきたい情報を分かりやすく解説します。
聴覚障害と補聴器の詳細
聴覚障害(難聴)とは?
聴覚障害(難聴)とは、耳のいずれかの部分に問題が生じ、音が聞こえにくい、または全く聞こえない状態を指します。
聴覚障害は、その原因がある場所によって、大きく3つの種類に分けられます。
1. 伝音性難聴
外耳(耳たぶ)や中耳(鼓膜など)といった「音を伝える経路」に問題がある場合に起こります。
耳垢が詰まっている、中耳炎を起こしている、などが原因です。
音が小さく聞こえるのが特徴ですが、多くの場合、適切な治療(耳垢の除去や中耳炎の治療)によって聴力が改善する可能性があります。
2. 感音性難聴
内耳(蝸牛)や聴神経といった「音を感じ取る神経」に問題がある場合に起こります。
音を感じ取る細胞(有毛細胞)が傷つくことが主な原因で、加齢による難聴(加齢性難聴)の多くがこれに含まれます。
感音性難聴は、単に音が小さく聞こえるだけでなく、「音が歪んで聞こえる」「言葉の聞き分けが難しくなる」といった症状を伴うことが多いのが特徴です。
現在の医学では、傷ついた神経を完全に元に戻すことは難しく、このタイプの難聴の「聞こえ」をサポートするのが補聴器の主な役割となります。
3. 混合性難聴
上記の伝音性難聴と感音性難聴の両方の原因を併せ持つ難聴です。
補聴器とは?その役割と仕組み
補聴器は、厚生労働省から「管理医療機器」として認定されているれっきとした医療機器です。
聞こえにくくなった音を、使用する人の聴力に合わせて増幅・調整し、「言葉の聞き取り」を改善することを最大の目的としています。
補聴器の基本的な仕組みは、「マイク(音を集める)」「アンプ(音を増幅・調整する)」「レシーバー(音を出す)」の3つで構成されています。
最近のデジタル補聴器はアンプの性能が非常に高く、単に音を大きくするだけでなく、騒音(雑音)を抑えながら会話の音域を強調するなど、個々の聴力や使用環境に合わせた細かい調整が可能です。
補聴器と集音器の違い
補聴器と混同されやすいものに「集音器」があります。
集音器は医療機器ではなく、音響機器(家電)に分類されます。
主な目的は、音を単純に大きくすることです。
補聴器のように、個々の聴力に合わせて音質を細かく調整する機能は限定的です。
「補聴器 評判」を調べる前に、まずは自分の聞こえにくさが治療可能なものか、補聴器が必要なレベルなのかを耳鼻咽喉科で診断してもらうことが重要です。
補聴器の主な種類と特徴
補聴器には、いくつかの形状があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
1. 耳かけ型
耳の後ろに本体をかけ、透明なチューブやワイヤーで耳栓(イヤホン)を耳の穴に挿入するタイプです。
-
メリット: 軽度から重度まで幅広い難聴に対応できます。
操作が比較的簡単で、電池も長持ちする傾向があります。
最近主流の「RIC(リック)タイプ」は非常に小型で目立ちにくく、音質も自然です。
-
デメリット: マスクやメガネの着脱時に、引っかかって落としやすい場合があります。
2. 耳あな型
耳の穴(外耳道)にすっぽりと収まるタイプです。
耳の型を採って作成するオーダーメイドが主流です。
-
メリット: 非常に小さく、外からほとんど見えないタイプ(CIC)もあります。
耳の穴に収まるため、風切り音がしにくく、電話も比較的しやすいです。
-
デメリット: 小型のため、電池の交換や操作(ボリューム調整など)がやや難しい場合があります。
耳垢や湿気の影響を受けやすい側面もあります。
3. ポケット型(箱型)
本体(マイクとアンプ)をポケットや胸元に入れ、コードで繋がったイヤホンを耳に入れて使用します。
-
メリット: 本体が大きいため、操作ボタンやスイッチが分かりやすく、操作が非常に簡単です。
比較的安価なモデルもあります。
-
デメリット: 本体とコードがあるため、持ち運びや装着感が煩わしく感じることがあります。
衣類と本体が擦れる音(衣擦れ音)が雑音として入ることがあります。
失敗しない補聴器の選び方
補聴器は購入してすぐに完璧に聞こえるようになるものではなく、適切な「選び方」と「調整(フィッティング)」が非常に重要です。
1. まずは耳鼻咽喉科を受診する:
聞こえにくさの原因が、治療可能な病気(伝音性難聴など)でないかを確認するため、まずは必ず耳鼻咽喉科の専門医の診断を受けてください。
「補聴器相談医」の資格を持つ医師であれば、補聴器の必要性についても的確に判断してもらえます。
2. 聴力と生活スタイルを伝える:
補聴器販売店(認定補聴器技能者が在籍する専門店が望ましい)では、聴力測定の結果に基づき、「どのような場面で聞き取りたいか(静かな自宅、騒がしい職場、会議など)」を具体的に伝えます。
3. 必ず「試聴(レンタル)」する:
補聴器は高価な買い物であり、その聞こえ方には個人差が大きいです。
購入前に必ず試聴期間(レンタル)を設け、自宅や職場など、普段の生活環境で実際に使ってみて、その効果を確かめましょう。
4. 購入後の調整(アフターケア)が鍵:
補聴器は「購入して終わり」ではありません。
使い始めてからがスタートです。
最初は小さな音量から始め、徐々に音に慣れていく「リハビリ」が必要です。
定期的に販売店に通い、聞こえの状態に合わせて音の調整(フィッティング)を繰り返すことで、自分に最適な補聴器に仕上がっていきます。
補聴器の公的支援(補助金)
補聴器の購入には公的な支援制度が利用できる場合があります。
-
障害者総合支援法(補装具費支給制度):
聴覚障害の程度が「身体障害者手帳」の交付基準に該当する場合、補聴器の購入費用の一部(原則1割負担、所得に応じて上限あり)が支給されます。
申請には、指定された耳鼻咽喉科医の診断書が必要です。
-
自治体独自の助成制度:
身体障害者手帳の基準に満たない軽度・中等度難聴の方や、高齢者向けに、自治体(市区町村)が独自に補聴器購入の助成金制度を設けている場合があります。
「(お住まいの自治体名) 補聴器 助成金」などで検索し、役所の福祉課窓口に問い合わせてみましょう。
参考動画
まとめ
聴覚障害(難聴)は、外見からは分かりにくいため、ご本人も周囲も気づきにくい障害の一つです。
しかし、聞こえにくさを放置することは、コミュニケーションの機会を減らし、社会的な孤立や、認知機能の低下に繋がるリスクも指摘されています。
補聴器は、失われた聴力を取り戻す魔法の道具ではありませんが、適切に選び、調整し、使いこなすことで、あなたの「聞きたい」という気持ちを力強くサポートし、生活の質を大きく向上させてくれる「医療機器」です。
もし、あなたやあなたの大切な人が「聞こえ」に少しでも不安を感じたら、まずは勇気を出して、耳鼻咽喉科の専門医に相談することから始めてみてください。
関連トピック
加齢性難聴:
年齢を重ねるにつれて、主に内耳(音を感じ取る部分)の機能が低下することで起こる難聴です。
高い音から聞こえにくくなるのが特徴で、補聴器によるサポートが非常に有効な難聴の一つです。
集音器:
補聴器(医療機器)とは異なり、音を大きくする「音響機器(家電)」です。
個々の聴力に合わせた詳細な調整はできませんが、比較的安価で、一時的に音を大きくしたい場合には有用なことがあります。
人工内耳:
補聴器を使用しても十分な効果が得られない、重度の感音性難聴(両耳)の方に向けた医療機器です。
内耳に電極を埋め込む手術が必要で、聴神経を直接電気刺激することで音を脳に伝えます。
認定補聴器技能者:
補聴器の選定や調整(フィッティング)に関する高い知識と技能を持つ専門家に与えられる資格です。
補聴器店を選ぶ際の一つの信頼の目安となります。
関連資料
書籍『よくわかる! 補聴器選び (専門医が教える!)』:
耳鼻咽喉科の専門医が、補聴器の基本的な知識から選び方、最新技術までを解説した一般向けの書籍です。
一般社団法人 日本補聴器販売店協会 (JHIDA):
補聴器に関する情報提供や、全国の「認定補聴器専門店」を検索できるウェブサイトを運営しています。
信頼できる販売店を探す際に役立ちます。
各自治体(市区町村)の福祉課ウェブサイト:
「補装具費支給制度」や、自治体独自の「高齢者向け補聴器助成金」などの公的支援に関する詳細な情報が掲載されています。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。