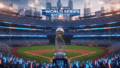「OTC類医薬品」とは?知っておきたい「指定第2類医薬品」の正しい知識と安全な選び方【OTC医薬品ガイド】
「OTC類医薬品」の概要
私たちが薬局やドラッグストアで処方箋なしに購入できる薬を「OTC医薬品」と呼びます。
このOTC医薬品は、含まれる成分のリスクの高さに応じて、いくつかのカテゴリに分類されています。
一般的に「類医薬品」と呼ばれるものは、この分類の中で「指定第2類医薬品」とされる医薬品を指すことが多いです。
これは、OTC医薬品の中でも比較的多くの人が利用するかぜ薬や解熱鎮痛薬などが含まれる一方で、副作用や飲み合わせ(相互作用)に特に注意が必要な区分です。
この記事では、「OTC類医薬品」の概要、特に「指定第2類医薬品」とは何か、その詳細や購入時の注意点について詳しく解説します。
「OTC類医薬品」の詳細
OTC医薬品とは?
OTC医薬品とは、「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略称です。
これは、薬局やドラッグストアのカウンター越しに、薬剤師などの専門家と相談しながら購入できる薬、という意味合いを持っています。
以前は「市販薬」や「大衆薬」とも呼ばれていました。
医師の診察と処方箋が必要な「医療用医薬品」とは異なり、消費者が自らの判断で症状に合わせて選ぶことができるのが特徴です。
OTC医薬品のリスク分類
OTC医薬品は、副作用のリスクや取り扱いの難易度に応じて、以下の4つに分類されています。
この分類によって、販売できる専門家(薬剤師か登録販売者か)や、情報提供の方法、陳列のルールが定められています。
1. 第1類医薬品:
副作用や相互作用などで安全性上、特に注意を要する成分を含みます。
購入の際は、薬剤師による文書を用いた情報提供が義務付けられています。
消費者が直接手に取れない場所(カウンターの内側など)に陳列されます。
(例:一部の胃薬(H2ブロッカー)、一部の育毛剤、スイッチOTC化されたばかりの薬など)
2. 第2類医薬品:
副作用や相互作用などで安全性上、注意を要する成分を含みます。
(例:多くの漢方薬、胃腸薬、便秘薬など)
3. 指定第2類医薬品(=通称:類医薬品):
これが、ユーザーの言う「OTC類医薬品」に該当するものと考えられます。
第2類医薬品に分類されるものの中で、副作用や依存性・習慣性のリスクから、特に注意が必要とされる成分を含む医薬品です。
パッケージには、「第②類医薬品」または「第(2)類医薬品」のように、「2」の数字が四角(□)や丸(〇)で囲まれて表示されています。
4. 第3類医薬品:
第1類、第2類に該当しないもので、比較的リスクが低いとされる医薬品です。
(例:ビタミン剤、整腸薬、一部の湿布薬など)
※この他に、医療用から市販薬に転用されて間もない「要指導医薬品」がありますが、これは薬剤師による対面での情報提供が必須で、OTC医薬品の分類とは少し異なります。
「指定第2類医薬品」の詳細と注意点
指定第2類医薬品は、私たちが日常的によく使用する薬が数多く含まれています。
-
具体的な医薬品の例:
総合感冒薬(かぜ薬)
解熱鎮痛薬(頭痛薬、生理痛薬)
鎮咳去痰薬(せき止め)
睡眠改善薬
アレルギー専用鼻炎薬
水虫薬(一部の成分)
痔疾用薬(一部の成分)
-
なぜ「特に注意」が必要なのか?
指定第2類医薬品には、以下のような理由から、他の第2類医薬品よりも慎重な使用が求められる成分が含まれています。
1. 依存性・習慣性がある成分:
一部の咳止めに含まれる「ジヒドロコデインリン酸塩」や、一部の鎮痛薬に含まれる「アリルイソプロピルアセチル尿素」、漢方薬の「マオウ」などは、長期連用や乱用により依存性を生じるリスクがあります。
2. 重い副作用のリスクがある成分:
解熱鎮痛成分(イブプロフェン、アスピリンなど)は、まれにスティーブンス・ジョンソン症候群や間質性肺炎といった重篤な副作用を引き起こす可能性があります。
3. 相互作用(飲み合わせ)のリスク:
複数の薬を併用することで、効果が強まりすぎたり、予期せぬ副作用が出たりするリスクがあります。
4. 使用対象者が限定される成分:
小児、高齢者、妊婦、授乳中の方、特定の持病(喘息、胃潰瘍、緑内障など)がある方は、使用してはいけない(禁忌)、または使用前に医師や薬剤師への相談が必須となる成分が含まれています。
-
購入時のルールとアドバイス
指定第2類医薬品は、薬剤師または登録販売者がいる店舗で購入できます。
第1類医薬品と異なり、専門家からの情報提供は「努力義務」とされています。
つまり、法律上は購入者から説明を求めない限り、必ずしも説明を受けなくても購入できてしまいます。
しかし、上記のようなリスクがあるため、厚生労働省は販売店に対し、購入者に積極的に情報提供を行うよう指導しています。
また、禁忌事項(使用してはいけない人)の確認や、専門家への相談を促す掲示をすることが義務付けられています。
安全に使用するためには、購入者側からも積極的に「今、他に飲んでいる薬はありますか?」「持病があるのですが使えますか?」といった相談をすることが非常に重要です。 店舗では、指定第2類医薬品は情報提供カウンターから7メートル以内の範囲に陳列するよう定められています。
参考動画
まとめ
「OTC類医薬品」、すなわち「指定第2類医薬品」は、かぜや頭痛といった日常的な症状を緩和してくれる、セルフメディケーションの柱となる医薬品です。
しかし、その利便性の裏には、第1類医薬品に準ずるほどのリスクが潜んでいる成分が含まれていることを忘れてはなりません。
パッケージの「第②類医薬品」という表示は、「特に注意して使うべき薬」というサインです。
購入時には、安易に自己判断せず、薬剤師または登録販売者に相談し、自分の症状や体質、他に飲んでいる薬との飲み合わせを確認してもらう習慣をつけましょう。
そして、購入後は必ず添付文書(説明書)を最後まで読み、用法・用量を守って正しく使用することが、自らの健康を守る上で最も重要です。
関連トピック
セルフメディケーション税制: 特定のOTC医薬品(スイッチOTC成分を含むもの)を年間1万2千円以上購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。指定第2類医薬品にも対象商品が多く含まれます。
スイッチOTC: これまで医療用医薬品として医師の処方が必要だった成分を、一般用医薬品として使用できるように転用(スイッチ)した医薬品のことです。第1類や指定第2類医薬品に多く見られます。
登録販売者: 都道府県知事の試験に合格した医薬品販売の専門家です。薬剤師とは異なり、第1類医薬品の販売はできませんが、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の販売と情報提供を担うことができます。
関連資料
総合感冒薬(かぜ薬): 発熱、のどの痛み、鼻水、せきなど、風邪の諸症状を緩和する多くの薬が指定第2類医薬品に分類されます。
解熱鎮痛薬: イブプロフェンやアセトアミノフェン(一部高含有量)、アスピリンなどを含む頭痛薬や生理痛薬です。
睡眠改善薬: 一時的な不眠症状を緩和する薬で、抗ヒスタミン成分の眠気を利用したものが多く、指定第2類医薬品となっています。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。