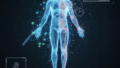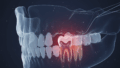梅毒が日本で急増中?その初期症状、感染経路、正しい検査と治療法を徹底解説
梅毒の概要
梅毒(ばいどく)は、「梅毒トレポネーマ」という細菌によって引き起こされる性感染症(STI)の一つです。
かつては過去の病気とされがちでしたが、近年、日本国内で感染報告数が再び急増しており、特に20代の女性や20代から40代の男性を中心に深刻な公衆衛生上の問題となっています。
梅毒は感染しても初期段階では症状が軽かったり、症状が出ても一時的に消えたりするため、「偉大なる偽装者」とも呼ばれています。
この特性から、感染に気づかないまま病状が進行したり、無自覚のうちにパートナーへ感染させてしまったりするリスクが高いことが特徴です。
しかし、梅毒は早期に発見し、適切な治療を受ければ完治が可能な病気です。
梅毒の詳細:症状、感染経路、治療法
梅毒の症状は、感染後の時間の経過によって大きく4つのステージに分けられます。
第1期梅毒
感染から約3週間が経過した頃に、細菌が侵入した場所(主に性器、肛門、口唇、口腔内など)にしこり(硬性下疳:こうせいげかん)や、ただれ(潰瘍)ができます。
このしこりや潰瘍は、痛みを伴わないことが多いのが特徴で、自然に(治療しなくても)数週間で消えてしまいます。
しかし、症状が消えても治ったわけではなく、細菌は体内に残っています。
第2期梅毒
感染から約1~3ヶ月後に、細菌が血液に乗って全身に広がります。
この時期の代表的な症状が「バラ疹(ばらしん)」と呼ばれる、手のひら、足の裏、体幹などに現れる赤く目立たない発疹です。
この発疹も痛みやかゆみを伴わないことが多く、数週間から数ヶ月で自然に消えていきます。
その他、発熱、倦怠感、リンパ節の腫れ、のどの痛みなど、風邪に似た症状が出ることもあります。
第1期および第2期は、特に感染力が高い時期とされています。
潜伏梅毒
第2期の症状が消えた後、再び症状のない期間(潜伏期)に入ります。
この期間は数年から数十年に及ぶこともありますが、体内で病気が静かに進行している状態です。
晩期梅毒(第3期・第4期)
感染から数年~数十年が経過すると、症状がない期間を経て、心臓、血管、脳、神経系などに深刻な障害を引き起こすことがあります。
ゴム腫と呼ばれる腫瘍が皮膚や骨にできることもあります。
現代の日本では、抗菌薬(抗生物質)による治療法が確立されているため、ここまで進行するケースは稀ですが、治療が遅れると重篤な後遺症を残す可能性があります。
梅毒の感染経路
主な感染経路は、第1期や第2期の症状(しこり、潰瘍、発疹など)が出ている部位と、粘膜や皮膚が直接接触することによる性的接触です。
オーラルセックスやアナルセックスを含む、あらゆる性行為によって感染する可能性があります。
また、妊婦が感染している場合、胎盤を通じて胎児に感染し、「先天梅毒」を引き起こすリスクがあります。
日常生活(お風呂、プール、食器の共用など)で感染することはほとんどありません。
検査と治療
梅毒の検査は、主に血液検査(抗体検査)によって行われます。
感染が疑われる行為から一定期間(約4週間以上)経過していないと、感染していても陰性(偽陰性)と出ることがあるため、不安な場合は時期を空けて再検査することが推奨されます。
梅毒の治療には、ペニシリン系の抗菌薬(抗生物質)が非常に有効です。
早期の梅毒であれば、内服薬を数週間服用するか、または注射(筋肉注射)を1回受けることで完治が期待できます。
治療が完了したかどうかは、再度血液検査を行って判断します。
パートナーが感染している場合は、自分に症状がなくても必ず一緒に検査・治療を受けることが極めて重要です。
参考動画:梅毒の流行状況(東京都)
まとめ:梅毒は早期発見・早期治療が鍵
梅毒の感染者数は、日本国内で近年顕著な増加傾向にあり、性的な活動がある人にとっては決して他人事ではない感染症です。
梅毒の最大の問題点は、症状が軽微であったり、症状が出ても自然に消えてしまったりするため、感染に気づきにくい点にあります。
しかし、放置すれば深刻な健康被害をもたらす可能性があり、また無自覚に他者へ感染を広げてしまうリスクを伴います。
早期発見と早期治療が、自身の健康を守るだけでなく、パートナーや社会全体の公衆衛生を守るために最も重要です。
少しでも不安な症状や、感染が疑われる行為があった場合は、決してためらわず、速やかに医療機関(性感染症科、泌尿器科、皮膚科、婦人科)や最寄りの保健所で相談・検査を受けるようにしてください。
梅毒に関連するトピック
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)
梅毒などの性感染症によって粘膜や皮膚に炎症や潰瘍があると、HIVにも同時に感染しやすくなる、あるいはさせやすくなると言われています。重複感染に注意が必要です。
クラミジア・淋病
梅毒と同様に、近年日本で増加傾向にある代表的な性感染症です。梅毒と同時に感染(重複感染)しているケースも少なくありません。
性感染症(STI)の予防
梅毒を含む多くの性感染症(STI)の予防には、コンドームを性行為の最初から最後まで正しく使用することが有効です。ただし、コンドームが覆わない部分の接触からも感染する可能性はゼロではありません。
先天梅毒
妊娠中の母親が梅毒に感染していると、胎盤を通じて胎児にも感染し、流産、死産、または新生児に重い障害(発達の遅れ、骨の異常など)を引き起こす可能性があります。妊婦健診での早期発見と治療が不可欠です。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。