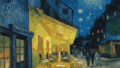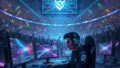叙勲とは? 旭日章と瑞宝章の違い、春と秋の栄典についてわかりやすく解説
「叙勲」の概要
「叙勲(じょくん)」とは、国家または公共に対して顕著な功労や功績があった人物に対し、国が勲章を授与する栄誉ある制度です。
長年にわたり社会の様々な分野で尽力した人々の功績を称えるもので、日本の栄典制度の根幹をなしています。
叙勲は、原則として毎年2回、「春の叙勲」と「秋の叙勲」として行われ、テレビや新聞などでそのニュースを見聞きする機会も多いでしょう。
この制度には「旭日章」や「瑞宝章」といった異なる種類の勲章があり、それぞれ授与される対象者の功績の内容によって区別されています。
「叙勲」の詳細
叙勲の主な種類:「旭日章」と「瑞宝章」の違い
日本の叙勲制度には様々な勲章がありますが、春秋叙勲において中心となるのは「旭日章(きょくじつしょう)」と「瑞宝章(ずいほうしょう)」の二つです。
これらは、授与される功績の性質によって明確に区別されています。
旭日章(きょくじつしょう)
「功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方」に授与されます。
具体的には、民間企業の経営者として経済社会の発展に大きく寄与した方、国会議員や地方公共団体の首長として顕著な実績を挙げた方、あるいは社会の様々な分野でめざましい功績を残した方などが対象となります。
功績の「華々しさ」や「社会的な影響力」が評価される勲章と言えます。
旭日章には、上から「旭日大綬章(きょくじつだいじゅしょう)」、「旭日重光章(きょくじつじゅうこうしょう)」、「旭日中綬章(きょくじつちゅうじゅしょう)」、「旭日小綬章(きょくじつしょうじゅしょう)」、「旭日双光章(きょくじつそうこうしょう)」、「旭日単光章(きょくじつたんこうしょう)」の6つの等級があります。
瑞宝章(ずいほうしょう)
「公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方」に授与されます。
こちらは、主に公務員(国家公務員や地方公務員)や、公共性の高い業務(例えば、学校の教員、警察官、消防士、自衛官、民生委員、公共交通機関の職員など)に長期間従事し、その職務を誠実に果たしてこられた方が対象です。
「顕著な功績」というよりも、「長年の地道な功労」が評価される勲章です。
瑞宝章も旭日章と同様に、「瑞宝大綬章」、「瑞宝重光章」、「瑞宝中綬章」、「瑞宝小綬章」、「瑞宝双光章」、「瑞宝単光章」の6等級に分かれています。
叙勲はいつ、誰がもらえるのか?
叙勲にはいくつかの区分がありますが、最も一般的なのが「春秋叙勲」です。
-
春の叙勲: 毎年4月29日(昭和の日)に発令されます。
-
秋の叙勲: 毎年11月3日(文化の日)に発令されます。
毎回、約4,000名の方が受章されます。
受章の対象となるのは、原則として70歳以上の方です。
ただし、精神的・肉体的に多大な労苦を伴う業務や、人目につきにくい分野で長年尽力された方については、55歳以上で対象となる場合があります(例:危険業務従事者叙勲など)。
選考は、各省庁や都道府県から推薦された候補者を内閣府で審査し、閣議での決定を経て、最終的に天皇陛下の御裁可(ごさいか)によって決定されます。
また、一般の人が「この人は叙勲にふさわしい」と推薦できる「一般推薦制度」も設けられています(ただし、本人や二親等以内の親族は推薦できません)。
叙勲の伝達式と拝謁
叙勲が決定すると、勲章と勲記(くんき:功績を記した証書)が授与されます。
大綬章や重光章など上位の勲章の受章者は、皇居の宮殿「松風の間」において、内閣総理大臣から勲章が伝達された後、宮殿「豊明殿」で天皇陛下に拝謁(はいえつ:お会いすること)する栄誉にあずかります。
この際、配偶者も同伴することが許されています。
中綬章以下の受章者については、各省庁の大臣や都道府県知事から伝達されます。
叙勲の辞退
叙勲は国家からの栄誉ですが、個人の信念や価値観、あるいは健康上の理由などから辞退する人もいます。
例えば、作家の大江健三郎氏は、1994年にノーベル文学賞を受賞しましたが、「民主主義に勝る権威と価値観を認めない」として、文化勲章の受章を辞退したことは有名です。
また、女優の杉村春子氏も文化勲章を辞退しています。
叙勲を受けるかどうかは、最終的には本人の意思に委ねられています。
参考動画
まとめ
叙勲は、長年にわたって国や社会のために尽くしてきた人々の功労に対し、国家が最高の栄誉をもって称える厳粛な制度です。
「旭日章」は社会的な華々しい功績に、「瑞宝章」は長年の地道な公務への功労に、それぞれ光を当てるものです。
春と秋に発表される受章者のニュースは、私たちが暮らす社会が、目立つ分野だけでなく、目立たない分野で尽力する多くの人々によって支えられていることを改めて気付かせてくれる機会でもあります。
関連トピック
褒章(ほうしょう):
叙勲と似ていますが、褒章は特定の分野(人命救助、社会奉仕、学術・芸術など)で優れた行いや業績のあった方に授与されるものです。
「紅綬褒章」「緑綬褒章」「黄綬褒章」「紫綬褒章」「藍綬褒章」などの種類があります。
文化勲章(ぶんかくんしょう):
文化の発達に関して、特に顕著な功績のあった方に授与される最上位の勲章です。
叙勲とは別枠で、毎年11月3日の文化の日に発令されます。
危険業務従事者叙勲:
警察官、消防士、自衛官、刑務官など、危険性の高い業務に長年従事した55歳以上の方を対象とする叙勲で、春秋叙勲と同日に発令されます。
皇居(こうきょ):
天皇陛下の御所であり、叙勲の伝達式や拝謁が行われる宮殿がある場所です。
受章者にとっては、生涯忘れられない栄誉の舞台となります。
関連資料
『叙勲・褒章受章者のしおり』:
内閣府が発行している公式ガイドブック。
受章が決まった後の手続きや、伝達式・拝謁の際の服装(モーニングコートや色留袖など)、心構えなどが詳しく記されています。
叙勲額(じょくんがく):
授与された勲章と勲記を一緒に飾るための専用の額縁です。
受章の栄誉を形として残すため、多くの受章者が買い求めます。
『叙勲・褒章 記録集(紳士録)』:
受章者の氏名や功績をまとめた記念の書籍。
受章祝賀会での記念品としてや、後世に栄誉を伝えるために利用されます。