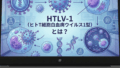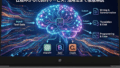日銀ETF含み益とは?仕組みから「30兆円超」の埋蔵金、出口戦略まで徹底解説
「日銀ETF含み益」の概要
「日銀ETF含み益」とは、日本銀行が金融緩和政策の一環として買い入れたETF(上場投資信託)の現在の市場価値(時価)が、購入時の価格(簿価)を上回っている状態のことを指します。
アベノミクス以降の長期的な株価上昇により、この含み益は膨れ上がり、2024年には一時30兆円を超える規模に達し、過去最高を記録しました。
この巨額の利益は「埋蔵金」として注目される一方、将来的にどのように現金化(出口戦略)するかという難しい課題も孕んでいます。
「日銀ETF含み益」の詳細
日銀がETFを買い入れた背景
日銀によるETF買い入れは、2010年に始まり、2013年からの黒田総裁による「異次元緩和」でその規模が大幅に拡大しました。
目的は、市場に資金を供給して株価を下支えし、投資家心理を改善させることで「資産効果」を生み、景気を浮揚させることにありました。
これにより、日銀は日本株の最大の保有者の一つ、「実質的な大株主」となりました。
含み益が拡大した理由と現状
日銀は、株価が比較的安い時期から大量にETFを購入し続けました。
その後、日経平均株価がバブル後の最高値を更新するなど市場が好調に推移したため、保有するETFの時価評価額が急増しました。
2024年3月末時点での保有残高(時価)は約74兆円、含み益は約37兆円にも上ると報じられています。
これは、日本の国家予算の約3分の1に匹敵する規模です。
損益分岐点とリスク
日銀にとって、保有ETFが「含み損」に転じる分岐点は、日経平均株価で約2万円程度と推計されています。
現在の株価水準(3万円台後半〜4万円)から見れば十分な余裕がありますが、もし世界的な金融危機などで株価が暴落すれば、日銀の財務健全性が損なわれるリスクがあります。
出口戦略の難しさ
最大の問題は、この膨大なETFをどう処理するかという「出口戦略」です。
市場で売却すれば、供給過多となり株価が大暴落する恐れがあります。
そのため、時間をかけて少しずつ売却する、あるいは個人投資家に譲渡するなど、様々な案が議論されていますが、決定的な解決策はまだ見つかっていません。
2024年3月に日銀はETFの新規買い入れ終了を決定しましたが、保有分の処理については先送りにされたままです。
「日銀ETF含み益」の参考動画
まとめ
日銀のETF含み益は、アベノミクスの遺産とも言える巨額の資産ですが、同時に日本経済にとっての潜在的なリスク要因でもあります。
「埋蔵金」として活用を期待する声もありますが、不用意に動かせば市場を壊しかねないため、その扱いは極めて慎重にならざるを得ません。
私たちにとっては、日銀の動向が間接的に自分の資産(年金や保有株)に影響を与えるため、今後の「出口戦略」に関する議論を注視していく必要があります。
関連トピック
異次元緩和(黒田東彦総裁の下で実施された、大規模な金融緩和政策。ETF買い入れもその柱の一つ)
出口戦略(中央銀行が金融緩和政策を終了し、平時の状態に戻していくプロセスのこと)
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人。日銀と並ぶ日本株の巨大保有主体)
TOPIX(東証株価指数。日銀が買い入れ対象としていた主要な株価指数の一つ)
関連資料
『日銀ETF問題―《最大株主化》の実態とその出口戦略』(平山賢一 著 / 中央経済社)
『新・金融政策入門』(湯本雅士 著 / 岩波書店)
『改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい』(朝倉智也 著 / ダイヤモンド社)
日銀のETF保有について解説する 日銀ETF保有解説 動画です。この動画は、日銀がなぜETFを保有し始めたのか、その金額の推移、そして今後の課題となる出口戦略についてわかりやすく解説しています。