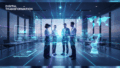空飛ぶクルマとは?未来の移動手段「eVTOL」の概要、実用化の課題、関連トピックまで徹底解説!
「空飛ぶクルマ」の概要
「空飛ぶクルマ」とは、文字通り空を移動する個人の乗り物を指す通称です。
近年では、特に「eVTOL(イーブイトール)」と呼ばれる電動で垂直に離着陸できる航空機が、この「空飛ぶクルマ」の主流として開発が進められています。
ドローンの技術を応用し、多数のプロペラを使って飛行するのが特徴です。
都市部の渋滞解消や、災害時の迅速な移動、過疎地へのアクセス改善など、次世代の移動手段として大きな期待が寄せられています。
世界中の多くの企業やスタートアップが開発競争を繰り広げており、実用化に向けた動きが活発化しています。
「空飛ぶクルマ」の詳細
「空飛ぶクルマ」の概要として、現在最も注目されているのがeVTOL(イーブイトール)と呼ばれる機体です。
これは「Electric Vertical Take-Off and Landing」の略で、「電動垂直離着陸機」と訳されます。
従来の飛行機のように離陸のための滑走路を必要とせず、またヘリコプターのように広いヘリポートがなくても、都市部のビルの屋上など限られたスペースから垂直に離着陸できるのが最大の強みです。
なぜ今、「空飛ぶクルマ」が注目されているのか?
空飛ぶクルマがSFの世界の乗り物から、現実のプロジェクトとして急速に発展してきた背景には、いくつかの重要な技術革新があります。
第一に、ドローン技術の飛躍的な発展です。
多数の小さなローター(プロペラ)をコンピューターで個別に精密制御し、安定した飛行を実現する「分散型電気推進(DEP)」という技術が確立されました。
これにより、従来の航空機よりも複雑な飛行制御が可能になったのです。
第二に、バッテリー技術の進歩です。
電気自動車(EV)の普及にも見られるように、高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーが実用化され、電動での飛行が現実的なものとなりました。
電動化により、従来のエンジン機に比べて騒音が大幅に低減されることも、都市部での運用において大きなメリットとされています。
第三に、ヘリコプターと比較した際の潜在的なメリットです。
ヘリコプターは構造が複雑で、操縦が難しく、運用コストやメンテナンスコストが非常に高いという課題がありました。
eVTOLは、構造が比較的シンプルであるため、機体価格や運用コストを将来的に大幅に下げられる可能性があると期待されています。
空飛ぶクルマ(eVTOL)の主な仕組み
eVTOLには、その飛行方式によっていくつかのタイプがあります。
最もシンプルなのは、ドローンのように多数のプロペラ(ローター)の回転数を変えるだけですべての飛行(上昇、下降、前進、回転)を行う「マルチローター型」です。
構造が簡単ですが、水平飛行時のエネルギー効率があまり良くないため、航続距離が短くなる傾向があります。
一方、垂直離陸時はローターを使い、水平飛行に移ると固定された翼で揚力を得て、別の推進用プロペラで前進する「リフト&クルーズ型」もあります。
さらに、離着陸時はプロペラを上向きにし、水平飛行時はプロペラごと前方に傾けて飛行機のように飛ぶ「ティルトローター型(またはティルトウィング型)」も開発されています。
これらのタイプは、マルチローター型よりも高速で長距離の飛行が可能とされています。
動力源は現在、主にバッテリーですが、航続距離をさらに伸ばすために、ガスタービンで発電してモーターを回すハイブリッド型や、水素燃料電池の研究も進められています。
実用化に向けた多くの課題
未来の移動手段として期待される「空飛ぶクルマ」ですが、その実用化と普及に向けては、乗り越えるべき多くの課題が存在します。
技術的な課題としては、まず第一にバッテリーの性能向上が挙げられます。
現在のバッテリー技術では、人を乗せて飛行できる時間は30分から1時間程度、航続距離も数十キロから100km程度に限られる機体が多く、用途が限定されます。
より長く、より遠くへ飛ぶためには、バッテリーのさらなる高密度化と軽量化が不可欠です。
また、突風や豪雨といった悪天候時でも安全に飛行できる機体の信頼性や、万が一飛行中に動力が停止した場合の安全対策(パラシュートなど)も重要です。
法整備の課題も非常に大きいです。
まず、機体そのものの安全性を証明するための基準(耐空証明)を新たに策定する必要があります。
次に、誰が操縦するのかという「免許制度」も必要です。
当初はパイロットによる操縦が想定されていますが、将来的には自動運転や遠隔操縦も見据えた新しいルール作りが求められます。
さらに、空の交通ルール(運航管理システム)の構築も急務です。
多くの機体が都市部の上空を安全に飛び交うためには、管制システムや機体同士が衝突しないための高度な技術が必要です。
社会受容性の課題も無視できません。
多くの人々が、自分の家の真上を未知の乗り物が頻繁に飛ぶことに対して、騒音やプライバシーの懸念、そして何よりも「もし墜落したら」という不安を感じる可能性があります。
ヘリコプターよりは静かとはいえ、無音ではありません。
こうした社会的なコンセンサスを得るための取り組みも重要です。
インフラとコストの課題もあります。
空飛ぶクルマが離着陸するための中継拠点となる「バーティポート(Vertiport)」を、都市部のどこにどれだけ整備できるか。
その建設コストや、機体本体の価格、そして実用化された際の「運賃」が、タクシーや電車と比べてどれだけ高額になるのかも、普及の鍵を握っています。
日本と世界の開発動向
「空飛ぶクルマ」の開発競争は、世界レベルで激化しています。
世界では、アメリカのJoby Aviation(ジョビー・アビエーション)やWisk Aero、ドイツのVolocopter(ボロコプター)、中国のEHang(イーハン)といったスタートアップ企業が開発をリードしています。
これらの企業は巨額の資金調達に成功し、すでに数多くの試験飛行を繰り返しています。
特に中国のEHangは、世界に先駆けて商用運航の型式証明を取得するなど、実用化で先行する動きも見られます。
日本国内では、SkyDrive(スカイドライブ)社が開発の筆頭とされています。
同社は、2025年に開催される大阪・関西万博において、会場と大阪市内を結ぶ「エアタクシー」サービスとして、実際に人を乗せて運航することを計画しています。
この大阪・関西万博は、日本において「空飛ぶクルマ」が多くの人の目に触れる最初の大きな舞台となり、社会実装に向けた重要なマイルストーンとして大きな注目を集めています。
参考動画
まとめ
「空飛ぶクルマ(eVTOL)」は、単なるSF映画の中のガジェットではなく、私たちの移動のあり方を根本から変える可能性を秘めた、次世代モビリティ革命の主役です。
都市部の深刻な交通渋滞から解放され、移動時間が劇的に短縮される未来や、災害時に迅速に被災地へ到達できる救急医療、過疎地と都市部を結ぶ新しい交通網など、その社会的インパクトは計り知れません。
もちろん、本記事で詳述したように、技術、法律、コスト、そして社会的な理解など、解決すべきハードルは高く、決して簡単な道のりではありません。
しかし、2025年の大阪・関西万博での商用運航計画を一つのマイルストーンとして、世界中で開発と実証実験が急速に進んでいます。
今後、空のインフラがどのように整備され、「空飛ぶクルマ」が私たちの日常の風景にどのように溶け込んでいくのか。
私たちは、この新しい移動手段がもたらす利便性と、安全性の確保という両方の側面を注視しながら、新しい時代を迎える準備をしていく必要があるでしょう。
空の移動革命は、もうすでに始まっています。
関連トピック
eVTOL(イーブイトール): 「Electric Vertical Take-Off and Landing」の略です。日本語では「電動垂直離着陸機」と呼ばれ、現在の「空飛ぶクルマ」開発の主流となっている機体カテゴリそのものを指す技術用語です。
MaaS(マース): 「Mobility as a Service」の略で、直訳すると「サービスとしてのモビリティ」です。電車、バス、タクシー、シェアサイクルなど、あらゆる交通手段をITプラットフォーム上で統合し、検索から予約、決済までをシームレスに行えるようにする概念です。空飛ぶクルマも将来的にはこのMaaSの重要な構成要素の一つとなると考えられています。
ドローン(UAV): 「Unmanned Aerial Vehicle」の略で、無人航空機のことです。ドローンで培われた多数のモーターを精密に制御する技術や、高性能バッテリー技術が、人を乗せるeVTOL(空飛ぶクルマ)の発展に大きく貢献しています。物流ドローンによる荷物配送は、空飛ぶクルマよりも一足先に社会実装が進むと見られています。
エアタクシー: 空飛ぶクルマ(eVTOL)を活用して提供されると想定されている、オンデマンド型の航空輸送サービスのことです。都市部や空港間の短距離移動を、ヘリコプターよりも手軽な料金で提供することが目指されています。
関連資料
書籍『空飛ぶクルマの時代 – eVTOLが開く、新たな空の産業革命』(日経BP): 空飛ぶクルマの技術的な側面や、国内外の主要な開発企業の動向、法整備や社会実装に向けた課題などを網羅的に解説した一冊です。
書籍『eVTOL(空飛ぶクルマ)の技術開発と将来展望』(各種技術情報協会など): より専門的な技術動向、例えばバッテリー技術、モーター制御、運航管理システム(UTM)などについて、専門家向けに詳細に解説されている資料やレポートが多数発行されています。
各社開発機体の模型: 日本のSkyDrive社や、海外のVolocopter社、Joby Aviation社などは、自社で開発中の機体のスケールモデル(模型)をイベントで展示したり、関連グッズとして販売したりしていることがあります。