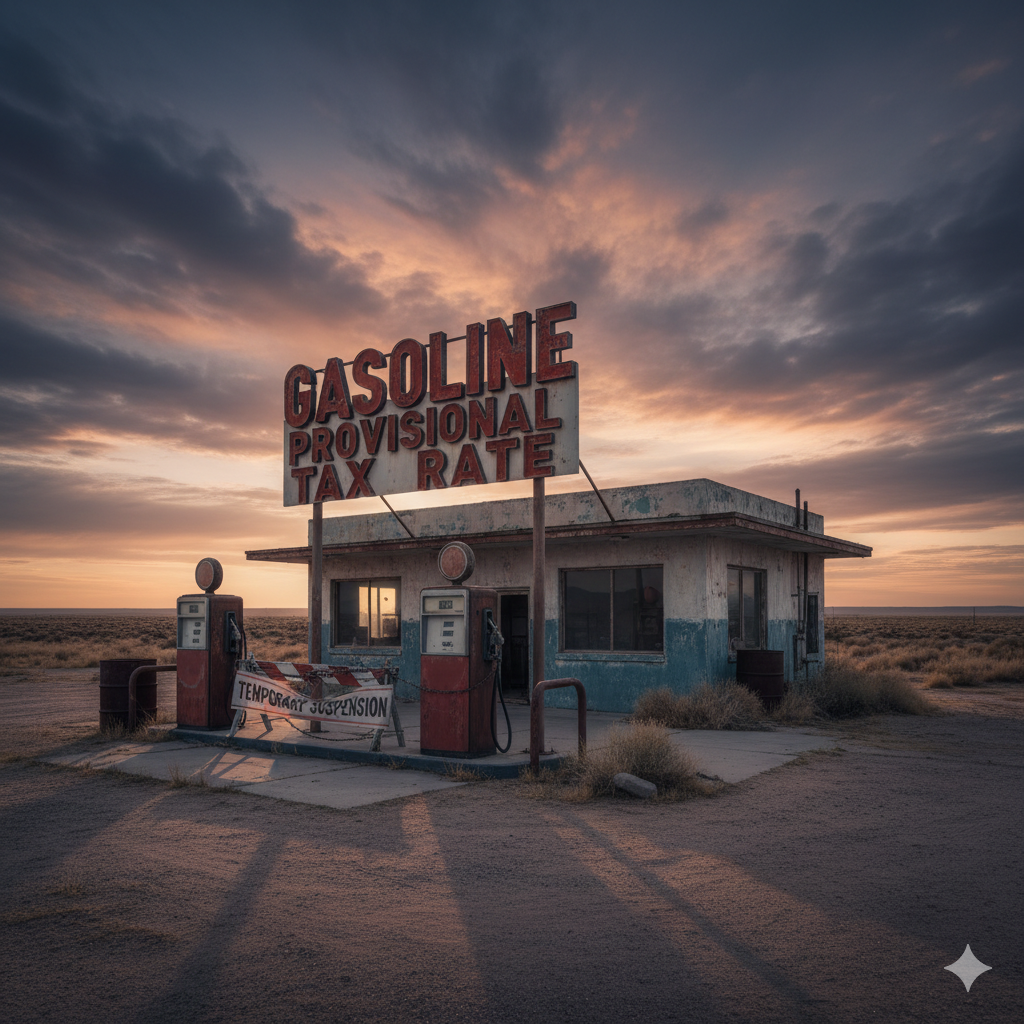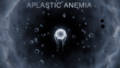50年の歴史に終止符?ガソリン暫定税率廃止へ!仕組みと今後の影響を徹底解説
「ガソリン暫定税率」の概要
ガソリン暫定税率とは、ガソリン価格に含まれる税金の一部です。
具体的には、ガソリン税(揮発油税と地方揮発油税)のうち、本来の税率(本則税率)に上乗せされている部分を指します。
現在のガソリン税は1リットルあたり53.8円です。
このうち、本則税率は28.7円、暫定税率分は25.1円となっています。
この暫定税率は、1974年に道路整備の財源を確保するという目的で、「一時的な措置」として導入されました。
しかし、導入後も繰り返し延長され、約50年間にわたり事実上の恒久的な税金として続いてきました。
「ガソリン暫定税率」の詳細
ガソリン暫定税率の仕組みとこれまでの経緯について、詳しく解説します。
50年間続いた「暫定」措置の歴史
ガソリン暫定税率は、1974年の田中角栄内閣時代に、道路整備の財源不足を補うために導入されました。
当初は「一時的」な措置と説明されていましたが、財源確保の必要性を理由に何度も延長が繰り返されてきました。
2008年には、この暫定税率の期限切れをめぐり国会が紛糾し、「ガソリン国会」と呼ばれました。
この時、一時的に暫定税率が失効し、ガソリン価格が1リットルあたり約25円値下がりしましたが、わずか1ヶ月で与党(当時)の再可決により復活した経緯があります。
道路特定財源から一般財源へ
もともと暫定税率を含むガソリン税の税収は、道路の建設や整備にしか使えない「道路特定財源」とされていました。
しかし、2009年にこの道路特定財源制度は廃止されました。
これにより、税収は国や地方の一般財源(使途を特定しない予算)として使われるようになりました。
「道路整備」という当初の目的が薄れたにもかかわらず、税率は「当分の間税率」と名前を変える形で維持され、課税が続いてきました。
ガソリン価格高騰とトリガー条項
近年、世界的なエネルギー価格の上昇により、ガソリン価格が高騰しています。
実は、こうした事態に備えて、2010年に「トリガー条項」という仕組みが導入されています。
これは、ガソリンの全国平均小売価格が3ヶ月連続で1リットル160円を超えた場合、暫定税率分(25.1円)の課税を自動的に停止する制度です。
しかし、このトリガー条項は、2011年の東日本大震災の復興財源を確保するという理由で凍結されてしまいました。
現在もこの凍結は解除されておらず、近年のガソリン価格高騰時にも発動されることはありませんでした。
そのため、政府は暫定税率の停止(トリガー条項の発動)ではなく、「燃料油価格激変緩和措置」(ガソリン補助金)によって価格高騰に対応してきました。
「二重課税」問題とは
ガソリン価格の構成も長年問題視されています。
ガソリンスタンドで支払う価格には、ガソリン本体価格、ガソリン税(暫定税率含む)、石油石炭税などが含まれています。
そして、これらの合計金額に対して、さらに10%の消費税が課されています。
つまり、ガソリン税という「税金」に対しても消費税がかかっている状態であり、これが「二重課税」であるとの批判が根強くあります。
暫定税率廃止に向けた最新の動き
物価高対策が喫緊の課題となる中、2025年秋、ガソリン暫定税率の廃止に向けた動きが急速に進展しました。
高市早苗総理が打ち出した物価高対策の一環として、与野党間での協議が本格化しました。
当初、野党は2025年11月からの早期廃止を求めていましたが、与党内やガソリンスタンド業界からは準備期間が必要との声もありました。
最終的に、与野党6党の実務者は、2025年12月31日をもってガソリン暫定税率を廃止することで正式に合意しました。
参考動画
まとめ
約半世紀にわたり続いてきたガソリン暫定税率の廃止は、私たちの生活に大きな影響を与えそうです。
暫定税率(25.1円)がなくなれば、ガソリン価格は単純計算でその分だけ値下がりすることになります。
ただし、注意点もあります。
政府は現在、ガソリン価格高騰対策として1リットルあたり10円程度の補助金を出しています。
暫定税率の廃止に伴い、この補助金制度がどうなるか(廃止または見直し)が焦点となります。
もし補助金も同時に廃止されれば、実質的な値下げ幅は「25.1円 – 10円=約15円」程度になる可能性も指摘されています。
とはいえ、家計の負担軽減につながることは間違いありません。
ある試算によれば、暫定税率の廃止により、自動車を所有する家庭では年間で約1万円程度の燃料費削減につながると見られています。
また、ガソリン価格の低下は、物流コストの削減を通じて、幅広い品物の物価上昇を抑制する効果も期待されます。
一方で、国としては年間1兆円を超える税収が失われることになり、その代替財源をどう確保するかが今後の大きな課題となります。
私たちの生活に直結するガソリン価格の動向と、それに伴う税制の変更について、今後も注目していく必要があります。
関連トピック
トリガー条項
ガソリン価格が一定水準(3ヶ月連続160円/L超)に達した場合に、ガソリン税の暫定税率分(25.1円)の課税を一時的に停止する仕組みです。
2011年から凍結されています。
道路特定財源
かつてガソリン税などの税収の使い道を道路整備に限定していた制度です。
2009年に廃止され、税収は一般財源化されました。
ガソリン補助金(燃料油価格激変緩和措置)
トリガー条項とは別に、近年の原油価格高騰を受けて政府が石油元売会社に支給している補助金です。
これにより、ガソリン小売価格の上昇が抑えられています。
二重課税問題
ガソリン税という税金が課された後の価格に対して、さらに消費税が課されることを指す問題です。
関連資料
『クルマにかかる税金』
自動車税制全般について解説した書籍。
ガソリン税や自動車重量税など、複雑な税金の仕組みを理解するのに役立ちます。
『日本のエネルギー政策』
ガソリン価格に影響を与える原油価格や、国のエネルギー戦略について学べる専門書や白書です。
『ガソリンスタンド経営』関連雑誌
業界の視点から、暫定税率廃止が現場(ガソリンスタンド)にどのような影響を与えるか、価格設定の裏側などを知ることができます。