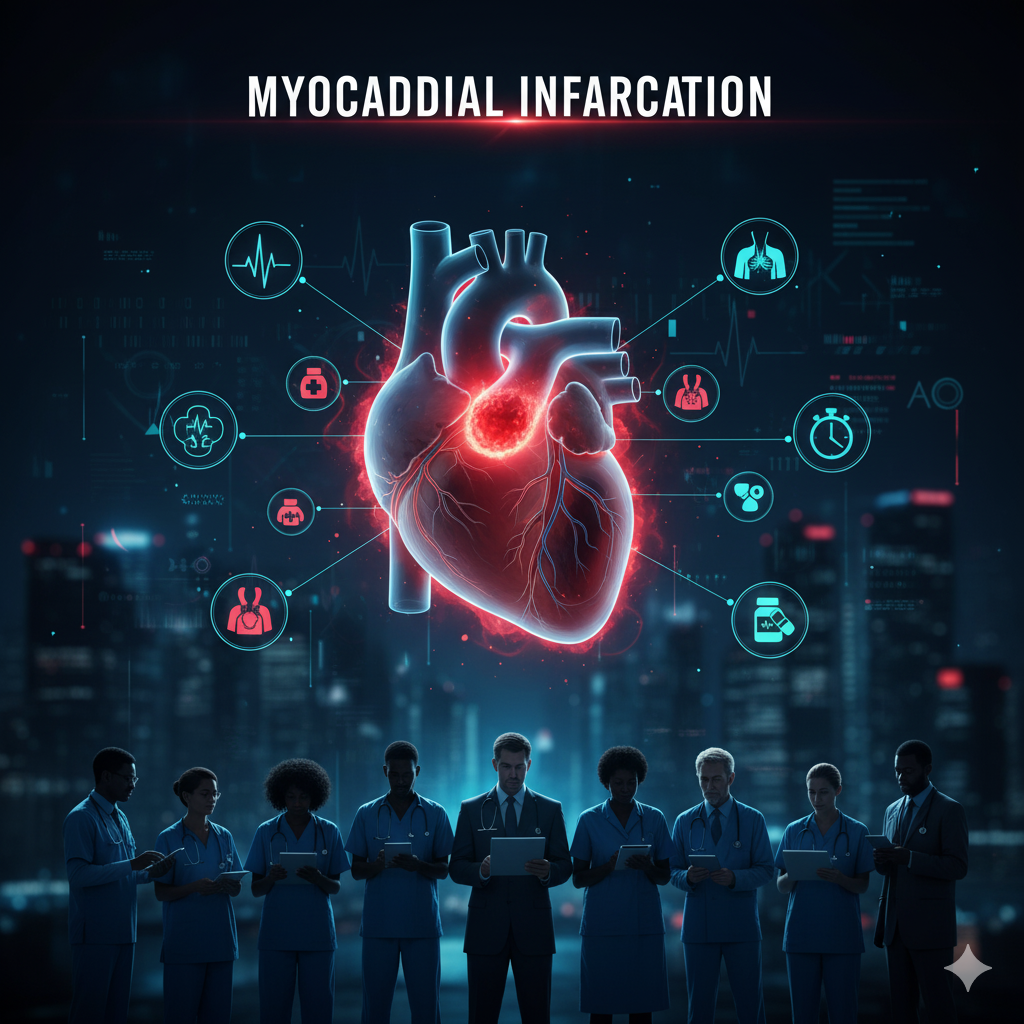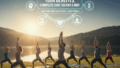突然死リスクを回避!「心筋梗塞」の症状、原因、治療、予防法までを徹底解説
「心筋梗塞」の概要
心筋梗塞(しんきんこうそく)とは、心臓の筋肉(心筋)に血液を送る冠動脈(かんどうみゃく)が詰まってしまい、心筋が酸素不足や栄養不足に陥り、壊死(えし)してしまう病気です。
これは虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)の一つであり、突然の激しい胸の痛みや圧迫感などを引き起こし、命に関わる非常に危険な状態です。
迅速な治療が求められる救急疾患であり、発症後の対応がその後の経過に大きく影響します。
「心筋梗塞」の詳細
心筋梗塞の最も一般的な原因は、動脈硬化(どうみゃくこうか)です。
動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールなどのプラーク(粥腫:じゅくしゅ)が溜まり、血管が硬く、狭くなる状態を指します。
このプラークが何らかのきっかけで破れると、その部分を修復しようと血小板が集まり、血栓(けっせん)と呼ばれる血の塊が作られます。
この血栓が冠動脈を完全に塞いでしまうと、その先の心筋に血液が流れなくなり、心筋梗塞が発症します。
心筋梗塞の危険因子
心筋梗塞を引き起こす動脈硬化には、いくつかの危険因子が関与しています。
高血圧、脂質異常症(高コレステロール血症など)、糖尿病といった生活習慣病は、動脈硬化を強力に進行させます。
喫煙も、血管を収縮させ、動脈硬化を促進する大きなリスク要因です。
肥満、特に内臓脂肪型肥満、運動不足、ストレス過多な生活も心筋梗塞のリスクを高めます。
また、加齢や家族歴(遺伝的要因)も関わっているとされています。
特徴的な症状と前兆
心筋梗塞の典型的な症状は、突然の激しい胸の痛みです。
「胸を締め付けられるよう」「圧迫されるよう」「焼けるよう」などと表現されることが多いです。
この痛みは数分ではなく、15分以上、時には数時間続くこともあります。
痛みは胸だけでなく、左肩、腕、あご、背中などに広がる(放散痛)こともあります。
冷や汗、吐き気、嘔吐、呼吸困難、めまい、失神などを伴う場合も少なくありません。
ただし、高齢者や糖尿病患者では、典型的な胸痛を感じにくく、「なんとなく体調が悪い」「胃が痛い」といった非典型的な症状しか現れないこともあり、注意が必要です(無痛性心筋梗塞)。
発症する前に、「狭心症(きょうしんしょう)」と呼ばれる、一時的な胸の痛や圧迫感(数分で治まる)を経験している人もいます。
診断と治療法
心筋梗塞が疑われる場合、迅速な診断と治療が不可欠です。
病院では、まず心電図検査が行われ、特徴的な波形の変化(ST上昇など)を確認します。
同時に、血液検査で心筋が壊死した際に血中に放出される酵素(トロポニンなど)の値を測定します。
心臓超音波(エコー)検査で、心臓の壁の動きが悪くなっていないかを確認することもあります。
最終的な診断と詰まっている場所の特定のために、冠動脈CT検査や、心臓カテーテル検査(冠動脈造影)が行われることもあります。
治療は、一刻も早く詰まった血管を再開通させ、心筋への血流を回復させることが最優先されます。
主な治療法には、カテーテルを用いて血栓を吸引したり、バルーン(風船)で血管を広げたり、ステントという金属の網を留置する「カテーテル治療(PCI)」があります。
また、血栓を溶かす薬剤(血栓溶解薬)を点滴で投与する方法や、緊急で「冠動脈バイパス手術(CABG)」が行われる場合もあります。
治療後は、心臓の機能回復と再発予防のために、心臓リハビリテーションが行われます。
薬物療法も継続的に必要となり、血液をサラサラにする薬(抗血小板薬)や、コレステロールを下げる薬(スタチンなど)、血圧を下げる薬などが処方されます。
まとめ:心筋梗塞の予防と対策
心筋梗塞は、発症すると命に関わる重大な病気ですが、その原因の多くは生活習慣と深く関連しています。
動脈硬化を予防することが、心筋梗塞の最大の予防策となります。
高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を適切に管理・治療することが非常に重要です。
禁煙、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理など、日々の生活習慣を見直すことが求められます。
もし突然の激しい胸痛や、これまで経験したことのないような圧迫感を感じた場合は、ためらわずに救急車(119番)を呼んでください。
「少し休めば治るかも」という自己判断が、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。
自分や家族の命を守るために、心筋梗塞に関する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療、そして何よりも予防に努めることが大切です。
関連トピック
狭心症(きょうしんしょう): 心筋梗塞と同様に冠動脈が狭くなることで、一時的に心筋への血流が不足する状態です。胸の痛みや圧迫感が数分続いて治まるのが特徴で、心筋梗塞の前兆となることがあります。
動脈硬化(どうみゃくこうか): 血管が硬く、狭くなる状態です。心筋梗塞や脳梗塞の根本的な原因となります。コレステロールや中性脂肪、高血圧、喫煙などが原因で進行します。
カテーテル治療(PCI): 心筋梗塞の主要な治療法の一つです。手首や足の付け根の血管からカテーテルという細い管を挿入し、詰まった冠動脈まで進め、風船(バルーン)やステント(金属の網)を使って血管を広げます。
バイパス手術(CABG): 冠動脈の詰まった部分を迂回する新しい血管(バイパス)を作成する外科手術です。カテーテル治療が困難な場合や、複数の血管が詰まっている場合に行われることがあります。
生活習慣病: 高血圧、脂質異常症、糖尿病など、食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症や進行に深く関わる疾患群です。これらは心筋梗塞の強力な危険因子です。
関連資料
心筋梗塞・狭心症の人の安心ごはん: 食事療法に焦点を当てた書籍です。塩分や脂質を抑えつつ、美味しく続けられるレシピを紹介し、再発予防をサポートします。
改訂版 心筋梗塞・狭心症がよくわかる本: 専門医が病気のメカニズム、検査、治療法(カテーテル治療やバイパス手術)、リハビリ、予防法までを分かりやすく解説した入門書です。
スマートウォッチ(心電図機能付き): 近年、一部のスマートウォッチには心電図(ECG)を簡易的に測定できる機能が搭載されています。不整脈の早期発見などに役立つ可能性があり、健康管理のツールとして注目されています。
家庭用血圧計: 心筋梗塞のリスク管理において、日々の血圧測定は非常に重要です。家庭用血圧計で定期的に血圧をチェックし、高血圧の管理に役立てることが推奨されます。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。