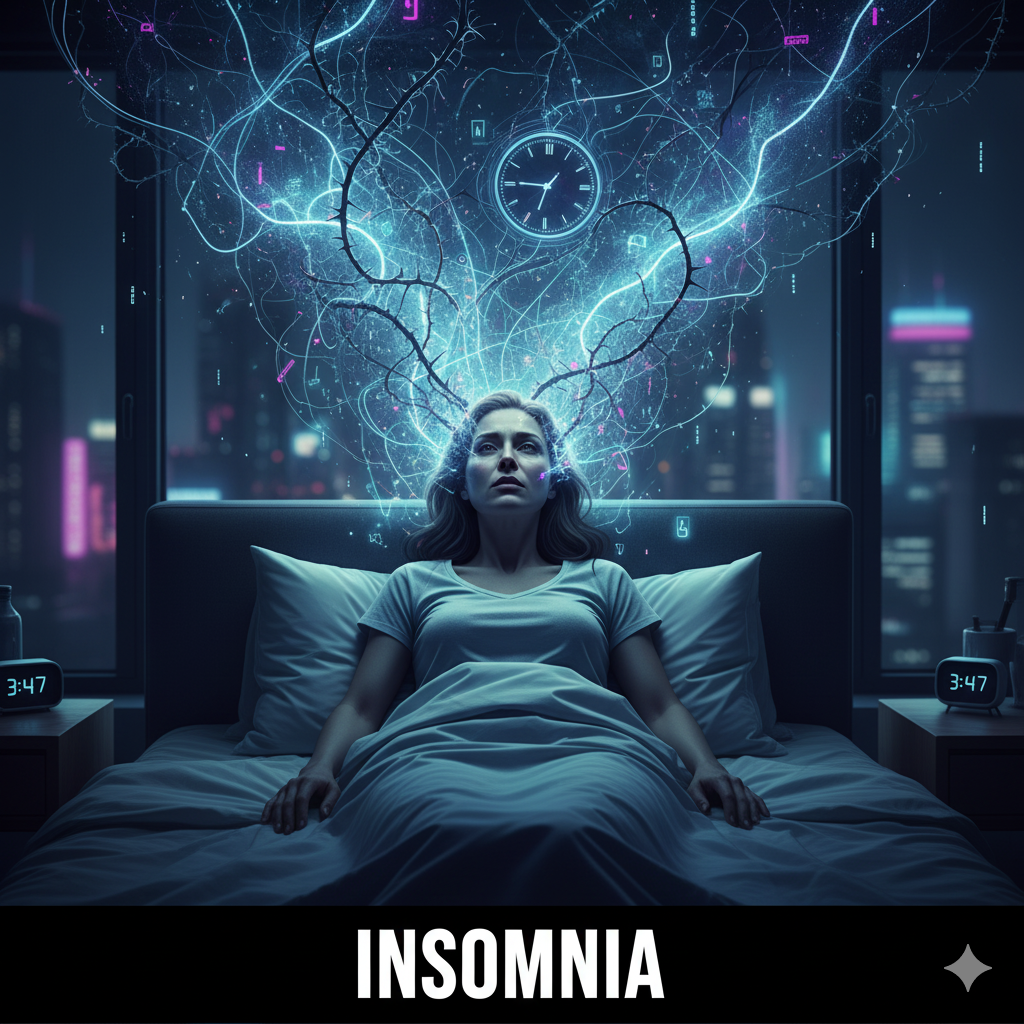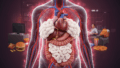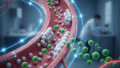不眠症とは?眠れない4つのタイプと原因、今日から始める睡眠改善策を徹底解説
「不眠症」の概要
不眠症とは、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるといった睡眠の問題が1ヶ月以上続き、日中の生活に支障が出ている状態を指します。
単なる一時的な寝不足とは異なり、倦怠感、集中力の低下、気分の落ち込みなどを伴う場合は「不眠症」という病気として扱われることがあります。
日本人の約5人に1人が睡眠に関する悩みを抱えていると言われており、非常に身近な問題です。
「不眠症」の詳細情報
不眠症の4つの主なタイプ
不眠症は、その症状によって主に4つのタイプに分類されます。
これらは一つだけ起こることもあれば、複数が重なって現れることもあります。
1. 入眠障害
布団に入ってもなかなか寝付けないタイプです。
一般的に、眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる状態が目安とされます。
不安や心配事、ストレスなどが原因で起こりやすいとされています。
2. 中途覚醒
睡眠中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けなくなるタイプです。
加齢とともに増える傾向があり、頻尿や身体の痛み、睡眠時無呼吸症候群などが原因の場合もあります。
3. 早朝覚醒
予定していた起床時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができないタイプです。
体内時計のリズムが前にずれてしまうことが原因で、高齢者やうつ病の初期症状として見られることがあります。
4. 熟眠障害
睡眠時間は十分に取れているはずなのに、眠りが浅く、「ぐっすり眠った」という満足感が得られないタイプです。
睡眠の質が低下しており、睡眠時無呼吸症候群や、寝室の環境(騒音、光など)が影響している可能性があります。
不眠症の主な原因
不眠症の原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることが多いです。
-
心理的・精神的要因: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安などのストレスが最も多い原因です。また、うつ病や不安障害などの精神疾患の症状として不眠が現れることもあります。
-
身体的要因: 年齢による睡眠の変化(眠りが浅くなる、中途覚醒が増える)のほか、ぜんそくの咳、アレルギーのかゆみ、関節リウマチの痛み、頻尿などが睡眠を妨げることがあります。
-
環境的要因: 寝室の騒音や光、不適切な温度や湿度、枕やマットレスが合わないといった睡眠環境の悪さも原因となります。
-
生活習慣的要因: 不規則な生活リズム、カフェインの過剰摂取、就寝前のアルコール(寝酒)や喫煙、夜遅くまでのスマートフォンやPCの使用(ブルーライトの影響)などが体内時計を乱し、不眠を引き起こします。
不眠症を放置するリスク
不眠症を「ただ眠れないだけ」と放置すると、日中の深刻な眠気や倦怠感、集中力・記憶力の低下を引き起こし、仕事の能率低下や事故の原因にもなり得ます。
また、慢性的な不眠は高血圧や糖尿病といった生活習慣病のリスクを高めるほか、うつ病の発症や悪化に深く関わっていることが知られています。
ある試算では、睡眠不足による日本の経済損失は年間十数兆円にのぼるとも言われています。
自分でできる不眠症対策(睡眠衛生の改善)
不眠症の改善には、まず生活習慣を見直す「睡眠衛生」の改善が重要です。
-
起床時間を一定にする: 休日でも平日と同じ時間に起きることで、体内時計のリズムが整いやすくなります。
-
朝日を浴びる: 起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。これが体内時計のリセットボタンとなります。
-
適度な運動: 日中の適度な運動(ウォーキングなど)は、夜の寝つきを良くします。
-
寝室の環境整備: 寝室は静かで暗く、快適な温度・湿度を保つようにしましょう。
-
就寝前のリラックス: ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、リラックスできる音楽を聴いたり、穏やかな読書をしたりする時間を設けましょう。
-
飲食の注意: 就寝4時間前からのカフェイン摂取、就寝1時間前からの喫煙は避けましょう。寝酒は眠りを浅くするため逆効果です。
-
寝る前のスマホ・PCを控える: 強い光(ブルーライト)は、睡眠を促すホルモン(メラトニン)の分泌を抑制してしまいます。
「不眠症」の参考動画
「不眠症」のまとめ
不眠症は、現代社会で多くの人が抱える深刻な問題です。
単なる「眠れない悩み」から、日中の活動の質の低下、さらには重大な健康問題や経済的な損失にまでつながっています。
もし「眠れない」状態が続き、日中の生活に支障を感じているなら、まずはご自身の生活習慣(睡眠衛生)を見直すことから始めてみてください。
それでも改善が見られない場合や、気分の落ち込みが激しい場合、あるいは睡眠中のいびきや呼吸停止を指摘された場合は、決して一人で悩まず、睡眠専門医や心療内科、精神科などの専門家に相談することが重要です。
質の良い睡眠は、心と体の健康を保つための土台です。
関連トピック
睡眠時無呼吸症候群 (SAS): 睡眠中に一時的に呼吸が止まることを繰り返す病気です。激しいいびきや日中の強い眠気を伴い、中途覚醒や熟眠障害の原因となります。
うつ病: 不眠はうつ病の代表的な症状の一つです。特に「早朝覚醒」はうつ病との関連が深いとされています。不眠とうつ病は相互に影響し合うため、両方のケアが必要な場合があります。
睡眠衛生: 快適な睡眠を得るために推奨される、日常生活での習慣や環境づくりのことです。規則正しい生活や寝室の環境整備などが含まれます。
メラトニン: 脳から分泌されるホルモンの一種で、体内時計を調整し、自然な眠気を促す働きがあります。朝に光を浴びることで分泌が抑制され、夜に暗くなると分泌が始まります。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。