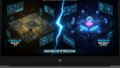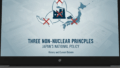安保関連3文書とは?日本の防衛政策大転換!概要、反撃能力、今後の影響を徹底解説
「安保関連3文書」の概要
安保関連3文書とは、2022年12月に岸田文雄内閣が閣議決定した、日本の安全保障政策の根幹となる3つの文書のことです。
具体的には、「国家安全保障戦略(NSS)」、「国家防衛戦略」(従来の「防衛計画の大綱」に代わるもの)、「防衛力整備計画」(従来の「中期防衛力整備計画」に代わるもの)を指します。
これらの文書は、ロシアによるウクライナ侵攻や、中国、北朝鮮の軍事的動向など、日本を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑になっているとの認識のもと策定されました。
日本の防衛政策を大きく転換する内容を含んでおり、国内外で大きな議論を呼んでいます。
「安保関連3文書」の詳細
策定の背景にある厳しい安全保障環境
安保関連3文書が策定された背景には、国際秩序の深刻な動揺があります。
特に、ロシアによるウクライナへの侵略は、力による一方的な現状変更の試みであり、既存の国際秩序を根底から揺るがすものとされています。
また、中国による急速な軍拡や海洋進出の動き、北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの発射実験なども、日本にとっての脅威として認識されています。
こうした厳しい安全保障環境の変化に対応するため、従来の防衛政策を見直し、防衛力を抜本的に強化する必要があるとの判断が示されました。
最大の焦点「反撃能力」の保有
今回の3文書で最も注目されるのが、「反撃能力」の保有を明記した点です。
これは、従来の「敵基地攻撃能力」と実質的に同義とされ、日本が他国から武力攻撃を受けた際、その攻撃を防ぐためにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手国の領域にあるミサイル発射拠点などに対して有効な反撃を加える能力を指します。
政府は、これはあくまで自衛権の範囲内であり、憲法9条が禁じる「戦力の行使」には当たらないと説明しています。
しかし、これは従来の「専守防衛」のあり方を大きく変える可能性があり、憲法との整合性や、かえって軍拡競争を招くのではないかといった懸念も指摘されています。
防衛費の大幅な増額と財源
もう一つの大きな柱が、防衛費の大幅な増額です。
3文書では、2023年度から2027年度までの5年間で、防衛費の総額を約43兆円とする方針が示されました。
これは、従来の5年間(2019~2023年度)の約27兆5000億円から大幅な増額となります。
また、2027年度には、防衛費と関連経費(海上保安庁予算、科学技術研究費など)を合わせた予算を、現在のGDP(国内総生産)の2%に達する水準にすることを目指すとしています。
この増額された防衛費は、反撃能力にも使われる長射程ミサイルの整備や、継戦能力の向上、サイバー防衛の強化などに充てられる計画です。
3文書の具体的な役割
「国家安全保障戦略(NSS)」は、外交・防衛を中心とする安全保障分野の最上位の戦略文書です。
日本の国益や安全保障上の目標、そのための戦略的なアプローチを示します。
「国家防衛戦略」は、NSSに基づき、防衛の目標や、それを達成するための「防衛のあり方」を定める文書です。
「防衛力整備計画」は、国家防衛戦略で示された「防衛のあり方」を実現するために、今後5年間(または10年間)で具体的にどのような防衛装備品をどれだけ整備するか、その経費はどれくらいかを示す計画です。
参考動画(YouTube解説)
まとめ:日本の防衛政策の歴史的転換点
安保関連3文書の決定は、戦後の日本の安全保障政策における歴史的な大転換点と言えます。
「反撃能力」の保有や防衛費の大幅な増額は、日本の防衛力を質・量ともに大きく強化するものです。
これは、厳しさを増す安全保障環境に対応するための現実的な選択であると評価する声がある一方で、平和憲法のもとでの専守防衛の理念から逸脱するのではないか、近隣諸国との緊張を高めるのではないかといった批判や懸念も根強く存在します。
また、巨額の防衛費増額の財源をどう確保するのか(増税、国債発行、歳出削減など)も、国民生活に直結する大きな課題です。
私たち国民一人ひとりが、この安保関連3文書の内容や背景、そして今後の影響について深く理解し、日本の進むべき道について議論を続けていくことが非常に重要です。
あなたは、この防衛政策の大きな転換について、どのようにお考えになりますか。
関連トピック
専守防衛: 相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという、日本の基本的な防衛戦略の姿勢です。今回の「反撃能力」保有が、この専守防衛の範囲内かどうかが大きな議論となっています。
集団的自衛権: 日本と密接な関係にある他国が攻撃された場合、それが日本の安全を脅かす事態であれば、共同して防衛にあたる権利のことです。2015年の平和安全法制(安保法制)によって、限定的ながら行使が容認されましたが、今回の3文書は、この集団的自衛権の運用にも影響を与える可能性があります。
GDP比2%: 防衛費の目標水準として示された、国内総生産(GDP)に対する比率です。これはNATO(北大西洋条約機構)諸国が目標としている水準であり、日本の従来の防衛費(おおむねGDP比1%程度)から倍増することを意味します。
防衛財源確保法: 防衛費増額のための財源を確保するために2023年に成立した法律です。税外収入の活用や決算剰余金の繰り入れなどが定められましたが、増税による財源確保の部分については、開始時期などが先送りされており、今後の議論の焦点となっています。
関連資料
国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定): 日本の安全保障政策の最上位文書であり、防衛省や外務省のウェブサイトで全文が公開されています。3文書の根幹となる考え方を理解するために最も重要な公式資料です。
日本の防衛(防衛白書): 防衛省が毎年発行している白書です。日本の安全保障環境や防衛政策、自衛隊の活動などについて網羅的に解説されており、安保関連3文書策定後の最新の動向を知る上で役立ちます。
(書籍)『「反撃能力」は日本を守れるか 安保3文書と防衛大転換』: 多くのジャーナリストや専門家が、安保3文書について論じた書籍を出版しています。例えば、岩波書店から出ている新書などは、多角的な視点からこの問題を理解するのに役立ちます。