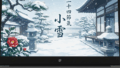国会議員歳費「月5万円増」はなぜ?今行われる理由と「お手盛り」批判の背景を徹底解説
「月5万円増」の概要
2025年11月、国会議員の給与にあたる「歳費」を月額約5万円引き上げる法改正案が浮上し、大きな波紋を呼んでいます。
物価高騰や実質賃金の伸び悩みに国民が苦しむ中、なぜ今、高額な報酬を受け取る国会議員の給与アップが議論されているのでしょうか。
本記事では、この増額案が出てきた法的な仕組み(人事院勧告)、「便乗値上げ」と批判される理由、そして他党の反応や過去の経緯について分かりやすく解説します。
詳細:仕組みと批判のポイント
1. なぜ「月5万円」増えるのか?その仕組み
今回の増額案の根拠となっているのは、「人事院勧告(じんじいんかんこく)」です。
公務員の給与は、民間企業の賃金水準に合わせて決めるというルールがあり、人事院という機関が毎年「民間が上がったから公務員も上げるべき(または下げるべき)」と国会や内閣に勧告を行います。
2024年から2025年にかけて、物価高への対応として民間企業で賃上げの動き(春闘など)が活発化したことを受け、一般の国家公務員の給与引き上げ(ベースアップ)が勧告されました。
ここからがポイントです。
国会議員の歳費は、法律(歳費法)によって「一般の公務員の給与改定に連動させる」という慣例や仕組みが強く働いています。
つまり、「一般公務員の給与が上がるなら、特別職である国会議員の給与も自動的に(法律を改正して)上げる」というロジックで、今回の「月額約5万円増」という数字が算出されました。
2. なぜ「今」なのか?批判される理由
このタイミングでの増額が猛反発を受けている最大の理由は、「国民感覚とのズレ」です。
一般公務員の賃上げは「人材確保」や「物価高対策」として必要性が理解されやすい一方、国会議員は既に月額約130万円近い歳費に加え、非課税の「調査研究広報滞在費(旧文通費)」月額100万円など、極めて高い待遇を受けています。
「国民は物価高で食費を削っているのに、政治家は自分たちの給料を上げるのか」「身を切る改革はどうなった」という怒りの声が上がるのは自然なことです。
これを専門用語やネットスラングで「お手盛り(自分たちで自分たちの利益を増やすこと)」や「便乗値上げ」と呼びます。
3. 各党の反応と「旧文通費」問題
この増額案に対し、自民党内では「公務員との均衡を考えればやむを得ない」として法改正を進める動きがある一方、日本維新の会や国民民主党などの野党の一部は強く反対しています。
「まずは不透明な『旧文通費』の使途公開や領収書添付を義務付ける改革を先にやるべきだ」という主張です。
本来議論すべき「政治とカネ」の問題(不透明な経費の改革)が遅々として進まない中で、自分たちの給与アップだけがスムーズに進むことへの不信感が、今回の騒動の核心にあります。
参考動画
まとめ
国会議員歳費の「月5万円増」は、法的な仕組み上は「公務員給与との連動」という理屈で説明されますが、国民感情としては到底納得できるものではありません。
特に、長年棚上げされている「旧文通費」の改革や、政治資金規正法の厳格化といった「身を切る改革」が不十分なままでの増額は、政治への信頼をさらに損なう可能性があります。
私たちは、彼らが「上げる理由」だけでなく、「その給与に見合う仕事をしているか」を厳しく監視し続ける必要があります。
関連トピック
人事院勧告:国家公務員の給与を民間水準に合わせるための勧告制度。議員歳費増額の根拠となる。
調査研究広報滞在費(旧文通費):月額100万円が支給される手当。使途公開の義務がなく「第2の財布」と呼ばれる。
身を切る改革:議員定数の削減や歳費のカットなど、政治家自身が痛みを伴う改革を行うこと。
関連資料
『政治家の給与と金 2025年版』:最新の政治資金の流れや歳費の仕組みを解説したデータブック。
『税金はどこへ消えた?』:国の予算配分や議員特権について鋭く切り込んだノンフィクション書籍。