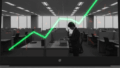日本の次なる宇宙大航海!火星衛星探査計画「MMX」徹底解説。フォボス着陸と世界初のサンプルリターンが太陽系の謎を解く。
火星衛星探査計画(MMX)の概要
火星衛星探査計画(Martian Moons eXploration:MMX)は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が中心となって進めている、日本の次なるフラッグシップ(旗艦)宇宙探査ミッションです。
この計画は、「はやぶさ」「はやぶさ2」で日本が世界をリードする「サンプルリターン(天体の試料を持ち帰る技術)」の集大成とも言える壮大な挑戦です。
MMX探査機の主な目的地は、火星に二つある衛星のうち、内側を公転する「フォボス」です。
探査機はフォボスに着陸し、その表面の砂(レゴリス)を採取。
そして、その貴重なサンプルを地球に持ち帰るという、世界初のミッションに挑みます。
この記事では、この「MMX」計画の概要、詳細、そしてなぜ今、火星の衛星を目指すのか、その科学的な意義について詳しく解説します。
MMX計画の詳細:火星圏の謎に迫る
MMX計画の二大目的:火星衛星の「起源」を解明せよ
MMX計画には、科学的に非常に重要な二つの目的があります。
1. 火星衛星(フォボスとダイモス)の起源の解明
火星には「フォボス」と「ダイモス」という二つの小さな衛星がありますが、その起源は長年の謎とされてきました。
これには大きく分けて二つの説があります。
一つは、もともと小惑星帯にあった天体が火星の重力に捕らえられたとする「捕獲説」。
もう一つは、太古の火星に巨大な天体が衝突し、その際に飛び散った破片が集まって衛星ができたとする「巨大衝突説」です。
MMXは、フォボスから持ち帰ったサンプルを地球で詳細に分析することにより、この二つの説のどちらが正しいのかに決定的な証拠をもたらすことを目指しています。
2. 火星圏の進化プロセスの解明
MMXは、フォボスとダイモスの探査を通じて、火星とその衛星群(火星圏)がどのように形成され、進化してきたのかを明らかにします。
特に、もし「巨大衝突説」が正しければ、フォボスの表面には、衝突によって火星本体から飛び散った太古の火星の物質が降り積もっている可能性があります。
つまり、フォボスのサンプルを調べることは、火星本体に降り立たずして「数十億年前の火星」の情報を手に入れることに繋がるかもしれないのです。
これは、かつて火星に海が存在した時代や、もしかしたら生命が存在したかもしれない時代の痕跡を探ることにも繋がる、非常にロマンあふれる探査です。
ミッションの詳細とスケジュール
MMX探査機は、JAXAの新型基幹ロケット「H3ロケット」によって、2026年度に打ち上げられる予定です。
打ち上げ後、約1年かけて火星の周回軌道に到着します。
火星圏に到着すると、まずはもう一つの衛星「ダイモス」に接近して観測を行います。
その後、約3年間にわたり、ミッションの主目的であるフォボスを詳細に観測します。
観測データを元に着陸地点を選定し、フォボスの表面に少なくとも1回着陸。
地表の砂(レゴリス)を10グラム以上採取することを目指します。
サンプル採取には、ドリルで地下の物質を採取する「コアラー」と、ガスの噴射で舞い上がった砂を吸引する「ニューマティック式」の2種類の方法が用意されています。
サンプル採取後、探査機はフォボスを離脱し、再び地球への帰還の途につきます。
地球への帰還は、2031年頃が予定されています。
「はやぶさ2」を超える技術的挑戦
このミッションは、「はやぶさ2」の成功で培った技術をさらに発展させたものです。
しかし、小惑星リュウグウとフォボスでは環境が大きく異なります。
リュウグウは重力が非常に微弱だったため、探査機はゆっくりと降下できました。
一方、フォボスはリュウグウよりは重力があるものの、火星本体の強い重力の影響(潮汐力)を受けており、着陸・離陸の制御は非常に複雑で高度な技術が要求されます。
MMXは、この難易度の高いミッションを成功させるため、フランスやドイツ、アメリカ(NASA)とも協力する国際ミッションとなっています。
特に、フランスとドイツが開発した小型ローバー(探査車)も搭載され、フォボス表面に投下されて着陸前に表面の状況を調査する予定です。
参考動画
まとめ
火星衛星探査計画「MMX」は、単に火星の衛星を調べるだけのミッションではありません。
これは、火星の衛星の起源という天文学的な大問題に答えを出し、さらには火星本体の太古の姿、そして生命の可能性にまで迫ろうとする、知的好奇心の結晶とも言える計画です。
「はやぶさ2」が持ち帰ったリュウグウのサンプルが「水」や「有機物」という生命の材料の起源を明らかにしつつあるように、MMXが持ち帰るフォボスのサンプルは、太陽系の進化、特に地球の隣人である火星の歴史を書き換えるかもしれません。
2026年度の打ち上げ、そして2031年の感動的なサンプル帰還に向け、JAXAの挑戦から目が離せません。
関連トピック
はやぶさ2: MMX計画の技術的な礎となった、日本の小惑星探査機。
小惑星リュウグウからサンプルリターンを成功させ、太陽系初期の貴重な情報を地球にもたらしました。
フォボスとダイモス: 火星が持つ二つの小さな衛星。
名前はギリシャ神話において軍神アレス(火星)に従う息子の「恐怖(フォボス)」と「敗走(ダイモス)」に由来します。
そのいびつな形状から、長年「捕獲された小惑星」だと考えられてきました。
サンプルリターン: 宇宙探査機が地球以外の天体に着陸し、その天体の物質(砂や石、ガスなど)を採取して地球に持ち帰る技術。
JAXAが世界をリードする分野の一つです。
関連資料
JAXA MMXプロジェクト公式サイト: MMXミッションに関する最新情報、CGによる解説、搭載機器の詳細などが最も正確に掲載されている公式情報源です。
『MMX 火星衛星探査計画』(寺薗淳也 著): MMX計画の科学的意義や技術的な挑戦について、一般の読者にも分かりやすく解説した書籍です。
国立科学博物館(東京・上野): 日本の宇宙開発の歴史や、「はやぶさ」「はやぶさ2」が持ち帰ったカプセル(実物やレプリカ)などが常設展示されており、サンプルリターン技術のすごさを体感できます。