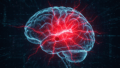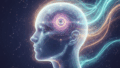「あれ、何だっけ?」その物忘れ、大丈夫? 年齢による違いと認知症の危険なサイン、今日からできる対策を徹底解説
物忘れの概要
「今、何をしようとしていたか忘れた」。
「あの人の名前が、喉まで出かかっているのに思い出せない」。
こうした「物忘れ(ものわすれ)」は、年齢を重ねるにつれて誰にでも起こり得る、ごく自然な脳の生理現象の一つです。
しかし、物忘れが頻繁になると、「もしかして認知症の始まりではないか」と不安に感じる方も少なくありません。
重要なのは、加齢による自然な物忘れ(良性の物忘れ)と、病気のサインである可能性のある物忘れ(危険な物忘れ)の違いを正しく理解することです。
その見分け方と、脳の健康を保つための対策を知っておくことが、不安の軽減と早期発見につながります。
物忘れの詳細:良性と危険なサインの見分け方
物忘れには、心配のいらないものと、注意すべきものがあります。
その違いを詳しく見ていきましょう。
加齢による「良性の物忘れ」の特徴
年齢を重ねることで生じる物忘れは、脳の処理速度が少し遅くなったり、記憶を引き出す力が一時的に低下したりすることが原因です。
これは病気ではありません。
-
体験の一部を忘れる:
例えば、「昨日の夕食は食べたが、何を食べたか(メニュー)を細かく思い出せない」といった状態です。体験したこと自体は覚えています。
-
忘れたことを自覚している:
「あれ、なんだっけ?」と、自分が何かを忘れていること自体を認識しています。そのため、メモを取るなどの工夫を自分で行おうとします。
-
ヒントがあれば思い出せる:
「あの俳優、ほら、あのドラマに出ていた…」という状態でも、「〇〇さんだよ」とヒントをもらえば「ああ、そうそう!」と思い出すことができます。 -
日常生活に支障はない:
物忘れはあっても、日常生活や家事、仕事などを一人で問題なくこなすことができます。
認知症など病気による「危険な物忘れ」の特徴
一方、認知症(アルツハイマー型認知症など)による物忘れは、脳の神経細胞が壊れてしまうことで記憶そのものが失われる状態(記憶障害)です。
これは早期の対応が必要です。
-
体験の全部を忘れる:
「昨日の夕食を食べたこと自体」をすっぽりと忘れてしまいます。そのため、食事をした直後に「ご飯はまだ?」と要求することがあります。
-
忘れたことの自覚がない:
体験そのものが抜け落ちているため、自分が忘れたという認識がありません。そのため、周りから「さっきも同じことを言ったよ」と指摘されても、本人にとっては初めてのことなので怒ったり、混乱したりすることがあります。
-
ヒントがあっても思い出せない:
出来事自体が記憶されていないため、ヒントをもらっても思い出すことができません。 -
日常生活に支障が出る:
同じことを何度も尋ねる、約束をすっぽかす、慣れた道で迷う、日付や曜日がわからなくなるなど、日常生活に明らかな支障が出始めます。
物忘れを引き起こすその他の原因
物忘れは、加齢や認知症だけでなく、以下のような要因でも引き起こされます。
-
ストレスや疲労:
過度なストレスや慢性的な疲労、悩み事があると、脳の働きが低下し、一時的に記憶力や集中力が落ちることがあります。 -
睡眠不足:
睡眠は、脳が記憶を整理し定着させるための重要な時間です。睡眠不足が続くと、新しいことを覚えにくくなります。
-
うつ状態:
気分が落ち込む「うつ状態」や「うつ病」になると、物事への関心が薄れ、記憶力が低下することがあります。これは「仮性認知症」と呼ばれることもあります。
物忘れが気になった時の対策と予防
脳の健康を保ち、良性の物忘れの進行を緩やかにするためには、日々の生活習慣が重要です。
-
生活習慣の見直し:
十分な睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事(特に青魚、野菜、果物など)を心がけましょう。ウォーキングなどの適度な運動は、脳の血流を良くする効果が期待できます。
-
メモや整理整頓の習慣:
忘れても困らないように、大事な予定はカレンダーや手帳に書き出す、鍵や財布は決まった場所に置く、といった工夫が有効です。 -
脳を積極的に使う:
新しいことに挑戦する、趣味を持つ、本を読む、人と会話を楽しむといった知的活動や社会的な交流は、脳にとって良い刺激となります。 -
専門機関への相談:
もし「危険な物忘れ」のサインに当てはまる、日常生活に支障が出ている、家族から見て明らかに様子がおかしいと感じる場合は、ためらわずに専門の医療機関(「物忘れ外来」や「認知症疾患医療センター」、脳神経内科、精神科など)を受診してください。認知症は、早期に発見し、適切な治療やケアを開始することが、その後の進行を遅らせる上で非常に重要です。
参考動画:もの忘れ?認知症?見分けのポイント
まとめ:不安を抱えず、まずは違いを知ることから
物忘れは、誰にでも起こる自然な現象です。
「また忘れた」と過度に落ち込む必要はありませんが、「忘れたことを自覚できているか」「体験の一部か、全部か」といった違いを冷静に観察することは大切です。
物忘れの多くは、生活習慣の見直しやストレス管理で改善が期待できます。
しかし、もし認知症が疑われるサインが見られた場合は、不安を抱え込まず、できるだけ早く専門家へ相談することが、ご本人とご家族の未来を守る最善の策となります。
脳の健康を意識した生活を今日から始めてみましょう。
「物忘れ」に関連するトピック
認知症(にんちしょう)
脳の病気や障害などにより、記憶、思考、判断などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態です。アルツハイマー型認知症が最も多いです。
軽度認知障害(MCI)
物忘れの訴えはあるものの、認知症とは診断できない(日常生活への支障は出ていない)、正常な老化と認知症の中間の「グレーゾーン」の状態です。早期に介入することで認知症への進行を予防・遅延できる可能性があるため、注目されています。
睡眠(すいみん)
脳が休息し、日中に得た情報を整理・定着させるための不可欠な時間です。睡眠の質と量は、記憶力に直接影響します。
ストレス
過度な精神的ストレスは、脳の記憶を司る「海馬」の働きを弱め、一時的な物忘れの原因になることが知られています。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。
認知症YouTube講座④もの忘れ?認知症?見分けのポイント – YouTube