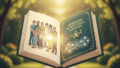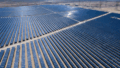難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)とは? 3つの柱と医療費助成の仕組みを解説
難病法の概要
難病法(なんびょうほう)とは、2015年(平成27年)1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」の通称です。
この法律は、従来の「特定疾患治療研究事業」が抱えていた課題(対象疾患の公平性や財源の不安定さなど)を解決し、難病患者さんをより幅広く、安定的に支援するために制定されました。
難病法の基本的な理念は、難病の克服を目指しつつ、難病患者さんが尊厳を保持し地域社会で共生できる社会を実現することにあります。
法律の大きな柱として、①公平で安定的な医療費助成(指定難病)、②難病に関する調査・研究の推進、③療養生活の質の維持向上(相談・就労支援など)が定められています。
難病法の詳細
難病法の目的と背景
難病法が制定される以前は、国の「特定疾患治療研究事業」によって、一部の難病(特定疾患:最終的に56疾患)に対する医療費助成が行われていました。
しかし、この制度は予算事業であったため財源が不安定であり、また対象疾患の選定基準が必ずしも明確でなく、助成を受けられない他の難病患者さんとの間に不公平感が存在していました。
こうした課題を解決し、支援の対象を拡大するとともに、消費税増収分の一部を恒久的な財源とすることで、より公平かつ安定した難病対策を実現するために難病法は制定されました。
法律の第一条(目的)では、難病患者さんへの「良質かつ適切な医療の確保」と「療養生活の質の維持向上」、そして「国民保健の向上」がうたわれています。
法律における「難病」と「指定難病」の定義
難病法では、「難病」と「指定難病」という2つの言葉が明確に定義されています。
- 難病: 発病の機構(原因)が明らかでなく、治療方法が確立しておらず、希少な疾病であり、長期にわたる療養を必要とするもの。
- 指定難病: 上記の「難病」の定義を満たすもののうち、患者数が一定の人数(人口の0.1%程度)に達せず、客観的な診断基準が確立しているもの。この「指定難病」が、後述する医療費助成の対象となります。
この法律により、医療費助成の対象となる「指定難病」は、従来の56疾患から大幅に拡大され、2024年現在では340以上の疾患が指定されています。
難病法の3つの柱
難病法に基づく施策は、主に以下の3つの柱で構成されています。
1. 公平・安定的な医療費助成(特定医療費)
法律の最も中心的な支援が、指定難病患者さんに対する医療費助成制度です。
- 対象者: 指定難病と診断され、疾患ごとの重症度基準を満たす方、または症状が軽くても高額な医療が継続して必要な方(軽症高額該当)です。
- 助成内容: 指定難病の治療にかかる医療費(診察、薬剤、訪問看護など)について、医療保険適用後の自己負担割合が3割から2割に軽減されます。
- 自己負担上限額: 世帯の所得に応じて、月々の医療費の「自己負担上限額」が設定されます。複数の指定医療機関でかかった医療費を合算しても、この上限額を超える支払いは発生しません。
- 申請: この助成を受けるには、都道府県の「難病指定医」が作成した臨床調査個人票(診断書)を添えて、お住まいの自治体(保健所など)に申請し、「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受ける必要があります。
2. 難病に関する調査・研究の推進
難病の根本的な克服を目指すため、国や自治体が難病の研究を推進することが法律で定められています。
患者さんの診断書(臨床調査個人票)などの情報を収集・データベース化し、発病の原因究明、診断基準の確立、画期的な治療法の開発などに役立てる体制が強化されました。
3. 療養生活の質の維持向上(療養生活環境整備)
医療費の支援だけでなく、難病患者さんが地域で安心して生活できるよう、療養生活の環境を整備することも法律の重要な柱です。
- 難病相談支援センター: 各都道府県・指定都市に設置され、患者さんやご家族からの療養生活や就労に関する様々な相談に応じ、情報提供や助言を行っています。
- 就労支援: ハローワーク(公共職業安定所)に「難病患者就職サポーター」が配置され、難病相談支援センターと連携しながら、症状の特性を踏まえた就職相談や、在職中の患者さんの雇用継続支援を行っています。
- 障害福祉サービス: 難病法と連動し、「障害者総合支援法」の対象に指定難病患者さんなどが加わりました。これにより、身体障害者手帳などを持っていなくても、必要性が認められればホームヘルプや就労移行支援などの障害福祉サービスを利用できるようになりました。
参考動画(指定難病の医療費助成制度)
まとめ:難病患者さんを社会全体で支える法律
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)は、従来の「特定疾患」制度から大きく前進し、難病患者さんを社会全体で支えるための法的基盤を確立した法律です。
この法律により、医療費助成の対象者が大幅に拡大されただけでなく、難病研究の推進や、療養生活・就労に関する相談支援体制が強化されました。
ご自身やご家族が難病と診断された場合、この法律に基づく様々な支援を受けられる可能性があります。
まずは主治医や病院の医療ソーシャルワーカー、そしてお住まいの地域の保健所や「難病相談支援センター」に相談し、どのような支援が利用できるかを確認することが重要です。