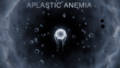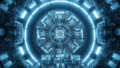核融合発電とは?未来のエネルギー源の仕組み、メリット・デメリット、実用化の今を徹底解説!
「核融合発電」の概要
核融合発電は、太陽が輝き続ける原理と同じ「核融合反応」を利用してエネルギーを取り出す、次世代の発電技術です。
現在の原子力発電(核分裂)とは異なり、非常に軽い原子核同士を合体(融合)させて、より重い原子核に変える際、莫大なエネルギーが発生する現象を利用します。
燃料が海水中にほぼ無尽蔵に存在することや、発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しないこと、原理的に暴走の危険性が低いことなどから、エネルギー問題と環境問題を根本から解決する「夢のエネルギー」として世界中で研究開発が進められています。
日本も国際プロジェクト「ITER(イーター)」への参加や、国内の実験装置「JT-60SA」などで、実用化に向けた研究をリードしています。
本記事では、核融合発電の基本的な仕組みから、そのメリットと課題、そして実用化に向けた最新の動向まで、わかりやすく解説します。
「核融合発電」の詳細
核融合発電の基本的な仕組み
核融合発電の主な燃料として研究されているのは、水素の仲間(同位体)である「重水素(D)」と「三重水素(T)」です。
重水素は海水中に豊富に含まれており、三重水素は自然界にはほとんど存在しませんが、核融合炉の内部でリチウム(海水や地殻から採取可能)から生成することができます。
この重水素と三重水素の混合ガスを、1億度以上という超高温に加熱すると、原子核と電子がバラバラになった「プラズマ」という状態になります。
この超高温のプラズマの中で、重水素と三重水素の原子核が高速で衝突し、融合します。
この「D-T核融合反応」によって、「ヘリウム」と「中性子」が生成されます。
重要なのは、この反応の前後で物質の質量がわずかに減ることで、その減った質量(質量欠損)が、アインシュタインの有名な公式 $E=mc^2$ に従って莫大なエネルギーに変換されることです。
発生したエネルギーの大部分は、新しく生まれた中性子が猛烈なスピードで飛び出す運動エネルギーとして放出されます。
この中性子を核融合炉の壁(ブランケットと呼ばれる装置)で受け止め、その運動エネルギーを熱エネルギーに変換します。
この熱を利用して蒸気を発生させ、タービンを回すことで発電するのが、核融合発電の基本的な流れです。
なぜ「夢のエネルギー」と呼ばれるのか?(メリット)
核融合発電が実用化されると、人類に多くの恩恵をもたらすと期待されています。
1. 豊富な燃料資源
主な燃料となる重水素は、海水1リットル中に約0.033グラム含まれており、地球上の海水全体では膨大な量になります。
もう一方の燃料である三重水素の原料となるリチウムも、海水や地殻に豊富に存在します。
計算上、海水中の重水素とリチウムだけで、人類が消費するエネルギーの数百万年分を賄えるとされています。
2. 高い安全性
核融合反応は、1億度以上のプラズマ状態という非常に特殊な環境を人工的に維持して初めて起こります。
もし何らかの異常で装置が停止したり、燃料供給が途絶えたりすれば、プラズマは瞬時に冷えて反応は自動的に停止します。
現在の原子力発電(核分裂)のように、連鎖反応が制御できなくなって暴走する(メルトダウンのような)危険性は原理的にありません。
3. 環境負荷が低い(クリーン)
発電の過程で、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)を排出しません。
また、現在の原子力発電で問題となる「高レベル放射性廃棄物」(ウランの核分裂で生じる、半減期が数万年にも及ぶ物質)を原理的に生み出しません。
ただし、反応で生じる中性子によって炉壁などの構造物が放射化(放射能を持つようになる)しますが、その放射能は高レベル廃棄物と比べて比較的短い期間(数十年から100年程度)で減衰するとされています。
4. 莫大なエネルギー効率
わずかな燃料から膨大なエネルギーを取り出せます。
燃料1グラムあたりで比較すると、核融合反応で得られるエネルギーは、石油を燃やして得られるエネルギーの約8トン分に相当します。
実用化に向けた高いハードル(課題・デメリット)
多くのメリットがある一方で、核融合発電の実現には超えるべき技術的な課題が山積しています。
1. 超高温プラズマの維持
核融合反応を持続的に起こすには、1億度以上という超高温のプラズマを、真空容器の中で壁に触れないように安定して閉じ込め続ける必要があります。
太陽が自身の強大な重力でプラズマを閉じ込めているのに対し、地上では強力な磁場を使ってプラズマを閉じ込める方法(磁場閉じ込め方式)が主流です。
この方式には「トカマク型」や「ヘリカル型」などがあり、いかに長時間、安定してプラズマを維持できるかが最大の課題です。
2. エネルギー収支(Q値)の問題
核融合炉を運転するには、プラズマを加熱したり、強力な磁場を作ったりするために大量のエネルギーを投入する必要があります。
発電所として成り立つためには、投入したエネルギーよりも、核融合反応によって得られたエネルギーの方が圧倒的に大きくなければなりません。
この「投入エネルギーに対する発生エネルギーの比率」を「Q値」と呼び、Q値が1を超える(投入した以上のエネルギーが生まれる)ことが「点火」と呼ばれるマイルストーンの一つです。
アメリカの国立点火施設(NIF)が2022年にレーザー核融合方式でQ値>1を達成しましたが、これは瞬間的なものであり、継続的に発電するにはQ値が10以上、商用炉としては30以上が必要とされています。
3. 耐久性の高い材料開発
核融合炉の内部は、超高温のプラズマと、反応で生じる強力な中性子に常にさらされます。
特に中性子は物質を透過して構造材を脆く(もろく)したり、放射化させたりします。
このような過酷な環境に長期間耐えうる炉壁材料や、三重水素を効率よく生成・回収するためのブランケット材料の開発が不可欠です。
4. 莫大な建設コスト
核融合実験炉の建設には、超伝導コイルや真空容器など、最先端の巨大な装置が必要であり、莫大な研究開発費と建設コストがかかります。
世界と日本の最新動向
これらの課題を克服するため、世界中で研究が進められています。
国際熱核融合実験炉「ITER(イーター)」
フランスで建設が進むITERは、日本、欧州、米国、ロシア、中国、韓国、インドの7極が協力する超大型の国際プロジェクトです。
トカマク型の実験炉で、Q値10(投入したエネルギーの10倍のエネルギーを発生させる)を目標としており、核融合発電の科学的・技術的な実証を目指しています。
日本の取り組み「JT-60SA」
日本では、量子科学技術研究開発機構(QST)が、ITERを補完・先行する実験装置として「JT-60SA」(トカマク型)を茨城県那珂市で建設・運用しています。
JT-60SAは、ITERよりも早く高性能なプラズマ運転を実現し、将来の原型炉(発電実証プラント)の設計に必要なデータを収集することを目的としています。
民間ベンチャーの台頭
近年、米国や英国を中心に、政府主導のプロジェクトだけでなく、多くの民間スタートアップ企業が核融合発電の早期実用化を目指して競争を繰り広げています。
これらの企業は、従来とは異なる新しい方式や小型化を模索し、巨額の投資を集めています。
実用化はいつ?
日本政府は、2030年代に発電を実証する「原型炉」の建設を目指し、2040年代から2050年頃の実用化を目標に掲げています。
世界的な競争と技術革新の加速により、このスケジュールが早まる可能性も期待されています。
「核融合発電」の参考動画
「核融合発電」のまとめ
核融合発電は、「地上の太陽」とも呼ばれるように、人類のエネルギー問題を根本的に解決し、脱炭素社会を実現する可能性を秘めた究極のエネルギー源です。
その原理は確立されているものの、実用化までには「1億度のプラズマの維持」「エネルギー収支の黒字化」「高耐久材料の開発」といった、極めて高度な技術的課題をいくつも乗り越えなければなりません。
現在は、ITERやJT-60SAといった国家プロジェクトに加え、世界中の民間ベンチャーが参入することで、かつてないスピードで研究開発が進んでいます。
私たちが生きている間に「核融合発電所」が稼働を開始するのか、それともまだ「30年後の夢」であり続けるのか。
この壮大な挑戦は、未来の地球環境と私たちの生活を大きく左右する重要なトピックであり、今後もその動向から目が離せません。
関連トピック
プラズマ: 物質は通常、固体・液体・気体の3つの状態をとりますが、気体をさらに加熱すると原子核と電子が分離した状態になります。これが物質の第4の状態と呼ばれる「プラズマ」であり、核融合反応が起こる舞台です。
ITER(国際熱核融合実験炉): フランスで建設中の、核融合の工学的実証を目指す超大型の国際共同プロジェクト。日本も主要メンバーとして参加しています。
トカマク型とヘリカル型: プラズマを磁場で閉じ込める方式の主流です。「トカマク型」(ITERやJT-60SAが採用)はドーナツ状のプラズマ電流とコイルで作る磁場を利用し、「ヘリカル型」(日本にも大型装置あり)は複雑にねじれたコイルだけで磁場を作ります。
レーザー核融合(慣性核融合): 磁場ではなく、燃料ペレットの周囲から強力なレーザーを均一に照射し、爆縮・圧縮することで中心部を超高温・超高密度にして核融合を起こす方式です。米国のNIFがこの方式でQ値>1を達成しました。
関連資料
『核融合炉入門 ―フュージョンエネルギーへの道』 (岡野 邦彦 著, 日本エネルギー学会 編): 核融合炉の基本的な仕組みから、ITER計画の進捗、経済性、ベンチャーの動向まで、専門家が分かりやすく解説した入門書です。
『図解入門業界研究 最新核融合産業の動向と仕組みがよくわかる本』 (尾崎 弘之 著): 核融合発電が「産業」としてどのように成立しようとしているのか、国内外のスタートアップ企業の動向も含めて図解で解説されています。
量子科学技術研究開発機構(QST)核融合エネルギー研究所: 日本の核融合研究の中心的な機関であり、JT-60SAなどの最新情報や、核融合に関する分かりやすい解説が掲載されています。
ITER機構(ITER Organization)ウェブサイト: 国際プロジェクトITERの公式ウェブサイト。建設状況やプロジェクトの目的について詳細な情報が公開されています(日本語ページもあります)。