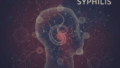親知らずは抜くべき?抜かないべき?親知らずの基礎知識、抜歯の必要性、痛み、抜歯後の注意点まで徹底解説
親知らずの概要
親知らず(おやしらず)は、10代後半から20代前半頃に生えてくる一番奥の永久歯で、正式には「第三大臼歯」または「智歯(ちし)」と呼ばれます。
現代人は食生活の変化などから顎が小さくなっており、親知らずがまっすぐ生えるための十分なスペースがないことが多くなりました。
その結果、親知らずが横向きに生えたり、歯茎の中に埋まったままだったり、一部だけが中途半端に顔を出したりすることが増えています。
このような親知らずは、歯ブラシが届きにくいために不潔になりやすく、虫歯や「智歯周囲炎」と呼ばれる歯茎の炎症、さらには歯並びの悪化など、様々な口内トラブルの原因となることがあります。
必ずしもすべての親知らずを抜く必要はありませんが、多くのケースで将来的なリスクを回避するために抜歯が推奨されています。
親知らずの詳細:トラブルの原因と抜歯の必要性
親知らずがなぜ問題を引き起こしやすいのか、どのような場合に抜歯が必要になるのか、その詳細を見ていきましょう。
親知らずとは?
親知らずは、上下左右の一番奥に1本ずつ、合計で最大4本生える可能性がある歯です。
人によっては生まれつき親知らずの本数が少なかったり、全くなかったりする人もいます。
また、顎の骨の中に完全に埋まったまま(埋伏歯:まいふくし)で、一生生えてこないケースもあります。
「親が知らないうちに生えてくる歯」という意味で「親知らず」と呼ばれるようになったと言われています。
親知らずが引き起こす主なトラブル
親知らずが問題となる最大の理由は、生えるスペースの不足と、一番奥にあることによる清掃の困難さです。
-
智歯周囲炎(ちししゅういえん)
親知らずが斜めや横向きに生えたり、一部だけが歯茎から出ていたりすると、歯と歯茎の間に深い溝ができてしまいます。この溝に細菌が溜まって繁殖し、歯茎が炎症を起こして腫れたり、痛みが出たり、膿が出たりする状態を「智歯周囲炎」と呼びます。
悪化すると口が開きにくくなったり、発熱や倦怠感を伴ったりすることもあり、親知らずを抜歯する最も多い原因の一つです。
体調を崩して免疫力が低下したときに、この炎症が起きやすくなる傾向があります。
-
虫歯(親知らず自体と手前の歯)
親知らずは最も奥にあるため、歯ブラシの毛先が届きにくく、非常に磨き残しが多い場所です。そのため、親知らず自体が虫歯になりやすくなります。
さらに深刻なのは、親知らずが手前の歯(第二大臼歯)を押すように斜めに生えている場合です。
親知らずと手前の歯との間に汚れが溜まり、手前の健康な歯まで虫歯にしてしまうリスクが非常に高くなります。
-
歯並びへの影響
親知らずが横向きや斜めに生えてくると、手前の歯を前方に押す力が加わることがあります。この力が、時間をかけて前歯の歯並びを悪化させる原因の一つになると考えられています。
矯正治療を行う際には、親知らずが歯の移動の妨げになるため、治療開始前後に抜歯することが一般的です。
-
嚢胞(のうほう)
頻度は稀ですが、骨の中に埋まった親知らずの周囲に「歯原性嚢胞」と呼ばれる液体の入った袋ができることがあります。この嚢胞は徐々に大きくなり、周りの顎の骨を溶かしてしまうことがあるため、発見された場合は摘出の手術が必要になります。
親知らずの抜歯は必要?(抜くべきケース・抜かないケース)
親知らずがあるからといって、すべてを抜かなければならないわけではありません。
-
抜歯が推奨されるケース
・智歯周囲炎を繰り返し起こしている(痛みや腫れ)。
・親知らずが虫歯になっている、または手前の歯が虫歯になるリスクが極めて高い。
・横向きや斜めに生えており、清掃が不可能である。
・手前の歯を押しており、歯並びに悪影響を与える可能性がある。
・矯正治療の妨げになる場合。
・上下どちらかしか生えておらず、噛み合わずに反対側の歯茎を噛んでしまう場合。 -
抜歯しなくてもよい(経過観察)ケース
・まっすぐ正常に生えており、上下の歯としっかり噛み合っている。
・歯磨きが問題なく行え、清掃状態が良好である。
・完全に骨の中に埋まっており(完全埋伏)、今後トラブルを起こす可能性が低いと診断された場合。
親知らずの抜歯と抜歯後の注意点
親知らずの抜歯は、生え方によって難易度が大きく異なります。
-
抜歯の難易度と痛み・腫れ
まっすぐ生えている上の親知らずなどは、比較的簡単に抜けることが多いです。一方、下の親知らずで、横向きに生えていたり、骨の中に深く埋まっていたりするケース(難抜歯)では、歯茎を切開したり、歯を分割したり、周りの骨を少し削ったりする必要があるため、手術時間が長くなり、抜歯後の痛みや腫れも出やすくなります。
抜歯後の痛みや腫れは、通常2~3日後をピークとし、1週間ほどで徐々に落ち着いていきます。
痛みは処方される鎮痛剤でコントロールし、腫れは冷やしすぎない程度に冷やすことが推奨されます(冷やしすぎると血流が悪くなり治癒が遅れるため)。
-
抜歯後の主な注意点
・処方された抗生物質(化膿止め)や鎮痛剤は、歯科医師の指示通りに必ず服用してください。・抜歯当日は、血行が良くなる行為(激しい運動、長時間の入浴、サウナ、飲酒)は避けてください。出血が止まりにくくなったり、痛みが増したりする原因になります。
・抜歯した穴には「血餅(けっぺい)」と呼ばれる血のかさぶたができ、傷口を治癒させる重要な役割を果たします。強くうがいをしたり、傷口を舌や指で触ったりすると、この血餅が剥がれて骨が露出し、激しい痛みを伴う「ドライソケット」になる可能性があります。うがいは優しく行うか、当日は控えるようにしてください。
・麻酔が切れるまでは、唇や頬を誤って噛まないよう注意し、食事は麻酔が切れてから、反対側の歯で柔らかいものを中心に摂るようにしてください。
・喫煙は傷の治りを著しく悪くするため、抜歯後はできるだけ控えることが強く推奨されます。
参考動画:【現役歯科医師が解説!】親知らずってどうしたらいい??
まとめ:親知らずの不安は歯科医師への相談から
親知らずは、現代人にとって口内のトラブルメーカーとなりやすい歯です。
痛みや腫れなどの症状がすでに出ている場合はもちろんですが、現在は症状がなくても、将来的に虫歯や智歯周囲炎の高いリスクを抱えているケースも少なくありません。
特に女性の場合、妊娠中はホルモンバランスの変化で歯茎が腫れやすくなる(妊娠性歯肉炎)うえ、つわりで歯磨きが難しくなったり、レントゲン撮影や投薬が制限されたりするため、親知らずのトラブルが起きてもすぐに対処できないことがあります。
そのため、将来的に妊娠を希望する場合は、その前に歯科医院で親知らずの状態をチェックし、必要であれば抜歯しておくことが推奨されます。
自分の親知らずがどのような状態なのか、抜く必要があるのか、いつ抜くのがベストなのかは、自己判断せずに、まずはかかりつけの歯科医師に相談し、レントゲン撮影などによる正確な診断を受けることが最も重要です。
親知らずに関連するトピック
智歯周囲炎(ちししゅういえん)
親知らずの周囲の歯茎が細菌感染によって炎症を起こす病気です。親知らずの抜歯理由として最も多いものの一つで、悪化すると口が開かなくなることもあります。
埋伏歯(まいふくし)
歯が顎の骨の中や歯茎の下に埋まったまま、正常に生えてこない状態の歯を指します。親知らず(特に下の歯)に最も多く見られ、抜歯が難しくなる主な原因です。
ドライソケット
抜歯後に、抜歯した穴の血餅(血のかさぶた)が何らかの原因で剥がれてしまい、骨が露出することで激しい痛みが生じる状態です。抜歯後の強いうがいを避けることなどで予防できます。
口腔外科(こうくうげか)
歯や歯茎だけでなく、顎の骨、舌、粘膜など、口の中(口腔)とそれに隣接する組織の疾患を扱う診療科です。横向きに生えている親知らずの抜歯など、難易度の高い抜歯は、一般歯科ではなく口腔外科を専門とする歯科医師が担当することが多いです。
ご注意:これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。