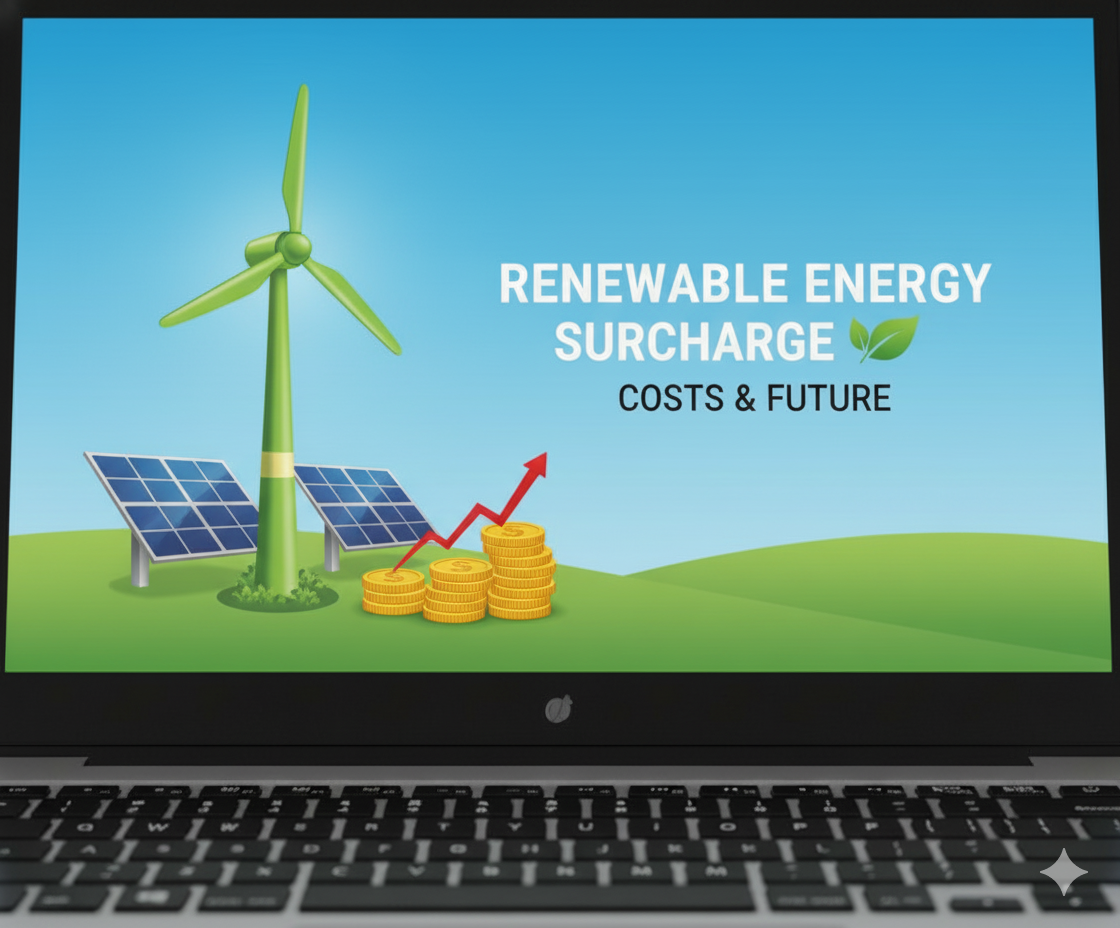電気代が高い原因?「再エネ賦課金」とは何か。仕組み、高騰の理由、いつまで続くのかを徹底解説!
「再エネ賦課金」の概要
再エネ賦課金とは、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略称です。
毎月の電気料金の明細に必ず記載されている項目の一つで、電気を使用するすべての人(家庭・企業)が支払っています。
これは、太陽光発電や風力発電といった「再生可能エネルギー(再エネ)」を日本国内で普及させるため、電力会社が再エネの電気を買い取る費用(FIT制度)を、私たち国民全員で公平に負担する仕組みです。
近年、この再エネ賦課金の単価が上昇傾向にあり、「電気代が高い」と感じる大きな要因の一つとなっています。
「再エネ賦課金」の詳細
なぜ支払う? FIT制度(固定価格買取制度)の仕組み
再エネ賦課金を理解するには、まず「FIT制度(固定価格買取制度)」を知る必要があります。
これは、日本がCO2排出量を削減し(地球温暖化対策)、エネルギー自給率を向上させるために、再生可能エネルギーの導入を促進する目的で2012年に始まりました。
この制度は、太陽光や風力などで発電された電気を、国が定めた「固定価格」で、電力会社が一定期間(例:家庭用太陽光は10年、事業用は20年)買い取ることを義務付けるものです。
発電事業者にとっては、長期間安定した収益が見込めるため、再エネ設備への投資が進みました。
しかし、電力会社がその電気を買い取るための莫大な費用が発生します。
この買取費用を、電気の利用者全員で公平に分担しましょう、というのが「再エネ賦課金」の基本的な考え方です。
どう支払っている? 賦課金の計算方法
私たちは、再エネ賦課金を電気料金の一部として、毎月自動的に支払っています。
賦課金の額は、非常にシンプルな計算式で決まります。
「再エネ賦課金 = 電気使用量 (kWh) × 再エネ賦課金単価 (円/kWh)」
この「賦課金単価」は、その年度に必要な買取費用の総額予測などに基づき、経済産業大臣が毎年決定します。
単価は全国一律であり、どの電力会社(大手電力会社でも新電力でも)と契約していても、同じ単価が適用されます。
したがって、電気を使えば使うほど、支払う賦課金の額も増える仕組みです。
なぜ高い? 単価高騰の理由
制度が始まった2012年度の賦課金単価は、1kWhあたり0.22円でした。
しかし、単価は年々上昇傾向にあり、2025年度には3.98円に達すると発表されています。
これは単純計算で10年以上で18倍近くに上昇したことになります。
なぜこれほど高騰しているのでしょうか。
最大の理由は、FIT制度によって再エネ(特に太陽光発電)の導入が想定を上回るペースで急速に普及したためです。
特に制度開始初期は、再エネを爆発的に増やすため、買取価格が非常に高く設定されました(例:事業用太陽光で1kWhあたり40円など)。
この高い価格での買取契約(20年間)が現在も続いており、買い取る電気の総量が増え続けているため、買取費用の総額が膨らみ続けているのです。
この増加する買取費用を賄うため、賦課金単価も上げざるを得ない状況が続いています。
(※2023年度に一時的に単価が下がりましたが、これはロシアのウクライナ侵攻による燃料価格高騰で「電力市場価格」が異常に高騰した結果、賦課金で補填する額が一時的に減ったという特殊要因によるものです。)
いつまで続く? 今後の見通し
では、この負担はいつまで続くのでしょうか。
現時点で、国から「再エネ賦課金は〇〇年に終了します」という明確な発表はありません。
FIT制度による電力の買取期間は10年または20年と定められています。
そのため、少なくともFIT制度で認定された発電所の買取期間が終了するまでは、賦課金の支払いが続くと予想されます。
多くの専門機関の試算によると、賦課金単価の負担のピークは「2030年頃」になると見られています。
2030年代に入ると、制度開始初期の高い買取価格が適用された発電所の買取期間が順次終了していくため、買取費用の総額が減少し、賦課金単価も徐々に下がっていくと予測されています。
参考動画
まとめ
再エネ賦課金は、日本のエネルギー政策を転換し、脱炭素社会やエネルギー自給率の向上を実現するために導入された、いわば「未来への投資」としての側面を持つ負担金です。
その一方で、年々増加する負担が家計や企業経営に重くのしかかっているのも事実です。
この負担のピークは2030年頃まで続くと予測されています。
私たち消費者にできる直接的な対策は、まず「節電」を心がけ、賦課金の計算の基となる「電気使用量(kWh)」そのものを減らすことです。
また、自宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社から買う電気を減らす(自家消費する)ことも、賦課金の負担を減らす上で非常に有効な手段となります(自家消費分には賦課金はかかりません)。
まずはご家庭の電気料金の明細を改めて確認し、自分が毎月いくら再エネ賦課金を支払っているのかを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
関連トピック
FIT制度(固定価格買取制度): 再エネ賦課金の根幹にある制度です。
再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で電力会社が買い取ることを保証する仕組みです。
FIP制度(フィードインプレミアム): 近年、FIT制度に代わって導入が進んでいる新しい制度です。
市場価格に一定の補助金(プレミアム)を上乗せする方式で、再エネ発電事業者の自立を促す狙いがあります。
再生可能エネルギー: 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、枯渇せず、発電時にCO2をほとんど排出しないエネルギー源の総称です。
エネルギー自給率: 日本は石油や天然ガスなどエネルギー資源の多くを輸入に頼っており、エネルギー自給率は非常に低い水準にあります。
再エネの普及は、この自給率を高める重要な鍵とされています。
関連資料
資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」: 経済産業省の公式ウェブサイトです。
FIT制度や再エネ賦課金の仕組み、最新の単価情報などが詳細に解説されています。
各電力会社のウェブサイト: ご契約中の電力会社のウェブサイトでも、電気料金の内訳として、再エネ賦課金の最新単価や計算方法が分かりやすく説明されています。
『いちばんやさしい「脱炭素」のキホン』(著:各種専門家): 再エネ賦課金の背景にある「脱炭素」や「カーボンニュートラル」といった世界の潮流について、基礎から学べる入門書籍が多数出版されています。