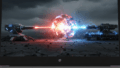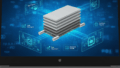暗号資産とステーブルコインはマネーロンダリングの温床か? 仕組みと規制の最前線「トラベルルール」を徹底解説。
概要
暗号資産(仮想通貨)は、その匿名性や国境を越えた送金の容易さから、残念ながらマネーロンダリング(資金洗浄)の手段として悪用されるケースが後を絶ちません。
犯罪組織や北朝鮮などの国家的な脅威が、不正に得た資金の出所を隠蔽するために暗号資産を利用していることは、世界的な安全保障上の問題となっています。
特に近年注目されているのが、ビットコインのような価格変動の激しい暗号資産ではなく、米ドルなどの法定通貨と価値が連動する「ステーブルコイン」の悪用です。
ステーブルコインは、犯罪収益の「価値の保存」と「安全な移転」という、マネーロンダリングにおいて極めて都合の良い特性を備えています。
この記事では、暗号資産とステーブルコインがどのようにしてマネーロンダリングに利用されるのか、その具体的な仕組みと、それに対抗するための国際的な規制「トラベルルール」について詳しく解説します。
詳細:暗号資産とマネーロンダリングの仕組み
マネーロンダリングの「仕組み」と暗号資産の役割
マネーロンダリングとは、犯罪などで得た「汚れた資金」の出所を隠し、正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけるプロセスを指します。
伝統的な金融システムでは、このプロセスは複雑な銀行送金やダミー会社を経由して行われます。
暗号資産は、このプロセス、特に資金の出所を曖昧にする「レイヤリング(分別)」の段階で非常に強力なツールとなります。
暗号資産の取引はブロックチェーン上に記録されますが、利用者は「ウォレットアドレス」という英数字の羅列で示され、現実の個人情報とは直接結びついていません。
犯罪者はこの「匿名性(正確には仮名性)」を利用します。
まず、不正な資金(ランサムウェアの身代金など)をビットコインなどで受け取ります。
次に、その資金の追跡を困難にするため、「ミキシングサービス(またはタンブラー)」と呼ばれる、複数の利用者の資金を混ぜ合わせて誰の資金かを分からなくするサービスを利用します。
あるいは、プライバシーコイン(モネロなど)と呼ばれる、取引の追跡が極めて困難な暗号資産に一度交換することもあります。
なぜ「ステーブルコイン」が特に危険なのか?
ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、価格変動(ボラティリティ)が非常に激しいという大きな特徴があります。
マネーロンダリングを行う犯罪者にとって、不正に得た1億円分のビットコインが、数日後に8000万円の価値になってしまうリスクは看過できません。
彼らは資金を「安全に」保持したいのです。
ここで登場するのが「ステーブルコイン」(USDTテザー、USDCなど)です。
ステーブルコインは、その価値が常に「1コイン=1米ドル」など、特定の法定通貨に連動(ペッグ)するように設計されています。
これにより、犯罪者は暗号資産の利便性を享受しつつ、価格変動のリスクを負うことなく、不正な資金を「デジタル・ドル」として安定的に保有できます。
さらに深刻なのは、「DeFi(分散型金融)」と呼ばれる領域の悪用です。
DeFiのプラットフォーム(DEX:分散型取引所など)は、銀行や中央集権型の暗号資産取引所とは異なり、管理者(仲介者)が存在しません。
そのため、利用者の本人確認(KYC)が不要な場合がほとんどです。
犯罪者は、ミキシングを経たビットコインを、KYC不要のDEXで「ステーブルコイン」に匿名で交換します。
この時点で、資金は「価値が安定したデジタル・ドル」に変換され、追跡は極めて困難になっています。
その後、このステーブルコインを複数のウォレットに分散させたり、規制の緩い国の取引所を通じて法定通貨に交換(キャッシュアウト)したりするのです。
ステーブルコインは、暗号資産を使ったマネーロンダリングの「中継地点」および「安全な資金プール」として、決定的な役割を果たしてしまっているのが現状です。
世界的な規制の包囲網:「トラベルルール」とは
こうした事態に対し、各国の規制当局も手をこまねいているわけではありません。
マネーロンダリング対策の国際的な基準を定める「FATF(ファトフ:金融活動作業部会)」は、暗号資産の送金に関して「トラベルルール」と呼ばれる規制を各国に導入するよう勧告しています。
これは、伝統的な銀行の国際送金で既に適用されているルールを、暗号資産の世界にも適用しようというものです。
具体的には、暗号資産交換業者(VASP)が顧客から依頼されて暗号資産の送金(出金)を行う際、送金依頼人と受取人の情報を正確に把握し、その情報を送金先の交換業者に通知することを義務付けるものです。
例えば、日本のA取引所から米国のB取引所へ暗号資産を送る場合、A取引所は「誰が、誰に、いくら送るのか」という情報をB取引所に伝えなければなりません。
これにより、暗号資産の取引が匿名で行われることを防ぎ、テロ資金供与やマネーロンダリングが疑われる取引を当局が追跡できるようにすることが目的です。
日本でも2023年6月から、このトラベルルールが施行されています。
しかし、このルールには大きな課題も残っています。
それは、規制の対象が「暗号資産交換業者」であるため、個人が管理する「プライベートウォレット(アンホステッド・ウォレット)」間の送金や、前述したDeFiプラットフォームの利用には、ルールが直接適用されにくい点です。
犯罪者は、規制された取引所を避け、これらの「規制の網の外」で活動を続けようとするため、規制当局と犯罪者の「いたちごっこ」は今後も続くと予想されます。
参考動画
まとめ
暗号資産、特にステーブルコインは、その技術的な利便性が皮肉にもマネーロンダリングの効率を高めるツールとして悪用されています。
ステーブルコインは、犯罪収益の「価値の安定化」と「移転の容易さ」を両立させてしまいました。
これに対し、国際社会は「トラベルルール」という統一基準で対抗しようとしていますが、DeFiやプライベートウォレットといった技術の進化が、規制の実施を複雑にしています。
暗号資産技術の革新性を守りつつ、いかにして金融システムの健全性と安全性を確保するか。
この両立は、今後も世界共通の重い課題であり続けます。
関連トピック
FATF (金融活動作業部会): マネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)の国際基準を策定する政府間機関。
トラベルルールの推進母体です。
DeFi (分散型金融): ブロックチェーン上で、中央集権的な管理者なしに金融サービス(取引、貸付など)を提供するエコシステム。
KYC(本人確認)がないことが多く、マネーロンダリングの温床となりやすいと指摘されています。
ミキシングサービス (ミキサー): 複数のユーザーの暗호資産を混ぜ合わせ、取引の追跡を困難にするサービス。
資金の「レイヤリング(分別)」に悪用されます。(例:Tornado Cashなど)
関連資料
Chainalysis 仮想通貨犯罪レポート: ブロックチェーン分析企業であるチェイナリシスが毎年発行するレポート。
暗号資産を利用したマネーロンダリングの最新の動向や被害額について、詳細なデータを提供しています。
FATF勧告(FATF Recommendations): FATFが各国に求めるマネーロンダリング対策の国際基準をまとめた文書。
トラベルルール(勧告16)もこの中に含まれます。
日本の改正資金決済法: 2023年の改正により、トラベルルールの実施が国内の暗号資産交換業者に義務付けられました。
FATFトラベルルールの究極コンプライアンスガイド この記事で解説した、暗号資産のマネーロンダリング対策の切り札である「FATFトラベルルール」について、その詳細とコンプライアンス(法令遵守)の方法を解説しているため、理解を深めるのに役立ちます。