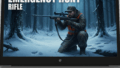トランプ関税とは? 第2次政権で日本にも15%発動! 米中貿易戦争から「一律関税」まで影響を徹底解説
「トランプ関税」の概要
トランプ関税とは、ドナルド・トランプ米大統領が、米国第一主義(アメリカ・ファースト)の公約に基づき、米国の産業保護と貿易赤字削減を目的に導入・提案している高率の関税(輸入品にかかる税金)政策の総称です。
2017年から2021年の第1次政権下で、中国製品や鉄鋼・アルミニウムに対して高関税を課し、「米中貿易戦争」と呼ばれる激しい貿易摩擦を引き起こしました。
2025年1月に第2次トランプ政権が発足して以降、この政策は「トランプ関税2.0」とも呼ばれ、さらに強力に推進されています。
選挙公約であった「全世界からの輸入品への一律10%関税」や「中国製品への60%以上の関税」を背景に、2025年8月には日本からの輸入品にも15%の関税を発動するなど、世界経済に再び大きな影響を与えています。
「トランプ関税」の詳細
第1次トランプ政権の関税(2017年~2021年)
トランプ氏の関税政策は、第1次政権時代に本格化しました。
主な目的は、長年の貿易赤字、特に中国との不均衡を是正することでした。
- 鉄鋼・アルミニウム関税(2018年): 「米国の安全保障上の脅威」であるとして、通商拡大法232条に基づき、日本やEUを含む多くの国々の鉄鋼・アルミニウム製品に高関税を課しました。
- 米中貿易戦争(2018年~): 「中国による知的財産権の侵害」や「不公正な貿易慣行」を理由に、1974年通商法301条に基づき、中国製品に対して段階的に高率の追加関税(最大25%など)を発動しました。中国も即座に報復関税で応じたため、世界第1位と第2位の経済大国による関税の応酬合戦となり、世界経済に大きな打撃を与えました。
第2次トランプ政権の公約と実行(2025年~)
2024年の大統領選挙キャンペーン中から、トランプ氏は第1次政権を超える強力な関税政策を公約していました。
- 選挙公約: 全ての輸入品に対して一律10%の「ユニバーサル・ベースライン関税」を課すこと。さらに、中国からの輸入品には60%以上、あるいは100%といった超高率の関税を課す可能性を示唆していました。
- 「トランプ関税2.0」の実行:
- 2025年1月就任直後: 第2次政権が発足し、公約の実行に向けた大統領令や法的根拠(国際緊急経済権限法:IEEPAなど)の準備が進められました。
- 2025年8月・日本への関税発動: 2025年8月1日、日本から輸入される製品(自動車や機械などを含む広範囲)に対し、15%の関税措置が発動されました。
- 対中政策の強化: 中国に対しては、第1次政権時の関税を維持・強化する姿勢を鮮明にし、2025年10月には100%の追加関税を示唆するなど、米中間の緊張は再び最高潮に達しています。
- カナダ・メキシコへの圧力: 北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の見直しも示唆し、メキシコやカナダに対しても25%の関税措置を発表(2024年11月)するなど、圧力を強めています。
トランプ関税の影響
この高関税政策は、米国、日本、そして世界経済全体に甚大な影響を及ぼしています。
- 日本経済への影響:
- 帝国データバンクの調査(2025年)によれば、トランプ関税の影響を受ける日本企業は「自動車」や「機械」産業を中心に約1万3,000社に上るとされています。
- 具体的な影響として「原材料コストの上昇」「売上の減少」が挙げられ、日本国内の企業倒産件数が従来の予測より3%以上増加する可能性が指摘されています。
- 米国経済への影響:
- 輸入品の価格が上昇するため、米国内のインフレーション(物価上昇)を加速させる要因となります。
- 消費者の負担が増え、実質GDP(経済成長率)を押し下げるマイナス効果も試算されています。一方で、関税による税収は増加します。
- 世界経済への影響:
- 各国が米国の関税に対抗して報復関税を発動すれば、世界的な貿易戦争に発展し、国際貿易が縮小します。
- これにより、グローバルなサプライチェーン(部品調達・供給網)が混乱し、世界経済全体が下振れする大きなリスクとなっています。
「トランプ関税」の参考動画
「トランプ関税」のまとめ
トランプ関税は、「アメリカ・ファースト」の理念に基づき、米国の国内産業を守ることを最優先する保護主義的な通商政策です。
第1次政権での米中貿易戦争を経て、第2次政権ではその対象を日本を含む全世界に拡大し、より強硬な「トランプ関税2.0」として実行されています。
すでに日本企業にも15%の関税が発動しており、自動車産業をはじめとする輸出企業は深刻な打撃を受けています。
この政策は、米国内の物価上昇という副作用を伴う一方で、世界経済の秩序を大きく揺るがす不確実性の中核となっています。
日本企業や私たち個人は、この世界的な経済環境の変化に対応するため、今後の米国の動向や為替の変動に、これまで以上に注意を払う必要があります。
関連トピック
米中貿易戦争: 第1次トランプ政権下で激化した、米国と中国による関税の報復合戦です。トランプ関税の象徴的な出来事とされています。
保護主義(Protectionism): 輸入を制限(高関税、輸入数量制限など)することで、自国の産業を外国との競争から保護しようとする貿易政策の考え方です。
アメリカ・ファースト(米国第一主義): トランプ大統領の政治スローガンであり、外交、経済、通商などあらゆる政策において米国の国益を最優先する考え方です。
通商拡大法232条: 外国からの輸入が「米国の国家安全保障を脅かす」と判断された場合に、大統領権限で関税や輸入制限を発動できる米国の法律です。第1次政権の鉄鋼・アルミ関税で使われました。
1974年通商法301条: 他国の「不公正な貿易慣行」に対して、米国が一方的に制裁(追加関税など)を課すことを認める法律です。第1次政権の対中関税の主な根拠となりました。
サプライチェーン: 製品が原材料の調達から製造、在庫管理、物流、販売を経て消費者に届くまでの連鎖的な流れのことです。トランプ関税はこれを世界的に混乱させています。
インフレーション(物価上昇): 輸入品の価格が関税によって上昇することで、国全体の物価が上がることです。トランプ関税の副作用の一つとされています。
関連資料
シンクタンク(経済研究所)のレポート: 大和総研、ニッセイ基礎研究所、アジア経済研究所などが、トランプ関税の影響について詳細な分析レポート(試算)を公開しています。
帝国データバンク等の調査レポート:
中小企業庁の関連資料: トランプ関税(2.0)などの影響を受ける中小企業を対象とした、補助金(ものづくり補助金など)や支援策に関する資料。