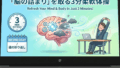日本における諜報活動と国家安全保障戦略:外交特権の壁と「強力な対抗策」に関する包括的分析報告書
序論:東アジアの安全保障環境と「スパイ天国」の汚名
1.1 変容する脅威のランドスケープ:中国・ロシアによるインテリジェンス攻勢
21世紀の東アジアにおける地政学的緊張の高まりは、伝統的な軍事力による抑止の枠組みを超え、情報、経済、技術が複雑に絡み合う「ハイブリッド戦争」の様相を呈している。日本は、世界最高水準の半導体技術、ロボティクス、量子コンピューティングなどの先端技術を有すると同時に、米国の最も重要な同盟国としてインド太平洋地域の要衝に位置している。この地政学的・技術的価値ゆえに、日本は外国情報機関(FIS: Foreign Intelligence Services)、とりわけ中国の国家安全部(MSS)や人民解放軍(PLA)、ロシアの対外情報庁(SVR)や軍参謀本部情報総局(GRU)による激しい諜報活動の標的となっている。
かつて冷戦期において、スタニスラフ・レフチェンコ(KGB少佐)が日本を「スパイ天国」と評したことはあまりに有名である。この汚名は、日本に包括的な「スパイ防止法(対スパイ法)」が存在せず、諜報活動そのものを直接的に処罰する法的枠組みが欠如していた事実に起因する。しかし、現代の脅威は当時より遥かに複雑化している。スパイ活動は、かつてのような政治情報の収集だけでなく、民間企業の知的財産(IP)奪取、学術機関への浸透、そしてサイバー空間を通じた重要インフラへの攻撃へと拡大している。
1.2 問題の核心:「スパイ防止法」とウィーン条約の法的ジレンマ
本報告書が対峙する中心的な問いは、日本の防諜(カウンター・インテリジェンス)能力に関する根本的な懸念である。すなわち、「日本国内で活動する中国やロシアのスパイに対し、仮に『スパイ防止法』を制定したとしても、彼らが外交官身分(ディプロマティック・カバー)を有している場合、現行犯であっても逮捕できず、大使館(公館)に逃げ込まれ、最終的には国外へ逃亡されてしまうのではないか」という法的・実務的なジレンマである。
結論から述べれば、この懸念は国際法上、極めて正確である。1961年の「外交関係に関するウィーン条約」は、外交官に対して受入国の刑事裁判権からの完全な免除(不逮捕特権)を保障しており、公館の不可侵権も認めている。したがって、国内法であるスパイ防止法がいかに厳罰化されようとも、条約上の特権を有する外交官を逮捕・拘束することは、国際法違反となるリスクを冒さない限り不可能である。
しかし、これは日本が「無力」であることを意味しない。本報告書では、逮捕という「司法的手法」が封じられた状況下において、日本政府が取りうる「強力な対抗策」とは何かを詳細に分析する。具体的には、2024年に成立したセキュリティ・クリアランス制度、2025年に可決された能動的サイバー防御法といった新たな法的ツールに加え、外交的追放(ペルソナ・ノン・グラータ)、移動制限、ビザ発給の厳格化といった行政的・外交的措置(Administrative and Diplomatic Measures)の有効性を検証する。
第1部:脅威の解剖学 ― 日本国内における諜報活動の実態
対抗策を論じる前に、敵対的情報機関が日本国内でどのように活動しているか、その手口(Modus Operandi)を正確に分類する必要がある。対応策は、スパイが「合法的身分(Official Cover)」を持っているか、「非合法的身分(Non-Official Cover)」であるかによって劇的に異なるからである。
2.1 「リーガル(合法)」スパイの活動実態:外交官カバーの脅威
ロシアの情報機関(SVR、GRU)は、伝統的に大使館、領事館、通商代表部といった公的機関に所属する外交官や職員としての身分(カバー)を利用することを好む。彼らは外交パスポートを持ち、ウィーン条約に基づく特権免除(Immunity)を享受しながら活動する。これをインテリジェンス用語で「リーガル(Legal)」と呼ぶが、その活動内容は当然ながら違法な諜報活動である。
彼らの主な手法はHUMINT(人的諜報)である。ターゲットとなる日本人(官僚、企業社員、研究者)に対し、最初は身分を隠して接触し、食事や接待を通じて人間関係を構築する。その後、公開情報の提供から徐々に非公開情報の要求へとエスカレートさせ、金銭授受や脅迫を通じて協力者(エージェント)に仕立て上げる。この際、万が一発覚しても、彼ら自身は外交特権を盾に逮捕を免れることができるという「安全装置」が、大胆な工作活動を可能にしている。
2.2 「イリーガル(非合法)」スパイと学術・産業スパイ:非公式カバーの浸透
一方で、中国の諜報活動はより多様かつ分散的である。外交官カバーも使用するが、それ以上に特徴的なのが「非公式カバー(NOC: Non-Official Cover)」の多用である。留学生、研究者、エンジニア、ジャーナリスト、ビジネスマンといった一般人の身分で入国し、活動する。
特に懸念されているのが、学術機関や研究機関への浸透である。中国の「千人計画」に代表される人材招致プログラムを通じ、日本の国立研究所や大学に所属する研究者が、日本の公的研究資金で得た成果を中国側に流出させるケースが後を絶たない。これらのアクターは外交官ではないため、外交特権を持たない。したがって、日本の国内法(不正競争防止法など)による摘発・逮捕が可能であり、実際に逮捕者がでている領域である。
2.3 サイバー領域における「見えざる戦争」:国家支援型ハッカー集団
第三の、そして最も急速に拡大している脅威がサイバー・エスピオナージである。中国の「APT40」「MirrorFace」、北朝鮮の「Lazarus」、ロシアの「APT28」などの国家支援型ハッカー集団は、物理的に日本に入国することなく、国境を越えて日本の政府機関や重要インフラ、防衛産業のサーバーに侵入し、機密情報を窃取する。
この領域では「外交特権」や「大使館への逃げ込み」は無意味である。攻撃者は海外(自国や第三国)に位置しており、日本の警察権が及ばない場所にいる。ここでの課題は「逮捕」ではなく、「特定(アトリビューション)」と「無力化(ニュートラライゼーション)」である。これに対応するために整備されたのが、後述する「能動的サイバー防御法」である。
第2部:法的障壁の分析 ― 外交特権(Diplomatic Immunity)の絶対性
「現行犯であっても逮捕できないのか?」という問いに対し、国際法の観点から詳細に回答する。
3.1 ウィーン外交関係条約の鉄則:身体の不可侵と裁判権の免除
外交官の特権免除に関する国際的な基本ルールは、1961年に採択された「外交関係に関するウィーン条約(Vienna Convention on Diplomatic Relations)」によって定められている。日本も締約国であり、国内法よりも条約が優越する憲法構造上、この規定を遵守する義務がある。
- 身体の不可侵(第29条):「外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法による抑留又は拘禁も受けない。」
この規定は絶対的である。たとえスパイ活動の現行犯であっても、殺人現場であっても、受入国の法執行機関(警察・公安)は、外交官の身分証明書(ID)を確認した時点で、その身体を拘束し続けることはできない。手錠をかけることも、警察署へ連行して取調べることも条約違反となる。 - 刑事裁判権の免除(第31条):「外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享受する。」
これにより、日本の検察は外交官を起訴することができない。スパイ防止法が存在し、死刑や無期懲役を含む重罰が規定されていたとしても、外交官には適用されない(起訴できないため)。
例外として、派遣国(ロシアや中国)が特権を「放棄(Waiver)」する場合(第32条)があるが、国家の命令でスパイ活動を行っている諜報員について、本国が特権を放棄することはあり得ない。それは国家としてのスパイ行為を認めることになるからである。
3.2 「大使館への逃げ込み」は防げるか:公館の不可侵権と現実
質問にある「大使館に逃げ込まれ」というシナリオも、条約第22条「公館の不可侵」によって裏付けられている。
「公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長の同意がある場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。」
日本の警察は、令状があっても外国の大使館敷地内に踏み込むことはできない。スパイ容疑者が大使館の門をくぐってしまえば、そこは事実上の聖域(サンクチュアリ)となり、日本の主権行使(逮捕権)は物理的に遮断される。また、外交官の個人の住居(第30条)や、外交官の文書・通信・財産(第30条2項)も同様に不可侵である。
3.3 ペルソナ・ノン・グラータ(PNG)のメカニズムと限界
では、日本政府になす術はないのか。条約が用意している唯一かつ最大の対抗措置が、第9条に基づく「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」の通告である。
- 通告: 受入国(日本)は、いつでも、理由を示さずに、外交官をペルソナ・ノン・グラータとして通告できる。
- 義務: 通告を受けた派遣国(ロシア等)は、その外交官を召喚(帰国)させるか、任務を終了させなければならない。
- 拒否した場合: もし派遣国が相当の期間内にこれを行わない場合、受入国はその人物を外交官として認めることを拒否できる。これにより特権免除が剥奪され、理論上は逮捕が可能になる。
現実のインテリジェンスの攻防では、PNG通告(あるいは水面下での自主的退去勧告)が行われると、派遣国は逮捕されるリスクを避けるために直ちに当該スパイを帰国させる。読者が懸念する「国外脱出」は、このプロセスを通じて合法的に行われる。これは「逃げ得」に見えるが、カウンター・インテリジェンスの観点からは「敵対的活動分子の無力化・排除」という目的は達成されたことになる。
第3部:事例研究 ― 諜報事案における司法と外交の限界
具体的な事件を通じて、外交特権の壁と、非外交官に対する処罰の実際を検証する。
4.1 ロシア通商代表部職員によるソフトバンク機密情報漏洩事件(2020年・2022年)
この事件は、外交特権を持つスパイと持たない協力者の運命の残酷な対比を示している。
- 概要: 2020年、ソフトバンクの元社員(荒木豊)が、ロシア通商代表部の職員(アントン・カリニン副代表、後に別の職員も関与)に唆され、社外秘の通信設備情報を渡した事件。
- 手口: ロシア側は、最初は飲食店での接待を通じて接近し、徐々に資料提供を求めて金銭を渡すという典型的なスパイ勧誘(Human Intelligence Recruitment Cycle)を行った。
- 結末:
- 日本人社員: 警視庁公安部に逮捕され、不正競争防止法違反で有罪判決を受けた。
- ロシア外交官: 警視庁は出頭要請を行ったが、ロシア側は外交特権を盾に拒否。カリニンらは事情聴取に応じることなく、成田空港から堂々と帰国(事実上の国外逃亡)した。
教訓: この事例は、現行法下でも、また仮にスパイ防止法があったとしても、外交官身分のスパイを処罰することは不可能であり、彼らが「国外脱出」することを防げない現実を浮き彫りにした。一方で、日本人の協力者は厳しく処罰されるため、スパイ防止法の主たる抑止効果は「日本国民」に向けられることになる。
4.2 産総研(AIST)中国人研究員による技術流出事件(2023年-2024年)
一方、外交官以外のスパイ活動に対しては、日本の警察力は有効に機能する。
- 概要: 国立研究開発法人「産業技術総合研究所(AIST)」の主任研究員であった中国籍の権恒道(Quan Hengdao)が、フッ素化合物の合成技術に関する研究データを中国企業に漏洩した事件。
- 背景: 権容疑者は、日本の公的機関に所属しながら、中国の「国防七校」の一つである北京理工大学の教授も兼任しており、中国の国家プロジェクト(千人計画等)に関与していた疑いが持たれた。
- 結末: 彼は外交官ではないため、特権免除は適用されない。警視庁公安部は彼を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)で逮捕・起訴した。2025年時点の報道によれば、公判が進んでいる(または有罪判決が見込まれる)。
教訓: 中国の諜報活動の多くを占める「非公式カバー(研究者、技術者)」に対しては、国内法の整備と適用強化が極めて有効である。彼らには「大使館への逃げ込み」というオプションは存在しない。
4.3 事例から読み解く「処罰の非対称性」
これらの事例から導き出される結論は、日本の防諜活動における「処罰の非対称性」である。
- 外交官スパイ: 逮捕不可。対抗策は「国外追放(PNG)」のみ。
- 非外交官外国人・日本人協力者: 逮捕可能。国内法の厳罰化が直接的な抑止力となる。
したがって、スパイ防止法制定の議論においては、「外交官を逮捕できないから無意味だ」という批判は一面的である。同法は、スパイ活動の実働部隊である非外交官や、情報源となる日本人に対する強力な抑止力として機能するからである。
第4部:立法による対抗策 ― 「スパイ防止法」とその補完機能
読者が問う「スパイ防止法」の現状と、それに代わる、あるいはそれを補完する「強力な法的対抗策」について詳述する。
5.1 「スパイ防止法」制定の歴史的経緯と現代的意義
日本では1985年、自民党によって「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案(スパイ防止法案)」が国会に提出されたことがある。これは、宮永スパイ事件(自衛隊高官によるソ連への情報漏洩)を契機としたものであったが、報道の自由や国民の知る権利を侵害する恐れがあるとして廃案となった。
現在、高市早苗氏をはじめとする保守派議員や、参政党、国民民主党などがスパイ防止法の制定を提言している。
- 目的: 現行法(特定秘密保護法、自衛隊法、公務員法、不正競争防止法)ではカバーしきれない「広範な国家機密」の漏洩や、非公務員によるスパイ行為を直接処罰すること。
- 現状: 特定秘密保護法(2013年成立)により、防衛・外交・テロ・スパイ防止の4分野については最高懲役10年の厳罰化が図られたが、経済安全保障やサイバー分野、あるいは「重要だが特定秘密指定されていない情報」の保護には空白がある。
5.2 経済安全保障推進法とセキュリティ・クリアランス(適性評価)制度
スパイ防止法が存在しない空白を埋める「実質的なスパイ対策」として、2024年に「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(セキュリティ・クリアランス法)」が成立し、2025年から施行段階に入っている。これは、外交特権に阻まれる「スパイの逮捕」ではなく、「スパイへの情報遮断」を狙った強力な予防策である。
- 制度の概要: 政府が保有する経済安全保障上の重要情報(Cyber, Supply Chain, Infrastructure等)にアクセスできる者を、政府が事前に調査(Vetting)し、信頼できる人物に限定する制度(Security Clearance)。
- 調査内容: 対象者の犯罪歴、薬物使用歴、借金状況、精神疾患、そして「外国との結びつき」が徹底的に調査される。配偶者や同居人の国籍も調査対象となる。
- 対抗策としての効果:
- リクルートの困難化: 外国情報機関が日本人研究者や技術者を勧誘しようとしても、クリアランス保持者は定期的に身辺調査を受けるため、不審な接触や金銭授受が発覚するリスクが極めて高くなる。
- 処罰の強化: クリアランス保持者が情報を漏洩した場合、5年以下の拘禁刑などの罰則が科される。これにより、産業スパイ行為に対する抑止力が飛躍的に向上した。
5.3 能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)法の衝撃
2025年5月、日本の国会は「能動的サイバー防御(Active Cyber Defense: ACD)法」(正式名称:サイバー対応能力強化法等)を可決した。これは日本の防衛政策、特に憲法9条と専守防衛の解釈における歴史的な転換点であり、サイバー・スパイに対する最も「強力な」物理的・技術的対抗策である。
- 通信の監視: 政府(および委託された機関)は、日本の重要インフラや政府機関を守るため、通信事業者のネットワークを流れるメタデータや通信内容を監視し、攻撃の兆候を探知することが法的に可能となった。これには、憲法が保障する「通信の秘密」との調整が含まれる。
- サーバーの無力化(Neutralization): 最大の特徴は、攻撃者が使用している海外のサーバーやボットネットに対し、自衛隊や警察のサイバー部隊が侵入し、データを削除したり機能を停止させたりする「無力化措置」を認めた点である。
- 対スパイ効果: 例えば、ロシアの外交官が第三国のサーバーを経由して日本の機密情報を盗み出そうとしている場合、日本政府はその外交官を逮捕できなくとも、その攻撃インフラ(サーバー)をハッキングして破壊することができる。これは、外交特権の壁を技術的に迂回し、スパイ活動そのものを物理的に阻止する極めて強力な実力行使である。
第5部:行政・外交による「強力な対抗策」 ― 拒否と撹乱の戦略
逮捕できない外交官スパイに対して、日本政府が現在実行している、あるいは強化しつつある行政的・外交的な対抗措置(ツールボックス)について解説する。
6.1 入国管理の厳格化と「ビザ戦争」:水際での阻止
スパイを国内に入れなければ、大使館への逃げ込みも発生しない。日本政府は水際対策を強化している。
- インテリジェンス・オフィサーのスクリーニング: 法務省出入国在留管理庁と外務省は、警察庁や公安調査庁、さらには同盟国(Five Eyes)からの情報提供に基づき、既知の諜報員リスト(ウォッチリスト)を共有している。ビザ申請段階で、諜報機関との関連が疑われる人物の入国を拒否する運用が強化されている。
- JESTA(日本版ESTA)の導入: 日本政府は、ビザ免除対象国からの渡航者に対し、事前にオンラインで渡航認証を取得させる「JESTA」の導入を2028年度を目処に進めている(一部報道では前倒しの可能性)。これにより、観光客を装ったスパイの入国を事前に審査し、阻止する能力が向上する。
- 学術・研究分野の審査厳格化: 中国人留学生や研究者に対するビザ発給審査において、軍事転用可能な技術に関連する経歴を持つ人物への審査が厳格化されている。これは米国の施策に追随するもので、経済安全保障の一環として実施されている。
6.2 国内移動制限(トラベル・リストリクション):25マイルルールの適用
スパイ活動(特にHUMINT)には、情報提供者と密会するための移動の自由が不可欠である。これを制限することで、活動を物理的に封じ込めることができる。
- 相互主義に基づく制限: 米国はロシア外交官に対し、大使館から半径25マイル(約40km)以遠への移動に事前通告義務を課している。日本もロシアとの関係において相互主義の原則に基づき、ロシア外交官の国内移動に対する監視や制限を強化するカードを持っている。
- 効果: 外交官が東京から離れた地方都市やリゾート地で協力者と接触しようとしても、移動制限があれば公安警察の追尾・監視が容易になり、秘密裏の接触が困難になる。事実上、スパイ活動の「足」を奪う強力な措置である。
6.3 外交的追放(Expulsion)の積極活用と戦略的効果
「現行犯逮捕」ができなくとも、日本政府は「ペルソナ・ノン・グラータ(PNG)」を通告し、強制的に国外退去させることができる。かつて日本は報復を恐れてこの措置に消極的だったが、近年その姿勢は変化している。
- 2022年の大量追放: ロシアによるウクライナ侵攻を受け、日本政府は2022年4月、駐日ロシア大使館の外交官ら8名を「ペルソナ・ノン・グラータ」として追放した。これは日本の外交史上極めて稀な強力措置であった。
- 諜報網の破壊: 外交官の追放は、単なる政治的メッセージではない。情報機関にとって、現地語に精通し、協力者網を構築したベテラン・ケースオフィサー(工作担当者)を失うことは、作戦能力への致命的な打撃となる。後任者の育成と配置には数年単位の時間が必要となるため、組織的なスパイ活動を長期間麻痺させることができる。
6.4 パブリック・アトリビューション(公的帰属表明):ネーミング・アンド・シェイミング
サイバー攻撃やスパイ活動の主体を特定し、公に非難する「パブリック・アトリビューション」も、近年日本が採用し始めた強力な対抗策である。
- 「名指し」の効果: 2024年、警察庁は中国共産党に関連するハッカー集団「BlackTech」や「MirrorFace」による攻撃を特定し、注意喚起を行った。また、外務省は中国政府が関与する「APT40」に対する非難声明に加わった。
- 抑止のメカニズム: スパイ活動は秘匿性を生命線とする。国家が公式に「お前の正体はバレている」と公表することは、相手の情報機関に対して「その手口はもう通用しない」「その組織はマークされている」というメッセージを送り、作戦の放棄や戦術の変更を強いる効果がある。
結論と提言:多層的な防諜体制の構築に向けて
読者の懸念に対する最終的な回答と、今後の展望をまとめる。
結論:逮捕できなくとも「無力化」は可能である
「スパイ防止法を制定しても、外交官は大使館に逃げ込み、国外脱出してしまうのではないか」という懸念は、法的観点からは正しい。ウィーン条約が存在する限り、外交官身分のスパイに手錠をかけることはできない。
しかし、「逮捕できない=対抗策がない」ではない。現代のカウンター・インテリジェンスの目的は、必ずしもスパイを刑務所に入れることではなく、「情報の流出を阻止し、敵対的活動を無効化すること」にある。その観点から見れば、日本は既に以下の強力な対抗策を講じ、あるいは整備しつつある。
- ターゲットの硬化(Hardening): 「セキュリティ・クリアランス法」により、日本側の協力者(アクセス・エージェント)に対する監視と罰則を強化し、スパイが情報を入手するルートを遮断する。
- インフラの破壊(Disruption): 「能動的サイバー防御法」により、外交特権に関係なく、スパイ活動に使用されるサーバーや通信インフラを直接無力化(ハッキング)する。
- 物理的排除(Expulsion): スパイ行為が発覚した場合、躊躇なく「ペルソナ・ノン・グラータ」を発動し、国外へ追放することで諜報ネットワークを物理的に破壊する。
- 非外交官への厳格な法適用: 産総研事件のように、特権を持たない研究者や民間人スパイに対しては、既存法や将来のスパイ防止法を適用して厳正に逮捕・訴追する。
今後の課題:日本版インテリジェンス・コミュニティの強化
これらの対抗策をさらに実効的なものにするためには、組織面の改革が急務である。現在、日本の防諜活動は警察庁(警備局・公安部)、公安調査庁(PSIA)、内閣情報調査室(CIRO)、防衛省情報本部などに分散している。
- 公安調査庁の権限強化: 公安調査庁は情報収集を行うが、逮捕権(捜査権)を持たない。英国のMI5のように、防諜機関としての権限を強化し、サイバー空間を含む広範な監視権限を付与する議論が進んでいる。
- 通信傍受の拡大: スパイ摘発の端緒を掴むためには、通信傍受(Wiretapping)の要件緩和が不可欠との指摘がある。現行の通信傍受法は薬物犯罪や組織犯罪に限定されており、スパイ活動への適用はハードルが高い。スパイ防止法制定とセットで、憲法上の「通信の秘密」との整合性を図りつつ、国家安全保障目的の通信監視を可能にする法整備が、残された「最後のピース」となるであろう。
日本は今、「スパイ天国」からの脱却を図り、法制度、サイバー能力、外交姿勢のすべてにおいて、能動的かつ攻撃的な防諜体制へと大きく舵を切っている。外交特権という壁は残るものの、それを包囲する多層的な防御網は、かつてないほど強固になりつつある。
| スパイの属性 | 主要な活動主体 | 外交特権 | 逮捕・訴追 | 主要な対抗策(Neutralization Methods) |
|---|---|---|---|---|
| 外交官 (Legal) | ロシア (SVR, GRU) 中国 (一部) |
あり | 不可能 | ・ペルソナ・ノン・グラータ(追放) ・移動制限(25マイルルール) ・日本人協力者の摘発によるネットワーク遮断 |
| 非公的カバー (Illegal) | 中国 (研究者, 学生, 企業人) ロシア (一部) |
なし | 可能 | ・不正競争防止法、スパイ防止法での逮捕 ・セキュリティ・クリアランスによる排除 ・ビザ発給拒否、入国禁止 |
| サイバー攻撃者 | 中国 (APT40等) 北朝鮮 (Lazarus) |
N/A (国外) | 困難 (国外) | ・能動的サイバー防御(サーバー無力化) ・パブリック・アトリビューション(公開特定) ・通信遮断 |
| 日本人協力者 | 官僚、研究者、企業社員 | なし | 可能 | ・特定秘密保護法、クリアランス法での厳罰化 ・身辺調査(Vetting)による事前排除 |
| 発生年 | 事件名 | 関与国 | スパイの身分 | 結末(日本側の対応) | 教訓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ソフトバンク機密漏洩事件 | ロシア | 通商代表部職員(外交官) | 職員は出頭拒否し帰国。日本人社員は逮捕・有罪。 | 外交特権の壁により主犯(スパイ)は逃亡。協力者への打撃で対処。 |
| 2022 | 在日ロシア外交官追放 | ロシア | 大使館・通商代表部職員 | 8名をペルソナ・ノン・グラータとして追放。 | ウクライナ侵攻を受けた外交的制裁だが、実質的な防諜措置。 |
| 2023 | 産総研(AIST)データ流出事件 | 中国 | 主任研究員(非外交官) | 権恒道容疑者を不正競争防止法違反で逮捕・起訴。 | 非外交官には日本の警察権が及ぶ。学術スパイ対策の重要性。 |
| 2024 | 精密機器メーカー機密漏洩 | ロシア | 通商代表部職員(元) | 元職員に出頭要請(事実上逃亡)。日本人元社員を書類送検。 | 依然として「外交官カバー×日本人抱き込み」の手法が主流。 |
参考文献・関連リンク
- JAPANESE BEGIN DEBATE ON BILL TO OUTLAW SPYING ON GOVERNMENT – CIA
- Foreign Influence in Japan: Lessons from the UK, US and Australia – RUSI
- Takaichi to Begin Consideration of Anti-Spy Law Within the Year: A Major Turning Point in Japan’s Security Policy – WORLD INSIGHT
- Diplomatic immunity – Wikipedia
- Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 – OFFICE OF LEGAL AFFAIRS
- Japan Approves Bill to Make Crucial Economic Security Information Classified
- Japan’s new Active Cyber Defense Law: A Strategic Evolution in National Cybersecurity
- Diplomatic expulsions during the Russo-Ukrainian war – Wikipedia
- Former Russian Trade Staffer Accused of Espionage; Allegedly Received Confidential Information From Machinery Firm Staffer – The Japan News
- Alleged Tech Leak to China ‘Just the Tip of the Iceberg’ | JAPAN Forward
- Chinese intelligence activity abroad – Wikipedia
- Overview of Threats in Cyberspace
- Japan Leading the Way With Proactive Cybersecurity Strategies – Remedio
- Diplomatic immunity | Research Starters – EBSCO
- Espionage and the Forfeiture of Diplomatic Immunity – SMU Scholar
- Russian diplomat in Softbank spying case leaves Japan – ARAB NEWS
- Scientist at Tsukuba’s AIST Arrested for Allegedly Passing on Research Data to Chinese Firm – TsukuBlog
- Chinese court sentences a Japanese man to more than 3 years in prison on espionage charges – AP News
- New Japanese Espionage Law Would Need to Respect Rights
- Japan begins studying law against spies – Nation Thailand
- Japan begins studying law to prevent foreign entities from stealing information
- The Cabinet approves a bill to build a “security clearance system:” Enabling a wider range of collaboration in cutting-edge fields and penalizing leakage of critical security information | Science Japan
- Japan Legal Update : Establishment of a Security Clearance System in the Economic Security Sector | Anderson Mori & Tomotsune
- Japan Cabinet OKs bill on new economic ‘security clearance’ system
- Remaining Challenges for Operationalizing Japan’s Information Security Legislation
- The Active Cyber Defense Law — Japan’s National Security Enters
- Japan’s Active Cyber Defense Law: AEV & Resilience – SafeBreach
- Japan’s ‘Active Cyber Defence’ Strategy – Cyber Security Intelligence
- JAPAN: CONTROLLING TECHNOLOGY LEAKAGE TO USSR – CIA
- Japan to tighten visa screenings of foreign students, researchers to prevent tech theft
- Visa Screening for Foreign Nationals Moved Up to 2028 | JAPAN Forward
- Is US Restricting Russian Diplomats’ Travel? – VOA
- Expulsion of diplomats and officials from the Embassy of the Russian Federation and the Trade Representation of the Russian Federation in Japan | Ministry of Foreign Affairs of Japan
- Japan Goes on Offense With New ‘Active Cyber Defense’ Bill – Dark Reading
- Public Security Investigation Agency [Koancho]
- JIIA Strategic Comments (2025-14) Strengthening Intelligence as a Component of Japan’s National Power | Research Findings
- Systematic government access to private-sector data in Japan – Oxford Academic
- Japanese Lawmaker Says Anti-Spy Law Could End Oshikatsu Culture – Unseen Japan