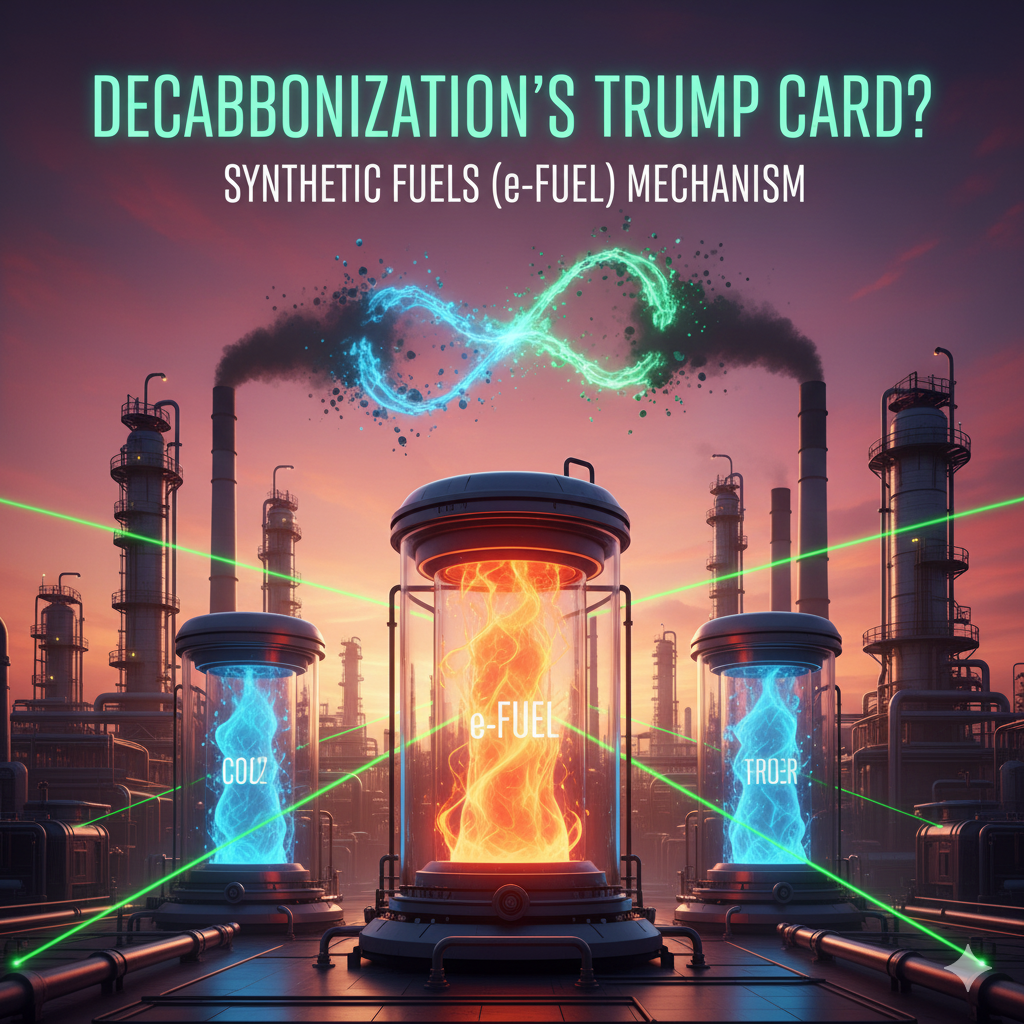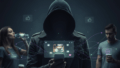🚗脱炭素の切り札か?「合成燃料(e-fuel)」の仕組み、メリット、日本の普及に向けた課題を徹底解説
「合成燃料(e-fuel)」の概要
合成燃料、またはe-fuel(イーフューエル)とは、「CO2(二酸化炭素)とH2(水素)を主な原料として人工的に合成される液体燃料の総称」です。
これは、化石燃料であるガソリンや軽油、ジェット燃料と化学構造が非常に近いため、既存の内燃機関(エンジン)や燃料インフラをそのまま利用できるという革新的な特徴を持っています。
合成燃料が脱炭素の切り札として注目される理由は、製造時に大気中や工場から回収したCO2を利用するため、燃焼時にCO2を排出しても差し引きで大気中のCO2濃度を増やさない**「カーボンニュートラル」**を実現できる点にあります。
特に、電気自動車(EV)への転換が難しい**航空機、船舶、大型トラック**などの分野で、脱炭素化を促進する有力な手段として期待されています。
「合成燃料」の詳細
合成燃料の基本的な製造プロセス(FT合成)
合成燃料の製造プロセスは、主に以下の3つのステップを経て行われます。
1. 原料の調達(CO2回収とクリーン水素製造)
合成燃料の原料となるCO2は、発電所や工場から排出される排ガスから回収されるか、**DAC(Direct Air Capture)**と呼ばれる技術を用いて大気中から直接回収されます。
もう一つの原料である水素(H2)は、再生可能エネルギー由来の電力を使って水を電気分解することで製造される**グリーン水素**であることが、カーボンニュートラルの大前提です。
2. 合成ガスの製造とFT合成(フィッシャー・トロプシュ反応)
回収したCO2とH2を反応させることで、**合成ガス(一酸化炭素COと水素H2の混合ガス)**を製造します。
次に、この合成ガスに特殊な触媒を作用させ、**フィッシャー・トロプシュ(FT)合成**と呼ばれる化学反応を起こします。
このFT合成によって、合成粗油と呼ばれる長鎖の炭化水素(人工的な原油)が生成されます。
3. 製品化(アップグレーディング)
最後に、合成粗油を精製・加工(アップグレーディング)することで、ガソリン、軽油、ジェット燃料(SAF)など、様々な用途に適した液体燃料に製品化されます。
このプロセス全体で、原料の水素をクリーンな電力で作り、CO2を回収して再利用することで、**「CO2の循環」**を実現します。
合成燃料(e-fuel)が持つ決定的なメリット
合成燃料の最大の強みは、その**互換性の高さ**にあります。
- 既存インフラの活用: 従来のガソリンや軽油と同じ液体燃料であるため、ガソリンスタンド、タンクローリー、貯蔵タンクといった既存の燃料供給インフラをそのまま利用できます。EVのような大規模な充電インフラの新設が不要です。
- 高エネルギー密度: 水素やアンモニアといった他の次世代燃料に比べ、化石燃料と同等の**高いエネルギー密度**を持つため、燃料タンクの小型化や長距離輸送が必要な航空機や船舶での利用に最適です。
- 内燃機関の継続利用: 既存のガソリン車やディーゼル車のエンジンを**改造することなく**利用できるため、社会全体での急激な車両買い替えコストを抑えることができます。
- エネルギー安全保障: 原料であるCO2と水は国内に豊富に存在するため、輸入に頼ってきた化石燃料から脱却し、**エネルギー自給率の向上**と世界情勢に左右されない**安定供給**に貢献できます。
普及に向けた課題と日本の動向
合成燃料の社会実装に向けた最大のハードルは、その**製造コストと効率**にあります。
- **製造コストの高さ**: 現状、合成燃料の製造コストはガソリンの数倍(1リットルあたり300円〜700円程度)と非常に高価です。これは、原料となるグリーン水素の製造コスト、CO2の回収コスト、そして製造過程のエネルギー変換効率の悪さが主な原因です。
- **製造技術の確立**: FT合成プロセスやCO2回収技術の大規模化・効率化はまだ発展途上にあり、大量生産体制を確立するためには、さらなる研究開発と大規模な設備投資が必要です。
- **環境排出物**: カーボンニュートラルとはいえ、燃焼時に**一酸化炭素(CO)**や**窒素酸化物(NOx)**などの有害な排ガスが発生するため、排出ガスの低減や浄化技術の向上が引き続き求められます。
日本政府は、2040年頃の本格的な商用化を目指し、実証プラントの建設や技術開発への支援を積極的に進めています。
特に航空分野では、合成燃料を主とする**SAF(Sustainable Aviation Fuel)**の導入目標が定められるなど、実用化に向けた動きが加速しています。
多くの日本企業が、この合成燃料技術の開発と社会実装に向けたサプライチェーン構築に取り組んでおり、脱炭素社会実現への重要な鍵として位置づけられています。
参考動画
カーボンニュートラルな未来の燃料?!ENEOSの合成燃料製造実証プラントが完成!
まとめ
合成燃料(e-fuel)は、既存のインフラを最大限に活用し、移動体の脱炭素化を可能にする**非常に現実的なソリューション**です。
特にエネルギー密度が高く電動化が困難な分野にとっては、「カーボンニュートラルの切り札」と呼ぶにふさわしい技術といえます。
最大の課題である**製造コストと製造効率**を克服するためには、再生可能エネルギーの大幅な普及と、CO2回収・合成技術のさらなる革新が不可欠です。
日本がエネルギー自給率を高めつつ、世界の脱炭素をリードしていくためにも、産官学が一体となった合成燃料の研究開発と社会実装への取り組みは、今後ますます重要性を増していくでしょう。
関連トピック
e-メタノール: CO2と水素を原料に作る液体燃料の一つで、特に船舶燃料としての活用が期待されています。
SAF(Sustainable Aviation Fuel): 持続可能な航空燃料のことで、合成燃料(PtL: Power to Liquid)やバイオマス由来の燃料がこれに該当し、航空業界の脱炭素化に不可欠です。
カーボンリサイクル: 排出されたCO2を資源として捉え、燃料や化学品などの製品に再利用する技術や取り組みの総称で、合成燃料製造はその中核をなします。
Power to X (PtX): 再生可能エネルギーの電力(Power)を用いて、水素や合成燃料など(X)を製造する技術体系のことで、脱炭素化のキーテクノロジーです。
関連資料
CO2由来液体燃料の最前線: e-メタノール、e-fuel、SAFなど、CO2を原料とする液体合成燃料に関する最新の技術動向や展望を解説した専門書籍です。
合成燃料のビジネス戦略考察 ー カーボンニュートラルに向けた切り札: 野村総合研究所(NRI)のコンサルタントによる、合成燃料のビジネス上の課題と戦略を考察した論考です。
図解でわかるカーボンニュートラル燃料: CO2削減の動向やカーボンリサイクル、次世代燃料について図解を交えて分かりやすく解説した書籍です。