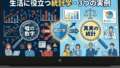「10年に一度の最強寒波」「10年に一度の猛暑」……。
ニュースをつければ、まるでバーゲンセールのようにこの言葉が飛び交っています。「去年も聞いた気がするけど?」「もはや毎年恒例じゃないか」と、モヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。
今回は、この「10年に一度が10回続いたら、それは『毎年恒例』になるのか?」という疑問に対し、感情論ではなく統計学・確率論の視点からズバリ回答します。
結論から言うと、それはもはや異常気象ではなく、統計学的に定義された「新しい常識(ニューノーマル)」なのです。
1. そもそも「10年に一度」の本当の意味とは?
まず、言葉の定義における誤解を解きましょう。
統計学において「10年に一度」という表現は、「10年ごとのスケジュール帳に予定が入っている」という意味ではありません。これは専門用語で「再現期間(Return Period)」と呼ばれ、単年度ごとの発生確率を指します。
P(確率) = 1 ÷ 10 = 10%
つまり、「毎年、神様がサイコロを振って10%の確率(10面サイコロの1の目)が出たらその現象が起きる」という独立した試行(ベルヌーイ試行)です。
今年「1の目」が出たからといって、来年「1の目」が出ない決まりはありません。確率は常にリセットされ、毎年10%なのです。
2. もし「10回連続」で起きたらどうなる?
では、疑問の核心である「10年連続で起きた場合」を計算してみましょう。
今の気象条件(前提条件)が変わっていないとしたら、確率10%の事象が10回連続で起こる確率は以下のようになります。
0.1 × 0.1 × …(10乗) = 0.00000001%
これは「100億分の1」という、天文学的にあり得ない確率です。
統計学の世界では、このような事象が現実に起きた時、「ああ、偶然レアなケースを引いたんだな」とは考えません。
「サイコロ自体がイカサマ」と判断する
100億分の1が起きた時、統計学では「前提条件(帰無仮説)が間違っている」と判断します。
つまり、「たまたま10回続いた」のではなく、「気候システムそのものが変化してしまい、サイコロの目が『1』しか出ないようなイカサマ状態(=気候変動)になっている」と結論づけるのです。
3. なぜ「毎年恒例」になるのか?(正規分布のシフト)
気象データは通常、釣り鐘型のグラフである「正規分布」に従うと仮定されます。
- これまで:その現象はグラフの端っこ(裾野)にある「異常値」でした。
- 10回続く場合:それはグラフの中心(平均値)自体がズレてしまったことを意味します。
これまで「めったに起きない大雪」だった量が、グラフ全体がズレることで「平均的な降雪量」の位置に来てしまう。
これが、異常気象が「ニューノーマル(新しい平均)」に変わる統計的な仕組みです。
4. 気象庁の定義も「上書き」される
実際に、私たちの生活感覚だけでなく、気象庁のデータも上書きされていきます。
気象庁は「平年値(平均的な気候)」を過去30年間の平均で定義しており、これを10年ごとに更新しています(現在は1991年〜2020年のデータを使用)。
もし、「かつての10年に一度クラス」が10年連続で発生し続けた場合、次の更新タイミングでそのデータが「過去30年の平均」にガッツリと組み込まれます。
結論:数値上も「普通」になる
その結果、かつての異常気象は、新しい統計基準において「毎年の普通の天気(平年並み)」へと格下げ(あるいは格上げ)されることになります。
つまり、10回続けば名実ともに「毎年恒例」になるのです。
まとめ:ニュースの違和感は「過渡期」の証拠
最後にまとめます。
- 確率的には:今の基準のまま10回連続で起きることは、偶然としては100億分の1であり得ない。
- 統計的判断:もし起きたなら、それは「異常」ではなく、気候のベースラインが変化したとみなす。
- 結論:データが蓄積され平年値が更新されることで、数値上も「毎年恒例」になる。
ニュースでこの言葉を頻繁に聞くという事実は、「過去の統計データ(過去30年)」と「現在の気候(リアルタイム)」の乖離が大きくなっている過渡期に私たちが生きていることを、統計的に示唆しているのです。